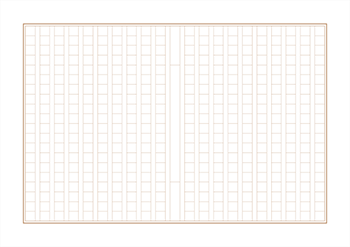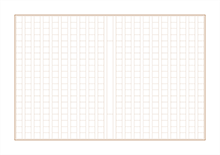お父さんへの作文コンクール入選結果2019~2013
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
小松崎 有美(34) 埼玉県
思いがけない妊娠が発覚した。私が二十四歳の時だった。一番戸惑ったのは主人だった。何せ女手一つで育てられた一人息子である。父親とはどういうものなのか想像でしかわからなかった。ある時、主人が言い出した。
「ねえ、父親って必要なの。」
「え・・。」
私は答えに詰まった。そして絞り出すように言った。
「よくわかんない。うちなんて、判子押す人って感じだったし。」
二人の間に微妙な空気が流れた。
思い返せば幼少期、父はいわゆる仕事人だった。休日といえるものがなく、ほとんど家に居なかった。何をしている人かもよくわからなかった。ただ、仕事で相当くたくたになっていることは知っていた。
父が帰宅し、せっかく温めなおしたおかずもそのままレンジで朝を迎えることは日常茶飯事だった。歳を重ねるにつれ、洗面台に胃薬や漢方薬、冷蔵庫には栄養ドリンクが増えていった。なかなか会えない父とのパイプ役は母だった。塾に行きたい、留学したい、一人暮らしをしたい、結婚したい。そんな時に父は大抵いない。だから母が、
「私じゃわからないから、あとでお父さんに聞いておくわ。」
と言い、翌日には父の捺印した書類がテーブルに置いてあった。
妊娠がわかってから、これまで全く家事をしなかった主人が台所に立ちだした。正直、私がやった方が早かった。それでも、
「俺がやるよ。」
と言われると、両目をつぶってありがとうと言った。
ある日、主人が一冊の本を買ってきた。タイトルは、「イクメンに、俺はなる!」だった。主人の必死さが伝わった。父を知らない人間が父になるということ。これは主人にとって大きなハードルだったのだ。
あれよあれよと言う間に、息子が生まれ、狭いアパートでの三人の暮らしが始まった。はじめはとても新鮮だった。幸せを家族で囲むテーブルは、まるく温かかった。
しかし、二カ月が過ぎた頃、初めての育児のプレッシャーや寝不足から夫婦ともども体調を崩した。さらに追いうちをかけるように、息子は毎晩のように泣き続けた。そんな日が何日も続き、二人の間に会話も、食事もなくなっていった。
そして事件が起きた。深夜零時をまわるというのに、息子が一時間以上泣き止まない。私もめまいが始まった。こんな時に限って主人も帰って来ない。藁をもすがる思いで電話をする。しかし、電源さえ入っていない。これはおかしい。
慌てて外に飛び出るとアパートの階段でしゃがみ込む主人の姿があった。身長百八十センチの体は肩を落とし、小さくなっていた。
「死にたい」
この時はっきりわかった。主人が産後うつになってしまったと。
泣く泣く、母に電話をかけると、
「来なさいよ。お父さんも、ほら、いいわよね。」
「いいんじゃないか。」
電話口でボソッと声がした。父だった。
私たちは逃げるようにアパートを出た。しかし、主人にはかける言葉がなかった。いい父親になろうと必死になり、いつの間にか家庭が窮屈な場所になってしまったのだろう。
そんな私たちの空気を感じ取ってか、父が主人だけを和室に通した。下を向く主人に父は何も言わずにお茶を出した。会話の無い時間が流れて、とうとう主人が大粒の涙を見せた。私は、自責の念にかられた。大事な人にこんな思いをさせ、妻として不甲斐ないと。
主人の涙もまた、自分を責めていた。
すると父が、
「いいんじゃないか。ここにいて。」
そう言って、主人の肩を抱いた。主人は、すみませんと、うなずいた。血のつながりはないけれど、心のつながりがあった。この時主人に「父」ができた。そして父には「息子」ができた。
こうして「息子」と娘は、子供の成長と共にパパとママになっていった。父は、時に見守り、時に手を貸してくれた。
「お前もあの頃はこんなんだったよ。」
そう父に言われ、愛されていたのだと感じた。
居候も半年を迎えようとした時、私たちは小さな一軒家を見つけた。今度こそ自分たちで家庭をつくっていこうと思い始めた。父に告げようと諸々の書類を準備した。しかしその日は父に会えなかった。翌朝も会えなかった。でも、書類に父の捺印があった。驚いた。でも嬉しかった。これは、「いいんじゃないか。やってみろ。」という父のメッセージだと思った。
その印を見ながら思った。あの頃も今も、判子を押す父の手は、私の背中を押す手なのだと。そして、ふと主人のあの質問を思い出した。
「ねえ、父親って必要なの。」
今ならこう言える。もちろんよ、と。だって、迷ったら、背中を押すのはいつも父だからね。
図司 智哉(5歳) 愛知県
パパはいたいところばかりある。パパのいたいところは、ひじとあたまとこしとあしのつけねだときいた。それに、てにはまめがいっぱいある。どうしてまめができたかというと、でんせんをひっぱったからだ。パパのおしごとは、でんせんをひっぱってきて、ちゅうもんのとおりにきるしごとだ。パパは、まいにちうんどうかいをしているようだとわらっていう。それをきいてぼくがおもったことは、おしごとたいへんだろうなということだ。
このまえ、いえで、パパはじてんしゃがパンクしたのでしゅうりをしていた。つうきんはじてんしゃがなおらないとこまる。それでてをまっくろにしてタイヤをかえていた。ぼくはそばでみながらおうえんしていた。
ぼくがパパにおしえてもらっていることがふたつある。ひとつはうんどうで、もうひとつはえをかくことだ。
スクワットやいすおこしなど、ぼくがつよくなるために、へやでできるトレーニングをかんがえてくれた。ぼくはパパにかんしゃしている。ぼくがかぜをひいたときはいつも、パパはトレーニングをするようにいう。それをしたら、かぜがよくなってひどくならずにすんだ。それだけじゃない。ぼくはころんであしをけがしていっしゅうかんいたくてあるけなかった。そのときパパはがんばってあるけといった。ぼくはパパのことばでまたあるけるようになった。
このあいだ、スケッチブックをパパがぼくのためにかってくれた。ぼくがくわがたやきょうりゅうのえをかくと、パパは、
「おう、もっともっとかけ。すばらしい。」
といった。ぼくはうれしいきもちになった。そしてもっとえをかこうとおもった。
ぼくは、
「パパ、いつもおそくまではたらいてくれてありがとう。」
と、パパにいう。
「おう、ありがとう。」
と、パパがいう。
おおきくなったらぼくは、パパに、
「これはいい。」
とみとめてもらえるようなえをかいてパパをよろこばせたい。
堀田 由香(40) 神奈川県
あの時の私にとって、両親は厭わしい存在でしかなかった。
今から二十二年前。十八だった私は、進学という言い訳を引っさげて家を飛び出した。それこそ家を出ようと決意したのは、小学生の頃だった。
片付けが苦手で自己中の性格の母は、いつも私に周囲の人の愚痴を言い、綺麗好きの嫌いがある父は、片付かない家や母の奔放さに腹を立て、酒が入ると手近にあるものを投げつけては、時折窓を壊した。
私にはそんな両親が厭わしく、すぐ物に怒りをぶつける父が恐ろしかった。
父の苛立ちは、当時の私にしてみればいつも突然で、私はたびたび耳をふさいで布団に隠れる夜を過ごした。
投げた何かが窓ガラスを壊し、その破片が散らばる。それは、日常とまでは言わないものの、慣れた光景だった。
高校生のある日、発端が何かはもう覚えてもいないけれど、父に反論すると包丁が飛んできた。
泣き叫んで私に覆いかぶさる母。
たまたま夕食後に母がリンゴを剥いた果物ナイフ。
それが手近にあっただけ。
父は、私の横、畳に突き刺さったそれを拾い上げ、もう一度投げつけた。
そのナイフは再び畳に突き刺さり、結局はだれもけがなどしなかったけれど。
私の中で何かが壊れる音がした。
翌朝畳を見ると、そこには2カ所の傷跡が残っていた。
父も母も、昨日のことは何もなかったかのように平然といつもどおりを振る舞う。
車なしではどこにも行けない封鎖された田舎の町。私は自分の感情をごまかして、その出来事に蓋をした。
窓ガラスが割れて破片が散らばるのは、日常とまでは言わないものの、慣れた光景。
きっとこれも同じような事。
だから笑顔を貼り付けてカウントダウンすればいい。
ここを出ていくまで、あともう少しの辛抱。
高校卒業後、私はやっと嫌で嫌で仕方のなかった家を出た。
学費も家賃も生活費さえも脛をかじって。けれどそれを当然の権利のように甘えて。
全ては家族、両親から離れるため。
進学先は、あえて実家から四〇キロ近くも離れた都心の学校を選び、成人して社会人になると、ほとんど実家には寄り付かなくなった。
偶に帰っても数日の滞在。そしてまた数年訪れない。それを十年以上も繰り返した。
その頃にはもう、父を恐いとは思わなくなっていた。
三十歳で結婚を決めたとき、父は彼にお願いしますと言って頭を下げた。
結婚式でバージンロードを共に歩く父が、顔中を涙と鼻水で濡らしながら「幸せに」と繰り返す。どこかで見たようなお決まりのシュエ―ション。別に何かを図ったわけじゃない。
私はあなたに父親としての名シーンを求めたわけじゃない。
けれど、年甲斐もなく泣きじゃくる父は、記憶にある父とあまりにも違っていた。
二年後、初孫を抱いた父は優しいおじいちゃんの顔で写真におさまり、更に半年後、その写真は遺影になった。
来春、初孫の娘は小学生になる。
もうすぐ、父の七回忌がやってくる。
親になって思うのは、子どもはなんて自分に近いのだろうかということ。
距離も感情も少しも離れていられない。
優しい親でいたいのに、それだけでいさせてもらえない。
けれど優しい言葉をかけるのは、他人でもできると気づいてしまった。
うわべだけの優しい他人と、感情的な家族の距離。
結局のところ、あんなにも厭わしく思っていた親と、内面的にはほとんど変わらないであろう自分。
あぁ、なんて身勝手で自己中心的なんだろう。
もしかしたら父も、本当は優しい父親になりたかったのかもしれない。
ただ、人間らしい人だっただけだ。
川底の石が年月を重ねて丸くなるように、きっと父も、十年という歳月で変わったのかもしれない。
自分が親になって、初めて親の気持ちがわかる。
そんな事を誰かが言っていたけれど、これはきっと本当だった。
お父さん。
私は今、お父さんが言ってくれた通り幸せでいるよ。
お父さん。
きっと、ずっと、思い出す。
新徳 由利香(24) 鹿児島県
「私、卒業したら東京に行くから。」
まだ、暑さの残る十月の半ば。当時、鹿児島に住んでいた専門学生の私は父にその一言を告げたあと左頬を殴られた。赤くなった頬から伝わる熱い痛みと、昔からの夢だった上京を否定されたことによる悲しさの痛み。その両方が一気に目から溢れて止まらなかった。十九にもなって泣くなんて。そんな気持ちが心の隅にある中、仲裁に入った母にすがりつくように泣きわめいた。
その日以来、父とは口を利かなくなった。
朝食や夕食の時間は顔を合わせないように時間をずらし、「おはよう」や「おやすみ」の一言すら自然と言わなくなってしまった。家の中の雰囲気は徐々に暗くなり、まるでお葬式の様な日々が過ぎ去った。
年が明けて三月。お互いに口を利かないまま春を迎えた。私は父の事など知らないと言わんばかりの態度で荷造りを済ませ、いよいよ出発の日を目前としていた。親戚や友達にしばしの別れを告げ、気持ちは上京によるワクワク感でいっぱいだった。
出発の日、空港に父の姿はなかった。期待などしていなかったが、最後まで認められることはなかったのだとほんの少し気分が沈んだ。
「行ってくるね。」
そういって母に手を振り、搭乗ゲートへ足を踏み出した。「ピコン」と携帯からメール受信の音が鳴った。待合椅子座り携帯を開くと、「いってらっしゃい。」その一言だけが画面に打ち込まれていた。父からだ。その数十分後に今度は少し長めの文章が私の携帯へと届いた。「大変だろうが、頑張れよ。お前が決めた道だ。父さんはお前の味方だから、何かあったらすぐに電話しなさい。」携帯に不慣れな父が一生懸命打った文字は瞳に留まった涙によってよく読めなかった。けれど、とても心が温かくなって、鼻をすすりながら何十回も読み返した。
あれから四年が経ち、私は地元へと帰ってきた。隣に父は居ないが、このコンクールを機に長く言えずにいたことを伝えようと思う。「お父さん、あの時は自分勝手な行動をしてしまってごめんなさい。そしてこの四年間、私の味方で居続けてくれてありがとう。これからも大好きです。」
高村 晴美(61) 北海道
93歳の父にとって一番の宝物、それは母です。
施設に入って二年目の冬、母は病に倒れました。退院後、母は自分の力ではベッドから起き上がること、歩くことができなくなりました。要介護5となった姿は、娘の私の目から見ても哀れでした。
しかし、父は気丈でした。
ヘルパーさんの手をかりて、オムツ替え、着替え、車イスへの移動で父のそばに来た母に対して、耳に口を近づけ「おはよう」と声をかけるその様子は、一天のくもりもない深い愛情のように感じられました。
父はおいしいものを前にすると、「お前さん、食べなさい」と母に言います。
好き嫌いの無い、少し太め(私から見ると少しダイエットした方が・・・)の母が食べるのを、横で嬉しそうに見ている父。
父にとって、自分の妻が笑顔でいることが一番の幸せなのかもしれません。
昨年父は、二度肺炎で入院しました。
病室で父は、「お母さん、どうしている?」と行く度、尋ねました。
母をひとり残して、死ねない、と思ったのでしょうか。
父は無事、退院しました。今の私の夢は、東京オリンピックを両親と共に見る事です。
お父さん、それまでお母さんと頑張って、生きていてください。
大宮 芽生(11) 千葉県
私の父は、コンピューターの仕事をしている。7時半くらいに家を出て、大崎まで行く。私はそんな父を、毎朝、「いってらっしゃい」とか「気をつけて」という一言を父のせなかに向かって言う。そのたびに、父はふり向き、「芽生も学校がんばれよ」とか「ママの手伝いするんだよ」という力がわく一言をくれる。
父は、5人の子どものお父さんである。だから、母の負担をへらすため、毎朝、家族7人分のせんたくをしたり、母が仕事の時は、ごはんをつくったり、時には、遊園地につれていってくれる。だから、家族みんなは、父の事が大好きだ。
そんなある日、母が、おなかの赤ちゃんのために、手術を受けることになった。実は、その手術の日、家族で山梨県の河口湖に行くことになっていた。だから、あきらめた方がいいと言ったのだが、みんながおどろいたことに、父が
「いやオレが子ども5人を連れていく!」
と言ったのだ。そのため、旅行は中止することなく山梨県に行った。
予想していた通り、末っ子をおぶい、おさないこをベビーカーに乗せ、三人をベビーカーにつかまらせ、堂々と歩く父の姿に通り過ぎる人がじろじろ見る。だが、父は気にすることなく歩き続けるすがたに私はかっこいい!こんなにやさしくて、心が広い父に初めてそう気づいたのだった。
旅行も無事に終え、母の待つ家に帰ると、なぜだかほっとしてしまった。その理由は、今になって思う。それは、初めての父と子どもだけの旅行に、予想以上に父がはりきっていたからだろうと。
私はまだ父に甘えているが、いずれ親ばなれすると思う。その時は、この旅行のことを思い出したい。
今日も私は、父のせに向かって一言かける。
𠮷田 真彩(15) 愛知県
昔、私は急に手が動かしにくい時期があった。何だろうと思い病院へ行って検査をしたら脳の病気が見つかった。
昔の父はすぐに怒らせると外に出し、謝るまで家に入れてくれないとても怖い人だった。でも病気が見つかってからはとても優しくしてくれて、手術がいやにならないように怒らないでくれたり、たくさん遊んでくれたりしました。
手術の日は朝が早くて休憩するひまがないまま始まりました。私は早くおわりたいので早く行こうとすると、父が抱きしめながら「がんばって行ってこい!」と言ってくれてがんばろうという気になりました。
手術は10何時間はかかって目が覚めた時にはすごく痛かったです。まわりを見た時に机がおいてあり、大好きなハンバーグがありました。どこで買ったのかきいたら、
「ハンバーグが売り切れだったからお店の人に子供が手術していてどうしてもハンバーグが大好きなんです。」
と言ったらお店の人がすぐ作ってくれたそうです。
私はみんなの支えがあって生きているんだと思うとすごくうれしくなりました。
もし父がもう少し年を取って病気になった時には、一番に動いて支えられる人になりたいです。
「父、ありがとう。これからも多変だと思うけど、よろしくおねがいします。」
横川 綾香(17) 青森県
私の顔は父にそっくりだ。生まれた瞬間から…いや、母のお腹の中に居る時から瓜二つ。眉の生え方までもが父譲りなのだ。私は、二重の母に似たかったと思うし、父に似ていると言われることに複雑な感情を抱く。
父は、怒ると当然怖いが普段はいつもユーモアで、私のことを全力で応援してくれている。
私が母に怒られていると、父は最後に必ず「あんまりいう事聞かないと、チューするからな。」と言う。気持ち悪いんだけどと、心の中で思うが、その一言で張り詰めた空気が瞬時に和むのだった。
そして、父は母のことがとても好きで、いつも大切にしている。母も、「パパ、足が臭いし、もぉ~。」などと言っているが、父の事を好きなんだなあというのが娘の私に伝わってくる。父も母も互いに幸せそうに見える。だから私も幸せな気持ちとなる。
そう感じるきっかけとなったのは、父が会社で怪我をして、三カ月半も入院することとなったからだ。それは突然の出来事で、今まで当たり前だった日常が、当たり前ではなくなった瞬間だった。ちょうどクリスマスやお正月・私の誕生日・母の誕生日など、いつも家族で過ごしていたイベントの時期で、父が居ないことによって静かな時を過ごした。
怪我をしたのは利き手で、何をするにも不自由な父の介助のため、母は仕事をしながらも父の病室へ通う日々が続いた。母は疲れているはずなのに、父に会いに行く時は嬉しそうに見えた。
父は退院の日、母はそれまでの不安や心細さが一気に解き放された様に、高熱を出し、一週間ほども寝込んだ。父は寄り添い優しく看病していた。母は安心した表情で、父が傍に居る事が嬉しそうだった。
そういう両親の姿は、とても微笑ましく感じ私も将来、父の様に私を大切にしてくれる人に出会い、愛情に包まれた家族をつくりたいと思う。
鏡をよ~く見る。うん、やっぱり私の顔は父にそっくりだ。複雑な感情は少し薄れ、愛情を覚える。
普段は恥ずかしくて言えないけど…
「パパ、大好きだよ。いつもありがとう」
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
田中 雄大(28)
父は、僕が幼少期の頃に、いつもお酒を飲んでは家で暴れていた。
その頃は、世界で一番好きな母を虐める、僕のまだ小さな世界で一番の悪者で一番怖い存在だった。
僕が八歳の頃に父は、酔っぱらって祖父を殴った。父は、いつも口ぐせのように祖父を尊敬していると言っていた。その日、酔いが醒めると父は何処かへ行ったきり帰って来なかった。
祖父を殴った日から父は、お酒を断ち家族思いの父に変わり、僕の小さな世界で一番のヒーローになった。父はお酒を断ってから、毎週僕と遊んでくれるようになり、毎日のように仕事が終わると僕が好きなかけっこを教えてくれた。
僕は、父がまだお酒を飲んでいた小学生低学年の頃の運動会では、最下位しかとったことがなく走ることがコンプレックスになっていた。しかし、父がお酒を断ってから、かけっこの練習を一緒にしてくれたことで、その年の運動会では、ぶっちぎりの一位を取るようになった。
僕は、父とのかけっこの時間が大好きだった。今思うとずっと父と遊んでほしかった気持ちが、父がお酒を断ってから、今まで我慢していた気持ちが溢れ出したのだと思う。
僕は中学では陸上部に入った。大好きな父が教えてくれたかけっこをもっと得意にしたくなったからだ。
中学になっても変わらず父は、かけっこを教えてくれた。そのおかげもあり、中学では県大会2位になり、さらにレベルの高い地域で陸上をしたくなった。
僕はさらに高いレベルの地域で陸上をするために上京を決意し、父とともに陸上の強豪校に入学をお願いしに行った。営業をしていて弁がたつ父が必死に監督に頼み込んでくれたおかげで入学が決まった。
高校では、かけっこから、走る競技にレベルアップしたこともあり、父から走り方を教わることはなくなった。
高校1年生の終わりに、上下関係やスポーツ強豪校特有の練習が辛く、父にもう退部したいと相談した。
父は一瞬悲しそうな表情になったものの、すぐに顔を上げ、僕に「一度逃げることを覚えると次も逃げるぞ。」と言った。
この父の言葉が僕には重く、後の人生でずっと大切にしている宝物になった。
この言葉は、かつて父がお酒を中々断てず、葛藤していた時に、ずっと自分に言い聞かせていた言葉だと高校生ながらに気づいた。
父は、酒を飲んでいるときも悪い父ではなかった。父は、この言葉を自分に言い聞かせながら、お酒を飲んでしまう自分と家族を思う気持ちで葛藤していたんだと思う。僕は、もう一度逃げずに頑張ろうと決めた。
それから僕の高校がリレー種目でインターハイを二連覇し、僕が高校三年生になると高校史上初の三連覇に三走として挑戦することとなった。
そして、きたるインターハイ決勝。ついにこの時がやってきた。父がお酒を断ってから、二人でかけっこを練習した大切な思い出が、いまや全国で一番かけっこが速くなることに挑戦ができている。
人生で初めて胸が躍動した。なんとしても金メダルとトロフィーを父にわたしたい。その一心でスタートへ向かった。
結果は三位。銅メダルであった。父は会場で見てくれていた。その日の夜に父が泣くところを始めてみた。僕の走りに感動して泣いてくれたのだ。
父が、高校一年生の頃に辞めたいといったときにすごく迷ったと言った。ただ、辞めなくて良かったな。父にとっては、この銅メダルは金メダルと同じだ。ありがとう。と言った。父がお酒を断って十年目の出来事であった。
それから約五年の月日が経ち、僕は大学を卒業し、総合商社の営業で全国を駆け回っていた。
ある日、利益ばかりを追う日々に心が追い付かなくなった。僕の仕事のやり甲斐はお金ではないと感じつつずっと働いていた。
社会人となり、二年目の夏の夜に、会社の寮の近くの公園に行き、ブランコに腰掛けながら思いに老けた。僕は、今の仕事が好きなのかと。
そんな時に父がお酒を飲んでいた頃にお世話になった地域の方や、断酒会の方、学校の先生などを思い出した。僕は、あの頃にお世話になったように、今度は僕が地域の役に立ちたいと思い市役所職員に転職することに決めた。
市役所職員を目指した採用試験一年目。これまでスポーツばかりやってきたこともあり、勉強でほかの受験生に追いつけず、とにかく落ちた。この時はもう市役所職員として働きたくてたまらなくなっていた。
そして一年公務員試験浪人をして、市役所職員を目指して二年目。父がお酒を飲んでいた頃に住んでいた市役所の募集に、スポーツで結果を出した人の採用枠というものがあった。その募集の条件が、全国大会三位以内入賞であったのだ。
父が、僕が高校生の頃に「いつか、この経験がお前を助けてくれる。」という言葉が現実となった。
僕は、この時に受かった市役所に入庁して今年で五年目。今、この大好きな仕事ができているのも、父があの時にかけてくれた言葉があったからだ。
僕は、酒を断ち、一生懸命お父さんをしてくれた父を尊敬している。お酒という父を悪者に変える魔物に打ち勝ち、僕のヒーローになってくれた父。僕の道しるべになり、いつも教えてくれた父。ありがとう。今度は、僕が父となる番となったけれど、僕は父のような父になりたい。
大西 賢(44) 東京都
中学二年のバレンタインデーの日に、チョコをもらった。受け取った瞬間、ものすごくドキドキしたのを覚えている。チョコをくれたのはカナコさんという優等生の女の子で、私のことを慕ってくれていることを知ってからはまともに顔も見られなくなった。
(ホワイトデーのお返し、どうしよう)
真っ先にそれを思った。何しろ中学二年である。同級生たちからはやしたてられるのはほぼ間違いなかった。カナコさんはこっそり渡してくれたが、私も同じようにこっそり返せるだろうか。
十四歳の私はだんだん怖くなってきた。お返しを渡すところを見られて同級生たちに茶化されるのも怖いし、それによってカナコさんを傷つけてしまうのも怖かった。お返しをうまく渡せてカナコさんと仲良くなっていくのも、それはそれで怖かった。
(お返し、渡すのをやめよう)
私はそう決めた。たかがバレンタインじゃないか。もうすぐ受験だし、こんなことに気を取られるのは良くない‥。そう思うことにして、私はお返しのことは忘れることにした。
ところがチョコの一件は妹から母へ、そして母から父へいつの間にか伝わっていた。
「お前、ホワイトデーのお返しはどうするんだ?」
ホワイトデーの一週間ほど前に父からそう聞かれて、私はうろたえた。だが、ごまかしてもしょうがない。正直に言った。
「俺、お返しは渡さないよ」
すると、普段は優しい父が厳しい口調で切り出した。
「相手の女の子の立場を考えなさい!どれだけ勇気を振り絞ってお前にチョコを渡したと思ってるんだ!お返しを渡すのが恥ずかしい気持ちは分かるが、どんな渡し方でもいい。必ずお返しを渡してこい!」
いつもはおっとりしている父が厳しい剣幕で言ったので、びっくりしてしまった。
その後、父は落ち着いた口調でこんなことを話した。何かをいただいたら必ずお返しを渡す。それは、これからお前(私のことだ)が社会で生きていくために、必ず守らなければならないルールだ。それは単なる物品の授受ではない。相手の気持ち、相手の優しさを受け止め、それに感謝を表すという、人としてやっておくべき決まり事なのだ。
そんなことを言った後、周りに母がいないことを確かめながら、父は言った。
「父さんと母さんは全然夫婦ゲンカしないだろう?なぜかというと、母さんから何かをしてもらったら、俺は必ずお返しをしているからだ。『ありがとう』という言葉でもいい。そっと手を繋ぐのでもいい。とにかく相手に優しくしてもらったら、必ずそれに応える。そうしているから父さんと母さんはいつも仲良しなんだ」
それを聞いてなるほどなと思った。確かに父と母はいつも仲良しで、夫婦ゲンカというものは一切しない。その裏には、きちんとしたルールが守られているからなのか。
ホワイトデーの日、緊張で胸が張り裂けそうななか、私は校庭の片隅でカナコさんにキャンデーの詰め合わせを渡した。カナコさんは真っ赤な顔をして、黙って受け取ってくれた。
父とのあの時の対話は、私に社会のルール、そして人間同士の交流の仕方を教えてくれる、とても貴重なものだった。
あれから三十年近くたち、カナコさんではない女性と私は結婚したが、夫婦ゲンカをすることもなく、仲良く過ごしている。全て父のおかげである。
父さん、あのときはありがとう。
藤本 ゆきな(27) 愛知県
お父さん。お父さんが病気だったと知ったのは、会えなくなって五年以上たってからでした。元々、ベタベタ甘やかすのは得意でなかったのか、少しはなれて見守ってくれていたお父さん。おんぶやだっこに肩車。おねだりするのが恥ずかしくて、なんども寝たふりをして、運んで貰うのを待っていたんだよ。気づいていたのか、いなかったのか。
「布団で寝なさい。風邪ひくよ。」
と、いつもだっこして運んでくれたね。目を閉じた私に、「重くなったな」とか「可愛くなってきた」とか。どんな顔で言っていたのかな。薄目を開けたら、寝たふりがバレそうで、結局一度も確認できなかったな。アルバムやビデオの中のお父さんは、いつも不器用に笑っています。私の不細工な笑顔は、絶対お父さんに似たんだと、今でも鏡を見るたび思います。約六年半。短い間だったけど、私はお父さんの子に生まれて幸せでした。愛してくれて、ありがとう。
伯父さん。伯父さんは、我が家が母子家庭になるとすぐ、当たり前のようにお父さん役になってくれましたね。学校行事への参加や、進学時の保証人、果ては結納代わりの食事会にも、当然のように参加してくれましたね。伯父さん一家と我が家で、子供は全部で六人。私が一番年上だから、お父さんとしての初めては、私が一番多くもらってしまったかもしれません。自分の子どもと分け隔てなく、いつも優しく、厳しく、育ててくれましたね。八年にも及ぶがんとの闘病中、じぶんがどんなに辛くても、どんなに苦しくても、いつだって周りを気遣って、最後の最後まで、温かく接してくれましたね。伯父さんから、大切な人たちを守る強さと優しさを学びました。育ててくれて、ありがとう。
おじいちゃん。「朝はおはよう」「お世話になるときはお願いします」「何かしてもらったらありがとう」「悪いことをしたらごめんなさい」「戸はピシッと閉める」「人のワル(悪口)は言わない」「背筋を伸ばして行儀よく」我が家の骨として、かわいい孫にもしっかり厳しく、“当たり前”を教えてくれましたね。中学・高校と不登校になった私に、きっと聞きたい事や言いたい事、たくさんあったでしょう。でも、自分からは何も聞かず、何も言わず、ただただ信じて待ってくれましたね。ある日、泣きながら早退して部屋にこもって居たら、
「こんなもんしかできんで悪いけど」
って、お昼ご飯をもってきてくれましたね。白いご飯と、厚切り焼の焼きハム、それから、黄身と白身が混ざり切っていないスクランブルエッグ。おじいちゃんの世代の男性が、台所に立つ意味、その優しさに、今になってやっと気がつけました。おじいちゃんが作ってくれた、私の中の“当たり前”は、今も私を真っすぐ支えてくれているよ。信じて、支えて、教えて、見守って。私の芯を作ってくれて、ありがとう。
お義父さん。第一声は「誰!」でしたね。初めてご挨拶させていただいた日、玄関を開けるなり「なんだ、フラれたのか。」と不機嫌そうに呟いたお義父さん。大きな夫が陰になって、見えなかった小さな私。ドキドキしながら「おじゃまします」と顔を覗かせると、
「わっ!誰!」とさらに不機嫌顔に。「お前が無駄にでかいから見えなかった」と理不尽に夫を責めながら、ますます皺が寄る眉間。
「楽しみにしていたのにダメになったかと思った」「さっきはびっくりしただけで怒ったわけじゃない」と呟きながら、これでもかというほどお茶とお菓子を出してくださったお義父さん。不機嫌顔が照れ隠しなのだとわかるまで、時間はかかりませんでした。多くは語らないけれど、お家にお邪魔すると必ず玄関まで見送りに立ち「またおいでね」と声をかけてくれる。娘を連れて帰ると、梅干しみたいな笑顔で遊んでくれる。私のことも、もう家族なんだと、背中でそう伝えてくれる。溢れる愛情を日々感じ、感謝しています。
私の四人のおとうさん。私はとても幸せです。私の大切なおとうさん。私のおとうさんになってくれて、本当にありがとう。
中関 令美(19) 東京都
「ホワッツ・ヨア・ネーム?」
父は初めて会う私の友達に聞く。それに対していつも私は即座に、
「ホワッツじゃなくて、ワッツ!もう、ちゃんと英語話して!」
と大声で怒鳴る。
「ごめん」
と言って頭をかく父。
私は父の仕事の関係で幼稚園、小学校、そして高校三年間をアメリカのニューヨーク州で過ごした。六歳になった秋、初めてアメリカに住むことになった時、私の英語力はほぼゼロ。私も初めて会うクラスメートに
「ホワッツ・ヨア・テーム?」
と聞いていた。しかし、月日はたち、英語を幼稚園で遊びながら覚えてしまった私は、英語を流暢に話すようになった。英語が上達して、アメリカ人のように英語を話せるようになった私は、父のジャパニーズ・イングリッシュが嫌でたまらなかった。父がレストランでもう一本フォークを頼むと、コーク(コーラ)を店員さんが持ってきた。タクシーで家に帰ろうとすると、RとLの発音の違いが苦手な父は、当時住んでいた家がある道、「ベーロード」ではなく、全く違う町の「バーリーロード」に連れてかれた。そんな英語が喋れない父を私は恥ずかしく思い
「私の友達と英語で喋らないで!」
と父に向かって怒鳴ったこともあった。父はいつも小さな声で、
「ごめん。」
と謝った。
私がアメリカの高校を卒業したと同時に父は日本に戻ることになった。帰国まで数週間のある日、父は私と妹をニューヨークで働いていたオフィスに招いてくれた。
「あんなに英語が喋れないのに、一体どうやって外国人の社員と仕事をしているのかな?大丈夫なのかな?」
と妹と半分父のことをバカにして笑いながら会社に向かった。しかし、その日、私が見た父の働く姿が私の考え方を大きく変えた。
オフィスに入ると、色々な国の出身の方が私たちを笑顔で出迎えてくれた。父のデスクの前に座っていたのは、日本人の同僚。隣で働くのはインド系の方。斜め前に座っていたのは中国人。後ろのデスクでコーとーを片手に私たちに挨拶をしてくれたのは、アメリカ人の会社員だった。なんてグローバルなオフィスなのだろう。父はこれから会議だというので特別に参加させてもらった。丸いテーブルのまわりに座る国際色豊かな会社員。右からはインドのなまりの強い英語、左からは中国語なまりの英語、テキサス出身の父の同僚は少しだけ南部のアクセントの英語で話していた。色々な英語が飛び交う。会議のリ―ダー的存在の父のジャパニーズ・イングリッシュが一番よく聞こえた。いつもだったら、
「英語下手だから、喋らないで!」
と叫びたくなるところだが、なぜかその時は気にならなかった。グローバルな環境で身振り手振りを使って、頑張って自分の意見を発信して仕事をしている父をみて、私はとても誇らしく思った。会社での父は輝いていた。そして、父の働く姿は私に大切なことを教えてくれた。
英語をペラペラと話せるか話せないかは、たいして重要ではない。色々なアクセントで英語を話す人がいる、英語での会話では、発音以上にコミュニケーション力や相手と会話をし、それを楽しむ姿勢が大事だ。これからどんどんグローバル化が進み、日本人が海外で活躍することも多くなるだろう。英語に対する苦手意識があったり、発音を不安に感じている日本人に気づいて欲しい。海外の人々と仕事をしたり、友達になったり、会話をしたりすることの楽しさを。間違えたり、失敗したりしても、その経験から学べばいい。コミュニケーションをとりたい、という姿勢さえあれば、相手に伝えたいことはきっと伝わる。父の働く姿は私にこのことを教えてくれた。
いつも私が、
「英語下手だから喋らないで!」
と怒鳴ると、父はいつも
「ごめん」
と小声で謝った。今度は私が謝る番だよ。お父さん、バカにしてごめんね。将来、私はお父さんみたいに世界中の人々と一緒に仕事をしたいな。尊敬しているよ、お父さん。
丸山 かおり(46) 大阪府
最近よく、父を恋しく思う。ちょうど自分が記憶の中の父と同じ年代になってきたからだろう。
私は父が四十歳の時に生まれた子で、だから物心ついた頃の父はすでに老いていて、
「疲れた」
が口癖だった。子供心の無知ゆえに、どうして父はいつも疲れているのだろうと不思議に思っていた。
トラックの運転手だった父は、私を一人残して朝早くから仕事に出かけて、夜遅くに帰ってきた。作業着で帰宅する父は、いつも汗臭かった。
早くに母が他界したため、父は毎日、私の世話や家事に追われていた。だから父はいつも難しい顔をしていて、そんな父のことを、私は好きではなかった。
なぜなら、友達のお父さん達は二十代の人が多く、父と違ってみんな若々しくて格好良かったからだ。どうして私の父はこんなにみっともなくて、年老いているのだろうと思ったものだ。父のことを私の、
「おじいちゃん」
と思う人も多かった。馬鹿にするクラスメイトもいた。からかわれたりすることが嫌で、でも明らかに周りのお父さん達とは違う父のことが恥ずかしくなり、それは私が思春期になるにつれて、嫌悪に変わった。
高校生になると、家には父と二人きりなのに会話は全くなく、父と顔を合わせないよう、時間をずらして過ごしていた。
そんな私のことを、父はどう思っていたのだろうか?
男親が、成長した娘とどう接してよいか分からない、ということもあっただろうし、父は元々ロ下手で、寡黙を美徳とする年代でもあったから、今なお、あの頃の父の気持ちは分からない。
何も言われないのをいいことに、年頃になった私は好き勝手に生きた。就職した大手の会社を簡単に辞めて、二年近く父のすねをかじっていた。その後はずっとフリーターで、給料が少ないことに危機感を抱くこともなく、父との生活を続けていた。十万円程度の給料を良しとし、将来への不安はまるでなかった。
父がいたから。父が、朝から晩まで働いてくれていたから。住む場所や食事、公共料金や雑費に至るまで、何の心配もなかった。父を嫌悪し、感謝の言葉どころか会話の一つもしないくせに、私は大きな顔をして、ふんぞり返って過ごしていた。
本来なら私がしっかり働いて、父に楽をさせてやるべきなのに、黙々と働く父にずっと甘えてしまっていた。六十を過ぎての肉体労働はさぞ辛かっただろうと、今頃になってやっと分かった。
それは自分が年をとってきたからだ。私は今年、四十六歳になる。十年前にその父を亡くし、今は独りで生きている。頼れる人もなく、家族もいない。自分一人の生活を、自分が働いて賄うしかない。それがどれだけ大変なことか、朝出勤するたびに痛感する。もう若くない身体が、心が、辛い辛いと訴える。
そんな時、朝早くから仕事に出かけた父の姿を思い出す。いつの間にか小さく、曲がっていった父の背中。どうして私は、父の辛さを、肉体的な苦痛を、わかってやれなかったのだろうか?なぜ父に、感謝のひと言すら言えなかったのだろうか?父は、どんな気持ちで毎朝仕事に出かけていたのだろうか?
父は七十歳まで働いた。朝食は食べず、昼は運転席で菓子パンを頬張りながら、夜遅くまで荷物を運んだ。耐えられる年ではなかったのにと、懺悔の思いが私を責める。
今なら、今の私なら、父とたくさん話ができるのに。仕事のこと、生活のこと、色んなことが話せて、そして父を支えてゆけるのに。
今頃になって、こんなにも私は父が恋しい。晩ごはんを一緒に食べて、笑い合いたい。私の帰宅が遅くなっても、父はいつも晩ごはんを食べずに待っていた。それは、気持ちを言葉に出せない父の、メッセージだったのかもしれない。
それに応えてやらなかった私なのに、父は最期まで私の心配をしながら逝った。
今ごろになって分かる、父のこと。今さらながらに、父が恋しい。笑い合って、存分に甘えて、父には楽をさせてあげたい。私が娘で良かったと思ってもらいたい。
思いを父に伝える事はもうできないけれど、それでも私は父に言いたい。
「お父さんのこと、大好きだよ。たくさん、たくさん、ありがとう」
根岸 亜矢(32) 埼玉県
「俺だよ。俺、俺。」
こう受話器越しに名乗る男性は、才レオレ詐欺でも、私のパ―トナーでもない。父だ。父が私の携帯電話に掛けてくる時は、いつもこう名乗るのだ。六十をとうに過ぎた父だが、未だに電話では自分のことを『俺』と呼ぶ。
そんな父のことを、私は幼いころ『パパ』と呼んでいた。でもいつからか.『お父さん』と呼ぶようになった。周りの友達が『パパ』と呼ばなくなって、私もなんだか恥ずかしくなり、『お父さん』と呼ぶようにしたのだ。
私には二人の子供がいる。小学三年生と年長の息子だ。長男は、一年生になるころから『ママ』ではなく『お母さん』と呼ぶようになった。次男は、まだ私のことを『ママ』と呼んでいる。でも最近、幼稚園では『お母さん』と呼んでいることを、私は知っている。きっと『ママ』と呼ぶことが恥ずかしく思えてきたのだろう。どうやら私は今『ママ』と『お母さん』の狭間にいるらしい。次男の成長を嬉しく思うが、同時に、もうすぐ私を『ママ』と呼んでくれる人がいなくなるのだろうと思うと、それはそれで淋しいのだ。もしかしたら父もそうだったのだろうか。
父は今、『パパ』でも『お父さん』でもなく『おじいちゃん』だ。長男が喋れるようになって『おじいちゃん』と初めて呼んだ時の嬉しそうな父の顔を、私はハッキリと覚えている。今までで一番嬉しい呼び名なのかもしれないな、と思った。
私も、息子達の前では父のことを『おじいちゃん』と呼ぶ。『お父さん』になってから、もう呼び名が変わることはないだろうと思っていたが、案外ホイホイ変わるものだ。
今度呼び名が変わる時は『ひいおじいちゃん』になる時だろう。どうせならうんと長生きして『ひいひいおじいちゃん』になってもらおうじゃないか。父は『ひいひいおじいちゃん』になっても、受話器越しに
「俺だよ。俺。」
と言うのだろうか。それとも
「わしじゃよ。わし、わし。」
に変わっているのだろうか。その答えを知るには、お互い長生きしなくちゃいけないな。またいつでも電話掛けてきてよね、お父さん。
中島 陽子(45) 大阪府
「今日、何食べたい?」と聞くと、夫は決まって、「陽子が食べたいもんでいいよ」と答える。
私の夫は、食事に対して何も言わない。むしろ作る側の張り合いのためにも、もっと興味を持ってほしいくらいだ。食事のとき、夫の反応を眺めていると、お決まりの平坦なトーンで「おいしい」とは言うのだけれど。とはいえ、食にこだわりのない夫と結婚したのは、父が反面教師になっているのかもしれない。
私の父は「自称グルメコーディネーター」。食べることにしか興味がなく、休日の朝などは、朝食をとっている最中から、「今日の昼はそうめんがええな。錦糸卵とハムと…ネギとミョウガも刻んでや。夜は中華鍋にして。鶏ガラで出汁とってウズラ卵と…」と、母に献立の内容を事細かに指示するのだ。わが家で一番大きな鍋の中に首長竜を小さくしたような鶏ガラが煮込まれていたときの驚きは今でも忘れられない。そんなふうに、日々お店レベルの味を求められたせいか、母の料理はおいしく、私が学生時代のときには弁当を広げると友だちにうらやましがられるほどだった。
「自称グルメューディネーター」は、私が一人、遅いタ食をとっているときにも発動した。食べようとするとどこからともなくやって来て、向かいの席に座り、「それは醤油をつけて。あ、それはちょっと待て、辛子がいる」などと、食べ方に指示を下すのだ。そして「うまいか?うまいやろ?」とうれしそうに私の顔を覗き込んでくる。可愛げのない私はいつも「うーん、まあ」とウザさ満開の返事を返していた。
食べるばかりで運動をしない父は、私が小さい頃からすでに糖尿病を発症していた。でも、「食事制限するくらいなら、好きなもん食って死んだ方がマシ」と断言し、一切、食べたいものをガマンすることがなかった。
そんな父が70歳を過ぎた頃、急に食べられなくなった。食べようとしても喉を通らず、しまいには嘔吐するようになった。医者嫌いの父をなんとか病院に連れて行った。結果は胃がんだった。手術もできないほどに進行していた。母と私はうろたえた。まさか、がんだなんて…。
入院すると、父はたちまち病人の顔になった。あんなに食べることが好きだった父が、食べたい気持ちはあるのに食べられなくなった。そんな父を見て、神様は、最後の最後に、人の一番好きなものを奪ってしまうのかと恨んだ。「せめて、あめ玉をなめたい」と父が言うので看護師さんに確認すると、喉に詰まらせないようにあめ玉をガーゼでくるんで、ガーゼの端を口から出してなめさせるようにと言われた。ベッドに座り、ガーゼにくるまれたあめ玉を力なくしゃぶる父。すぐに「もう、ええ」と言ってあめ玉をコロンと吐き出し、またベッドに横たわった。哀れでならなかった。
ろれつも回らず、会話も困難だったけれど、せめて気がまぎれることをと、父と母と三人でしりとりをはじめた。父は「て…てっかまき」「な…なまぎも」と、この期に及んでも食べることばかり言う。おかしくて母と顔を見合わせて泣き笑った。
そして、胃がん宣告から一年を待たずに父が息を引き取った。棺には父が好きだったチョコレートパンの他、しりとりで出てきた鉄火巻きも入れた。天国でいっぱい食べられますように。そう願って手を合わせた。
元気な頃は、人一倍、食い意地の張った父にうんざりしていたけれど、今となってはそれはそれでよかったなと思う。なぜなら、いろんな食材やメニューを見るたびに父との思い出がよみがえるのだ。夏に冷麺の張り紙を見れば、「あの店の冷麺、パパが好きでよく食べに行ったな…」。冬に鍋を食べれば、「『鍋の火を家族で囲むと幸せや…て思うねん』て、言ってたな…」。お肉売り場に行けば、「パパが好きだったセンマイ、豚足…やっぱり私は苦手やな…」。そんな記憶をよみがえらせてくれるのだ。
パパ。今、天国でおいしいものを食べられていますか。ずっと生意気な私でごめんなさい。おいしくて笑える思い出をありがとう。
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
澤登 勇輝(10) 大阪府
「パチン。見て見て、こんなにうまく鳴るようになった。」
ぼくはパパに教わった色々な技をたまに人に見せたくなって、お姉ちゃんやママにみせる。みんなは決まってこういう。
「本当にパパは役に立たない技ばかり教えて。もっと役に立つことを教えてくれたらよかったのに。」
「パチン。パチン。」
ぼくは友達の前でかっこよく指を鳴らす。
「すげー、どうやって鳴らすの?」
友達がよってきた。ぼくは友達のリクエストに応えてゆっくりと指の動きを見せる。一人ひとりのゆびの動きを見てアドバイスをしていった。僕が何回見本をみせても指の使い方がおかしい友達には直接指をもって動きを直してあげる。みんな何日かするとだいぶ指がなるようになっていった。みんなお父さんからアドバイスをもらってたくさん練習をしたらしい。それを聞いてぼくの胸の奥の方でチクリとなにかが刺した。
ぼくは夏の暑い日によくパパとプールへ行った。ぼくがプールに入ろうとしたら、パパが先にプールに入っていて下を向いてうかんでいて全く動かない。
「パパ!パパ!どうしたの。」
ぼくはうきわをつかみあわててそばによりゆすった。そうするとパパがガバッと顔を上げて得意そうに
「びっくりしただろう。これは死んだふりだ。はっはっはー。」
「もうおどろかさないで、おねがいだから。」
ぼくは泣きそうになりながら言う。パパはプールに行くたびにこの技をつかうのでさすがのぼくもこれは死んだふりだとわかってくる。うそだとわかっていてもそのたびに心臓がどきどきする。
「死んだふり、おぼえときやー。」
とパパに言われた。いまだに何の役に立つのかわからない。
「ほら見ててみー。ポン!パックン。」
パパの得意な芸がまた出てきた。
「どうだできるか?」
パパに聞かれたがもちろんぼくはできない。パパは上に小さい食べ物を投げて口に入れるのが得意だ。それをするたびにママに変なことを子供に教えないでと怒られていた。
「やって見るか?」
とパパに聞かれたので、ぼくは嬉しくてすぐに
「やりたい教えて。」
と、おかしをつかんだ。パパはぼくにていねいにコツを教えてくれる。ぼくは何度も挑戦したが、うまく口に入らない。いろんなアドバイスをもらい何日もがんばって、練習していると、少しずつ口の中に入るようになった。思ったように入らなくてくやしかったから、あきらめずに何回も練習を続けた。上を向きすぎて首がいたくなる。そのうちにたまにしか外れないようになった。今ではほぼ百発百中だ。指を鳴らすのも両方の手でできる。
ぼくはうまくなった技をパパに見せたい。でも見せることができない。5年前、ぼくがねている間に突然いなくなった。ゆすってもゆすっても動かないパパを見て僕の涙は止まらなかった。
今、パパがぼくの技を見たらなんて言うだろう。絶対どちらがうまいか競争しているはずだ。そう思うと目の奥がつんとする。
パパに教わった役に立たない技。家族の中でできるのはぼくだけだ。パパがぼくにだけ教えてくれたとっておきの技だ。おかげでどこにいってもすぐ友達をつくれるし、周りの人を楽しませることもできる。
嬉しい時も悲しい時もぼくは指をならす。パパがすぐそばで笑っているように感じるからだ。ぼくがおとなになって、いつかお父さんになったら子どもにきっとこれらの技を伝授しよう。きっとね。パパ見ていてね。
「パパ、大好きだよ。」
鎌田 誠(68) 北海道
私の忘れられない思い出は、たった一枚の数秒の画です。
上野発の夜行列車が青森駅に着いて、連絡船に乗るために桟橋に向かうあの通路です。いまはもうありません。
五十年前の三月、私は東京での大学受験を終え、浪人生活を覚悟して落ち込んでいました。国鉄職員の父は受験について何も言いませんでした。
母から、出来れば小樽の自宅から通える札幌の公立へ、東京へは国立で寮に入ることといわれていました。貧しかったのです。その頃は、国立大学は一期、二期と二回受験することが出来ました。それも一期の合否がわかって二期を受験というシステムでした。父も母も合格を信じていました。ラジオで表された合格発表で、私の受験番号はありませんでした。青春時代は戦争中で、充分な教育が受けられず、戦後子供たちの成長と教育に命をかけてきた父と母。
函館行きの連絡船に小走りで急ぐ人の波の中、私が見たのは、通路の端に立っている父でした。どうして父がそこに居るのかすぐにはわかりませんでした。
父は何も言いませんでした。
ただ私をしっかりと確認しただけでした。
私がどの汽車に乗りどの連絡船に乗るか父は知っていました。家族割引というのが国鉄職員の家族は使えました。大切な福利厚生制度でした。父も職員証を見せるとどの列車も乗れました。本当は普通列車だけだったのでしょうが、当時の国鉄一家の慣例でした。もちろん仕事を休み、そこに居てくれたのです。そこに駆けつけてくれて、寒い桟橋で待って居たのです。
その父の想いを優しさを本当に解ったのは、私が結婚してわが子を抱いてからでした。どれだけあの時、父が私のことを心配してくれていたのか。
九十歳で父は亡くなりました。八カ月の介護の末、あっけない最後でした。
「何にも遺してやれなくてゴメンな」
それが父の最期の言葉でした。
その父にあの青森駅の出会いのお礼を言えませんでした。
四十九日の納骨にやっと「ありがとう、お父さん。曾孫も生まれますよ」言うことが出来ました。
お父さん、北海道に夢の新幹線が来ました。グリーンとラベンダーラインのかっこいい車両です。お父さんの爺ちゃんが、ニシン漁で一旗揚げようと、北海道へ渡ってきたという弘前へ行ってみましょう。弘前城のお堀に浮かぶ花筏は見事だそうです。連絡船でなく、あの津軽海峡の下のトンネルを潜って通っていってみましょう。優しいお父さんでありがとう。
冨樫 正義(31)
六五歳で退職した父。旅行が好きで、老後生活を楽しみにしてきたことだろう。馬鹿が付くほどに真面目な性格で、一生懸命に頑張ってきたからかどうかは分からないが、早々に難病のパーキンソン病と診断された。
最初は、手足の不自然な震えから始まり、貧乏ゆすりのような震えが全身に起こるようになった。そして、ついには、肩より上に腕が上がらなくなった。当然、車の運転は、もうできない。腰も曲がり、この数カ月で私の知らない父へと変貌していった。正直、その姿を見ていることが辛く、なんと声をかけていいものかと、躊躇うことも多くなった。それでも、父は、寝たきりになって家族に迷惑をかけないようにと、リハビリに励んでいる。
地元を離れて生活している私だが、書道を趣味にしており、毎年地元の書道展に出品している。そして、毎年欠かさず、父が書道展に足を運び、私の作品だけでなく、入賞作品のすべてを撮影し、作品づくりの参考になるようにと送ってくれるのだ。しかし、今年は全身が震え、肩より上に腕が上がらなくなってしまったので、写真撮影どころか、書道展に足を運ぶことすらできないのではないかと心配していた。それでも、自分で決めたことは何があっても継続する芯の強さを持つ馬鹿真面目な父は、私の作品を鑑賞するために、今年も書道展に足を運んでくれた。そして、毎年の習わしの如く、すべての入賞作品と私の作品の写真データをパソコンから送ってきてくれた。写真を見ると、肩より上に腕が上がらなくなったことがハッキリとわかるような下から上を見上げるような写真になっていた。もちろん、全身が震えるような状態だから、ぶれた写真もあり、斜めに歪んだ写真がほとんどだ。それでも、「ないよりはマシだろう」と写真を送ってくれた。私の作品の写真に関しては、何枚も撮り直し、できるだけ真っすぐしっかりとした写真を撮ろうと努力が分かるほど、何枚も似たような写真が送られてきた。送られてきた写真を目にした私は、言葉を失い、目から涙がこぼれおちていた。これが、父の愛か、と噛み締めながら、自分がいかに愛されて、幸せだったのかを思い知らされた。
もしかしたら、今年の書道展は、父が足を運ぶ最後の書道展になるかもしれない。そう思うと、まだ一度も入賞作品として展示されたことがない自分自身が情けなくなった。毎年、何年も、欠かすことなく、すべての入賞作品の写真を送ってくれていたにも関わらず、たったの一度も、私の作品は入賞作品として父の目に触れたことがないのである。年に四度は書道展に足を運び、その都度、すべての入賞作品の写真を送ってくれたにも関わらず、今日までただの一度も入賞することがなかった自分の不甲斐なさばかりが際立ってくる。次こそは、父の目に入賞した自分の作品を必ず刻むと練習に身がはいる。練習量、書き込み量ならば誰にも負けない。師範を超え、今年は最高位となる成家試験にも合格した。しかし、それでも、地元の書道展での入賞は過去一度もない。私以上に、父はそれを知っている。私の努力も、私の結果も、すべてを父は見届けてきた。だから、きっと、「今年こそは」の期待とともに、深刻な体調にも関わらず、足を運んでくれるのだろう。いつ、父が書道展に足を運べなくなってもおかしくはない。寝たきりになることも覚悟しなければならないほど、症状の悪化は深刻である。
「父さん、約束するよ。今年の秋の書道展では、必ず入賞作品として展示された姿を、見せるから。書道展の恩は、しっかり書道展で返すよ。」
中山 雄陽(6) 高知県
「いってきます。」といってパパはでかけていこうとします。
ぼくはびっくりしました。パパは、そのときかぜをひいて、すこしおねつがあったからです。
「やすみや」とぼくはいいました。すると、パパは、
「しごとやきやすめん」と、いいました。そのときぼくは、えらいと、おもいました。
パパはほてるではたらいています。そのひ、パパはやきんでぜったいやすめませんでした。
ぼくはパパをみて、かわいそうとおもいました。
「パパかわいそう」と、ぼくがいうとパパは「だいじょうぶ」といってでかけていきました。ぼくはパパがだいすきです。
しごとでつかれていても、いつもいえにいるときはあそんでくれます。こんなパパは、ままにもやさしいです。
ひるもよるもはたらいてかぞくをまもってくれるパパ。
ぼくは大きくなったらパパみたいにやさしくて、つよいひとになってかぞくをまもりたいです。パパいつもありがとう。
田中 加奈(34) 東京都
私は物心ついた時から、玄関を開けたあと必ず一番初めにすることがあった。
「あ!あった!」
玄関に父の靴が置いてあったときの、言葉では表せない、うれしく飛び上がるようなそんな気持ちを、今でも鮮明に覚えている。
「ただいま!」きっとその声はいつもよりずっと生き生きとしていたに違いない。「お!おかえり。」仕事帰りの父の笑顔と声に、ばんざいしたくなっていたのだから。
私の父は、昔から子どもに甘く、母に怒られると必ず自分の味方になってくれた。『ええやないか』が口ぐせで、穏やかな口調で話す内容は、多彩で楽しくて元気になれた。中学生、高校生になると照れて態度に表すことは少なくなっていたが、父が家にいてくれるだけで、私は何となく安心できたのだ。だからこそ、その父の存在の有無を示してくれる、父の”靴”は、私にとって少しずつ特別なものとなっていった。
大きくなるにつれ、そんな風に父の靴を見ていると、だいたい父の”勝負靴”がどれなのかわかってくる。大事な商談がある時、気合を入れるべき時、たいてい”それ”をはいていた。
私が大学生の時、初めての一人暮らしではめをはずしていた時期があった。そんな時、突然父が「仕事でたまたまな」と訪ねてきた。そして私は、父に初めて真剣に怒られた。一緒に飲みながら、普段とは違うトーンで静かに話す父の気持ちを聞いた。そして最後に、「お父さんな、加奈がどれだけがんばって大学入ったか知ってる。そんな娘であること、本当に自慢に思ってるんやで。」
反省と自己嫌悪で眠れない夜を過ごした次の日の朝、ふと玄関を見ると父の靴はあの”勝負靴”だった。「父は覚悟を持って、私のためにここまで来てくれたんだ。」父の気持ちが痛いほど伝わってきた瞬間だった。
また、私の結婚式当日の朝だった。「もうしばらくは見納めだろう」と、今日のために用意した父のピカピカの靴をしばらく眺めながら泣きそうになるのをこらえていた。そして決心をし、昨夜遅くまで考えていた“娘”としての最後の感謝の言葉を、ちゃんと三つ指をつき、両親二人に伝えようとしていた。
と、その時。「あれ?お父さんの携帯がないんとちゃうか」と父。昨夜、親戚一同と飲んでいて酔っぱらって帰ってきたためか、どこに置いたか記憶にないと言う。父は「あ、マナーモードにしてるわ。」と言う。会社の取引先の連絡先も入っているという大事な携帯。「えらいこっちゃ」と家族全員で探索。見つからない。
そうこうしているうちに、私は準備のため式場に向かう時間になってしまった。私はいろいろな意味で後ろ髪を引かれる思いで家を後にした。結局、本と本の間にはさまっているのが見つかったとしばらくして連絡がきた。
私は今でもあの時、父は私に面とむかって”最後のあいさつ”をさせないように仕組んだのではないかと疑っている。それくらい父にとって私が家を出ていってしまうという事実は、切ないもので、娘の私にはそんな気持ちを悟られたくなかったのかもしれない。その証拠に、私が「結婚したい」と式の日どりを決めてから一週間、仕事帰りの私が、玄関に父の靴を見ることはなかったのだから。
そんな父から、久しぶりに連絡がきた。内容は、父が今探している”新しいビジネスシューズ”についてだった。どこの靴屋に行っても在庫切れらしい。調べてみると、デザイン性よりも機能性を重視したものだった。『歩いても疲れにくい』というウリのそれは、父の年齢を物語っているようで、私は少し切なさを感じた。
帰省するといつも私に、笑いながら「太ったんとちゃうか?」と言う父。私は「そっちは白髪も増えて、うすくなったね。」と心の中で返す。帰るたびに、しわが増えてる気がするが、父の好きな言葉、「お父さん、まだまだ若い格好して、元気でなによりね。」と返していること、気づいているだろうか。
そんな私は、父の電話で改めて、父の重ねてきた年齢を実感することになったことに
少し戸惑いを感じながらもその靴を懸命に探すことになったのだ。そして期待した通り、次の帰省時には、それが玄関にあった。私はやっぱり昔と変わらぬ気持ちでそれを見た。
「ただいま!」
「お!おかえり。」
私は父が大好きだ。今も昔もその気持ちは変わらない。父は知っているだろうか。私の娘が父に遊んでもらう姿を見て、私が昔の自分と重ねていること。孫に優しく楽しそうに接している姿は、私の遠い記憶の父を思い出させることを。
そんな理想の父。夫にも娘にとってのそのような父になってほしいと思っているが、その話をした時、母に言われた。「お父さんみたいな人はそうそういないよ。」そうなのだ。それはわかっている。けれど、違う形ではあるだろうが、娘にとって夫もそういった存在になってほしいと心から思っている。幼い私が、父の靴を見つけた時に感じた、あの飛び上がるようなうれしい気持ちを娘にも持ってもらえたら。それは今でも私が、父に思いを馳せる時に感じる、なにものにも代えがたい幸せな気持ちになれるから。
お父さん、今までこんなに自分の靴が娘に見られているの、知らなかったでしょう。で
もきっとこれからも私は実家の玄関を開ける時、昔の私と同じ気持ちになると思う。お父さんの”娘”であることに幸せを感じながら。だから、いつまでも可能な限り“靴”を玄関に置いておいてよね、お父さん。
小山 しず枝(62) 山口県
「♪疾風のように表われて 疾風のように去ってゆくー。」まるで、月光仮面のようで
した。父には、困った時、何度も即けられました。その中で、今でも心に残る3つの出来事があります。
一つ目は、小学2年の時のことです。転衣してすぐの頃。下夜途中の家に住む上級生の男の子が、顔を合わせる度に大声でからかったのです。今思うと、ワンバクな男の子で、単純なイタズラだったと思いますが、2年生の私は、とてもイヤでした。
そのことを父に話しました。それから、数日後、父が言いました。「あの子に、箱いっぱいアイスクリームも持っていったからね。」
習日通ると、男の子の態度が変わっていました。何も言わず、ニコニコとして上きげんです。父がアイスクリームを渡す時、何と言たのかわかりませんが、私の悩みは、すうっと解決しました。父、42才の時でした。
二つ目は、結婚して2人目の子を産んでまもなくの頃のことです。産まれた子が熱を出しました。上の子も一下半通ぎで、まだまだ手がかかります。夫もちょうど出張中で、助けがありません。無理と知りつつ実家に電話しました。母が言いました。「じいちゃんがもうすぐ帰るから、行くと言うかもしれん。」
真っ暗になった夜8時頃、アパートの庭側のガラス戸をたたく音がしました。父でした。それを見て、じいちゃん子の上の子が、飛びつくのを見て、「ほうっ。」と肩の力が抜けていったのを覚えています。
父は退職後、フェリー乗り場の車の誘導の仕事に就きました。あの日、夜7時まで働き、自転車で20分かけて帰り、それから、夕クシーを飛ばして我が豪に駆けつけてくれたのでした。父、64才の時でした。
三つ目は、義父が亡くなった時のことです。近くに葬儀会場が見つからず、家で葬儀を行うことになりました。夫も、諸々の連絡や打ち合せで余裕がありません。一子供も、長女小6、次女小4、長男小1。これから、短時間で二部屋の物を片づけ会場を作らなければならないと途方に暮れていたのです。
その時に父は現れたのです。ひょうひょうとした顔で孫達と一緒に机などあらゆる物を倉庫や他の部屋に移動し、ガランとした部屋を作ってくれたのです。今でも次女は言います。「あの日、じいちゃんが葬儀の部屋を作ってくれたね。」父、74才の時でした。
いずれも、母と話し合っての行動だと思いますが、間髪いれない動きの速さは、見事だったと思うのです。
その父も、90才で旅立ちました。亡くなる数ヶ月前まで、車で15分かかる道を、自転車でこいでゆく達者ものでした。
難しいことは言わず、困っている人がいると、ヒヨイと助ける。まさに「疾風のように現れて、疾風のように去ってゆく。」そんな父でした。きっと、孫にとっても「スーパーじいちゃん」だったと思います。
私もあと数ヶ月すると、初孫を抱きます。父には到座及びませんが、私流の「スーパーばあちゃん」めざせたらなあと思い始めました。
もうすぐ、七回忌。
「フットワークの軽さだけは遺伝しているよ。みていてね、お父さん。『さすが、ワシの子じゃ。』と言わせてみせるから。」
大西 賢(43) 東京都
高校一年生の夏休みに、生まれて初めてアルバイトをした。製本工場での作業で、お金を稼ぐことの大変さをしみじみと思い知った。
一ヶ月ほどの短期アルバイトで、最終日には八万円ほどもらえる計算だった。人生で初めての給料である。もらう前からワクワクした。そして同時に思った。何に使うのが一番いいだろう―。
十六歳、高校一年生である。同級生でアルバイトをしている者はほとんどおらず、給料の使い道について相談できる人はいなかった。仕方ない。私は製本工場で働く正社員のおじさんに相談してみた。
「初めての給料の使い道といえば、両親へのプレゼントだろう。俺たちの世代はみんなそうだったなあ」
父親ぐらいの年齢のおじさんは、笑ってそう言った。初めての給料は両親へのプレゼントに使う―。そういえば、よく聞く話だ。それが日本の文化なら、私もそれに従おう。
今から三十年近く前のことだ。給料は現金で手渡しだった。事前の計算よりかなり多めに現金が入っていた。その夜、帰宅した私は早速、両親に何が欲しいか訊いてみた。
すると、父がこんなことを言った。「お前、初めての給料で俺や母さんにプレゼントを買うようなマネはするなよ」
え、なんで―。
「初めての給料はお前にとって大切な記念だ。お前のために使え。父さんも長く働いてきたから分かるが、自分へのご褒美をきちんとしないと、次に働く意欲が湧いてこなくなるものなんだ」
そういうものなのかな―。
「お前、本当は一人旅がしたかったんだろう?夏休みはあと一週間ある。初めての給料で一人旅をして、楽しい思い出を作ってこい。元気に帰ってきたら、それが父さんと母さんへのプレゼントだ」
私はもう何も言い返せなかった。一人旅がしたかったのも事実で、アルバイトから帰ってくると、いつも私は自室で旅行のガイドブックを見ていた。父はそれを知っていたのだ。
父の教えに従って、私は初めての給料で一人旅をしてきた。そして、お土産として湯飲みを買って帰ってきた。両親はそのお土産をとても喜んで受け取ってくれた。「汗を流して働いたのはお前自身だ。初めての給料はお前のために使え」
十六歳の私にそう言ってくれた父に、今でも感謝している。
そして、あれから三十年近く経つのに、未だにあの湯飲みを使い続けている父を見ると、すごく嬉しくなる。
久保田 莉奈(20) 兵庫県
私の父はある意味、能天気な人だ。でも私はそのような性格の父が羨ましい。私は細かいことに執着し、悩む。その時父に相談すると、いつも笑顔で「大丈夫よ」と言うのが口癖だ。私の心の中は父の軽々しい態度に対しての腹立たしい気持ちが勝つと思いきや、羨ましさが勝つのだ。
今は、愛媛と神戸と離れているが、毎日電話もし、メールもする。周りからはただのファザコンだと思われるかもしれないが、私は父の存在に助けられている。毎日連絡を取り合うことで、私の様子をわかってくれ、気分が落ち込んでいるときはすぐに気が付いてくれる。そして、父の口癖の「大丈夫よ」を聞くと安心するのだ。だが、父は能天気な分、何か大きなショックな出来事が起きるとすぐ顔や声に出る。私は、なんて言葉をかければいいのか分からず、父のような「大丈夫よ」と言う事もできず、ただ見守るだけだ。でも、父はすぐ立ち直り、前に進む。次の日、何事もなかったかのように仕事に行き、私に元気に連絡をしてくる。そんな父が誇らしいし、大好きだ。
そして、私たちの自慢は二人で買い物に行くことだ。ほとんど私の化粧品や洋服を選びに付き合ってくれるのだが、父は嫌な顔一つしない。むしろ「楽しい」と言ってくれるのだ。私が洋服を好きなせいか、父もレディースブランドに詳しくなった。私の好きなテイストと、父の好みは違うけれど、買い物のとき、その好みの違いで言い合いになる空気が好きで、楽しんでいる自分がいる。さらに父は、フレンドリーなため、行きつけの洋服屋さんの店員さんともすぐに仲良くなる。そのおかげで、私も楽しく面白く洋服を選ぶことができ、買い物をせず談笑して帰ることもある。だが、最近父を悩ませる出来事がおきたのだ。それは私がもう二十代ということもあり、街で知り合いの人に会うと勘違いされるらしい。父が、若い飲み屋の姉ちゃんと歩いていたと。それを防ぐために、知り合いの人に会うと必ずすぐに「私の娘です」が口癖化している。その様子が面白くて、可愛らしくて、愛おしい。きっと、母はこんな父の性格を好きになったのだなと、今頃気づいた。
私はこれからもこの能天気な大黒柱を信じ、前に進んでいきたい。そして、私は年をとっても父と二人で堂々と買い物に行けるような関係を続けていきたい。
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
市村 朋子(23) 奈良県
父と二人でお酒を飲んだ。
大学院に進学することが決まった私のために、父が引っ越しの手伝いをしに来てくれた日のことです。
私はこれまで、両親から「こうしなさい」と言われた覚えがありません。「どうしたらいいと思う?」と相談しても「朋子さんの好きなようにしたらええ」とそっけなく言われていました。愛情は感じます。大切な家族として思ってくれていることも知っています。けれど、『私ら親も一人の人間・あんたも一人の人間』という考えのもと、私のことに深入りしてこない両親でした。なので、「早く帰ってきなさい」「勉強しなさい」と親がうるさいと嘆く友人たちに「心配してくれてるんだよ」と笑顔で言葉をかけながら、「じゃあ何も言ってこない私の両親は?」。自分の言葉が自分自身に跳ね返ってきました。
幼い頃からこのように育てられたので、私は自分でしたいことを決め一人で行動する人間になりました。高校受験では高校選びから一人で行い、受験しました。やっとその高校から合格通知が来るかもという頃になって、母から「そういえばあんた、高校どこを受けるつもりなん?」と聞かれたほどです。父は何も言ってきてくれさえしませんでした。
そしてそのまま育った私は、大学で行っていた研究が非常に楽しく、より先端科学を勉強したいと思ったので大学院へ進学することも一人で決めました。そしてこの春から進学することになりました。
これまですべて自分で決めてきた進学ですが、大学院まで学校に通わせてもらって申し訳ないという気持ちは常に付き纏まとっていました。自分で決めた学校だからといって、自分でそれにかかる費用を出せるわけではありません。学費はもちろんのこと一人暮らしにかかる家賃や生活費も、すべて両親から出してもらっています。アルバイトをしてはいるものの、学業の片手間では気持ち足しになる程度の収入しかありません。それにも関わらず、両親に「ここの大学院受かったから。入学金・学費がこれだけ要る」と伝えると、「へえ、そうなのおめでとう。どこの口座に入れればいいの?」と嫌な顔ひとつせずにお金を出してくれるのです。本当は大学院に行ってほしくはないんじゃないか、子供の決めたことだから仕方なくお金を出してくれているんじゃないか、進学なんてせずに就職してこれまでの学費を早く返せと思ってるんじゃないか?。これらの不安がぎゅうぎゅうに詰まった重たい荷物を、私はずっと抱えていたのです。どこにも置き場所がなく、誰に見られるわけにもいかず、しっかりと蓋ふたをして。なので、引っ越しが終わった夜に父から「どこか飲みに行くか」と言われた時には正直行きたくないな、と思いました。私が必死に閉じている蓋をこじ開け、責められるのではないかと怖かったのです。
お店の料理は非常に美おい味しく、話に花が咲きました。お酒も進み、父はいい気分のようでした。しかし私はあの話題にいつ触れられるのかと、お酒に酔うことも料理を味わうことも出来ませんでした。
話題もひと段落し、ふと私たちの間に静かな時間が流れました。私が何か話題を探していると、父が突然「ありがとう」と呟つぶやきました。料理を取り分けてあげたわけでも、飲み物を渡したわけでもありません。何のことだろうと首を傾かしげると、父は手のひらで自分の顔を押さえて続けました。
「母ちゃんも僕もな、朋子さんに勉強しろとかこうせえとかああせえって言って育ててこんかったやろ。やから嬉うれしいんや、大学院に行ってくれて。もっと勉強したいから院に行きたいと思ってくれて。朋子さんがしたいと思ったことを自分で決められるように育ってくれて」
ありがとう、と最後に付け加えた父の声は震えていました。 目の奥から涙が迫ってくる感覚に息を止めました。別に泣くなと言われたわけではありません。しかし泣くよりも今目の前で涙を堪こらえきれていない、初めて知る父の姿をもっと見ているべきだと思ったのです。そして私だけじゃなかったんだと力が抜けました。蓋をした重たい荷物を抱えていたのは私だけではなかったのだと。 両親の抱えていた荷物をこの時初めて知りました。初めての子育てで、自分の子供であろうともどこまで他人の人生に干渉していいものか。どうしたらしっかりとした人に育ってくれるのか、いろいろと迷い、二人で話し合って。その結果、私にすべての選択を任せるというそっけなくも感じる態度を取っていたのだと。その裏では、親としてもっと口を出した方がいいのではないか、本当にこれが良い選択なのかどうかと不安になりながら。
私は込み上げてきたものをなんとか抑え込んで、私の荷物の蓋も開きました。 それからの父はいつも以上に饒じょうぜつ舌で、「飲んで忘れてくれや」と恥ずかしそうにしていました。しかし、お酒のせいにするにはお互い酒に強過ぎて。
「あなたの娘やねんから、無理やろ」「それもそうやな」と笑い合って、そのまま父は新幹線に乗り込みました。「じゃあな」と、また明日も顔を合わせるような軽い挨拶を残して。
遠ざかっていく父の姿を見送りながら、私は身体の軽さを感じていました。もう私に抱えなければならないものはありません。
引っ越しの終わった部屋に帰り着いた時、私の本当の引っ越しが終わったような気持ちになりました。
次はいつ父と二人で飲めるのか分かりません。帰り際に「次の引っ越しも手伝ってね」とお願いしてみたら断られてしまったので。
ですが、それが父なりの照れ隠しなのだと、もう私は知っています。子供思いのとても優しいお父さん。また一緒に飲もうね。その時までに、たくさんたくさん面白い話を用意しておくから。詰め込み過ぎて重たい荷物になってしまうかもしれないね。
服部 勝美(48) 愛知県
長女が中学を卒業して四月から高校生になる。母として思い出に残る入学プレゼントをしたいと思い悩んでいる所だ。親になってからは、プレゼント一つでも真剣に考えるようになった。本当に子どもに必要か?そうでは無い物か?の判断に迷うこともしばしばある。子どもにとってプレゼントは最高のご褒美だからそのタイミングが大事だと思っている。適切な時と適切な品物のタイミング!それが難しい。
私は、子供の時に親からプレゼントという物をもらった記憶がほとんどない。もし、貰ったとしても記憶にないからたいしたものでは無かっただろう。しかし、今でも覚えているプレゼントが一つある。それは父親からもらった大学の入学プレゼントであった。
二十三歳の時、一年だけ英語を勉強して戻る約束で留学をしたが、約束を破って大学の受験までしてしまった。運よく合格はしたが親には約束を守れないと告白をしなければいけなかった。更に足りない入学金も用意しなければいけなかった。入学前に叔母さんに預けたお金が少しあったのでそれを返してもらうつもりだった。不足分は、借りる覚悟をしていた。ようやく一年ぶりに戻ったけれど約束を守れない娘の事で怒ったのか、父はずっと暗くて悲しい顔をしていた。母は、やせすぎた私を見て涙を流しながら四年間の学費の心配をした。父は、私が故郷にいる間ずっと暗い顔だったが約束を守れなかった私の立場からは、寂しいというそぶりは見せなかった。
父は三十年間金属製工の職人だった。年を取り、目が見えなくなり、細かい作業が出来なくなった上にお酒の飲み過ぎで手も振るえるようになった。つまり、クビになったわけだ。その後は母の洋服店の隅っこで小さいコーナーを作り、金属アクセサリーを作って生活をしていたがその稼ぎは父の飲み代位だったらしい。なので、父親として娘に学費を出す余裕は全く無かっただろう。だから私も一切父に学費のことは言えなかった。そういう立場の父だからこそ娘に厳しく言えなかったのだろう。
複雑な心境を神様がわかってくれたのか、叔母さんが預けたお金を一年間増やしてくれた。そのおかげでとりあえず入学金は解決出来た。一安心した私は、すぐにでも学校に戻りたくて急いで荷造りをしていた時だった。父が急に一緒に行きたい所があると言って出掛ける準備をし始めた。理由を聞いても答えないで先に出て行った。二人は地下鉄に乗り、一番にぎやかな繁華街で降り、高いビルが並んでいる中を数えきれないくらいの人混みにまみれて歩いた。父の後ろ姿はあんなにも派手な街には似合わなく、時代遅れの人に見えた。まるで色よりどりのドーナツ箱の中のおにぎりのようだった。
父が向かった所は、派手なブランド品の店が並んでいる商店街で庶民が簡単に見物をする所ではなかった。その中の1件の靴屋を父は戸惑いもなく入って行った。訳が分からず私は外で待っていたら、父が硝子越しに入って、入って、と招き猫のように手招きをしていた。恐る恐る私も店に入ると、父はレディースコーナーに私を連れて行った。突然のことに固まっている私に「入学式で履くような靴を選んでね。それから普段も履けるように楽な感じがいい!」と言った。この状況がすぐに飲み込めなかった私は、小さい声で「こんなに高級な店じゃなくてもいい。」と返事をした。父は「年末に勤めていた会社からこの店の商品券が届いたから安心して選んでね。」と、ささやいた。その話を聞きながら、父の靴に視線が行った。私が中学生だった時から履いていた馴染みのある茶色の靴で、色は剥げていてほとんど茶色ではない靴になっていた。「お父さんの靴を先に買って。私は市場で買うから。」と言ったら、もう一つ靴の商品券があるとバレバレのウソを言い始めた。ウソをいうと父は顔が赤くなるので私と目を合わせない為に商品を選んでいるふりをしていた。そういう父のふりが切なく見えてきて、目に熱いものが集まってきた。瞬きをすると、こぼれ落ちそうだったから二階を見るふりをした。
娘に学費も何も出せない親が、あげれるものがあるならすべてあげたいという心境だろうと、父の言う通りにしようと決めた。もしそれを断ると、父はずっと苦しむだろうと分かっていたから、嬉しい顔を演じた。その代り父に選んでくれと頼んだ。父は、地味で楽でおとなしい感じの黒い靴を選んでくれた。帰りの父は、重くもないのに靴の紙袋を家までずっと持ち続けた。故郷に戻って初めて父の笑顔を見た。その笑顔を見て私は安心して学校に戻れた。それから無事に入学手続きを終え、ピカピカの大学生になった。
父は、自分は何年も古い靴を履きながら、四年間の勉強のために旅立つ娘に新しい靴を履かせてあげたかったのだろうと勝手に思った。それが親の心なのだと、しみじみ感じたプレゼントであった。
「頑張ってね!」「無理しないでね!」「最善を尽くしてね!」などの言葉より何十倍も何百倍も力をくれた一足の靴だった。
しかし、そういうプレゼントを娘にしてあげたいと思うと、複雑になりすぎて迷ってしまうのだ。何かの意味を付けようとするのが演技っぽくてわざとらしい。心から自然に出てくるようなプレゼントをあげたい。それが本当に難しいけれど、こんな悩み事も幸せの一つであることに違いない。つまり、プレゼントは幸せの一つであることは確実に知っている。
入倉 文子(62) 山梨県
「ああ、もう生きていたくない」
目が覚めるといつもそう思った。秋から突然始まった鎮痛剤の効かない体の痛みは年明けから全身に広がり、生きるのが嫌になってしまったのだ。
その日も目が覚めるとすぐに痛みが襲ってきた。室内でも息が白く見える寒い朝だった。(また苦痛に満ちた一日が始まるのか。この病気のせいで長く仕事も休み、いろんな人達に迷惑をかけてしまった。もうこの世から消えてしまいたい。早く楽になりたい)
重苦しい黒い塊が胸にのしかかったような感じで、起き上がる気力もなく、とりとめのない思いを巡らせていた。その時、ふと亡き父の顔が浮かんできた。
父が戦後に裸一貫から始めたメリヤス工場は、時代の波に乗って成長し、昭和四十年代の初めには百人以上の従業員を抱えるまでになった。ところが、昭和四十六年のドルショックで、取引先が倒産。その影響で父の会社も不渡りを出し、連鎖倒産に追い込まれた。親戚の援助のお陰で家だけは取られずにすんだが、五十代半ばで、父はそれまでに築きあげたものの大半を無くしてしまった。高校生の私は、倒産騒ぎの数か月間は祖母の家から学校に通い、実際の修羅場を見たわけではない。でも、久しぶりに母に会ったとき、驚きで声が出なかった。まだ四十代の母は、髪がほとんど白くなってしまっていたのだ。私は、マリー・アントワネットが一夜にして白髪になったという話しはきっと本当なのだろうと思った。
会社を閉めた父は縁側で背中を丸め、一日中たばこを吸っていた。こんな状態がどれくらい続いただろうか、ある日を境に猛然と働き出した。知人が経営する会社で働くように勧めてくれるのを断り、一人で問屋街を回ってブラウスやセーターなどを仕入れ、露店で売り始めた。
ある日、私は学校の帰りに、バスの中から役所の前で店開きをしている父を見た。折り畳みの長机の上に色とりどりの衣類を並べ、役所から出てくる人たちに声をかけていた。色白の父が真っ黒に日焼けし、笑顔で頭を何度も下げている。バスは一瞬にして通り過ぎたが、ぺこぺこ頭を下げる父の姿に激しく胸が締め付けられた。それと同時に、お勤めの話を断って露店を始めた父を恨めしくも思われた。
仕事のかたわら、父は自動車教習所に通い、人の倍以上の時間をかけてどうにか免許証を手にした。そして、知人に譲ってもらった古ぼけた車にワンピースやスーツを積み込み、露天商時代に顔見知りになった客の家を訪問する仕事を始めた。父は客の好みをとらえるのが上手く、その人に似合う品物を持っていくのでよく売れた。洋裁の心得のある母はサイズ直しを手伝うようになったが、客の希望通りぴったりに直すので、評判がよく、次第に売り上げを伸ばしていった。
そんなある日の夜、役所勤めの母の弟が訪ねてきた。丹念に帳簿をつけている父をしばらく見ていた叔父は、感心したように言った。
「にいさんは偉いよな。人に頭を下げてものを売り歩くなんてこと、俺にはとてもできん」
私は胸がどきんとした。以前にバスの窓から見た光景がはっきりと目に浮かび、父はどう答えるのか、じっとその横顔を見守った。
父は、帳簿から目を離し、ゆっくりと顔をあげて真っ直ぐに叔父を見た。そして静かな声で言った。
「この仕事を辛いと思ったことは一遍もない。俺はいつも商売の神様に頭を下げているんだから」
負け惜しみではなく、父が本心から言っているのが私にはわかった。「商売の神様」に深々と頭を下げる仕草をし、にっこりと笑った。心から楽しそうな笑顔だった。小柄な父が大きく輝いて見えた。
布団に横たわっていると、古い記憶が光のようにあふれ、ぼろぼろ涙がこぼれた。
父の人生は苦労の連続だった。幼くして母親と生き別れ、戦争で足に大けがを負い、六十代で妻に先立たれた。でも、子供の頃に奉公に出され、商売のいろはをたたきこまれた父の中には不屈の商人魂が宿っていたのだろう。人の下で働くのを潔しとせず、自分の才覚で生き抜くことに誇りを持っていた。私にも、雑草みたいにたくましい父の血が流れている。そう思うと、どこからか力がわいてくるのを感じた。
それからひと月ほどして、私は名医に出会い、おかげで一年以上たった現在は普通の生活ができるようになった。
今も、あの朝の出来事を思い出すと、とても不思議な気持ちになる。滅多に夢にも出てこない父なのに、不意に記憶がくっきりと蘇り、弱っている私に力を与えてくれた。あの時以来、私は少し変わったような気がする。ちょっと図太く、楽観的になったのだ。これからも予想がつかないような試練が待ち受けているかも知れない。でも、それも生きていればこそ。本当につらいときには、きっとまた父が現れて助けてくれる。だからくよくよしないで、与えられた日々を朗らかに生きたいと思う。
家入 李佐(31) 鹿児島県
家族参観日。大勢のお父さん達がざわざわと並んだ。
「一番怖そうなのがうちのお父さんだよ。さあどれでしょう。」
私はケラケラ冗談混じりで友人に問いかけた。
「もしかして・・・あのピンクのシャツ?」
当たるはずがないと思っていた質問は一発で正解の回答が返ってきた。答えた友人も質問者である私もまさかの正解に驚いて、思わずおかしくなって笑った。いや、ただおかしかったのではない。私の笑いは父が参観日に姿を現した嬉しさが混じっていたのかもしれない。
現役時代、父はまさに仕事人間だった。仕事の舞台は魚市場。生活は昼夜逆転、体力勝負の現場だった。仕事から帰ると夕方5時にはまだ何にも並んでいないテーブルに座り、空の皿と箸を握って台所に立つ母に無言のプレッシャーをかけていた。小学生の私が夜の子供向けの番組にワクワクし始める頃、父は寝室のある二階へと上がる。そして、深夜2時には重い体をぐぐっと起こし足音も立てず黙って一階へ降り、寝起きで食欲のない胃袋に母の握ったおにぎりを押し込む。月明かりの中、父のエンジン音はスーッと消えていくのだった。
私は3人兄弟の真ん中だった。幼くともなんでも下の二人に譲る聞き分けのいい姉と三つ下の泣き虫な弟の間で私は一際わがままで我の強い女の子だった。その名残りは年を重ねても染みついていた。何かを行動に起こす時、親への相談はほとんど無かった。何でも自分の好きなように、例え相談したとしても親の薦めより自分の希望が最優先。それは相談ではなく専ら報告というべきものだった。
短大は栄養学を学ぶ学校へ通い、そこで私は栄養士の資格を取得。卒業後は当然栄養士としての道を進むであろうという両親の予想をさらりと裏切り、またもや相談もなく飲食店の接客業に就いた。朝から晩までハードな労働時間を力いっぱいこなす毎日。一年後には店の責任者になっていた。昼食時間は十五分。一日を目まぐるしく過ごし、帰宅時間は日を跨いでいて帰りはある口からも残されていないほどだった。それでも仕事が楽しかった。職場のみんなが頼ってくれる嬉しさと忙しさの中の充実感で満たされていた。
だが三年目、よく分からなくなった。周囲の人間から働き過ぎだよ、他の会社はそんな扱いしないよ、と言われるうちに、そうか自分は働き過ぎなんだ、会社にうまく使われているんだと思うようになり、いつしか会社が嫌いになっていた。
私はついに辞めてしまった。いつも通りの独断だった。
時が経ったの後に、この時の心境を親と話したことが一度だけあるが、母は我が子が身を削り働く様をこぶしを握る想いで見ていたと述べた横で父は何も言わなかった。結局のところ飲食店とはそういうハードな労働スタンスの職業であり、それを選んだのは私自身、自分の選んだ仕事に対して甘かった私の考えを父は見抜いていたのかもしれない。
社会人生活を好きなように過ごして、二十五歳で私は結婚することとなった。
思いの募る結婚式前夜、父は私に一枚の茶封筒を差し出した。決して綺麗とは言えない字で「父へ」と書かれた古い封筒。それは私が社会人になって初めてもらったお給料の中から一万円、父に渡した時の封筒だった。その字は社会にもまれる前の初々しさとやる気に満ちた渾身の二文字だった。
父は言った。
「これはお前に返すよ。社会人一年目のあの頃の気持ちを忘れるな。初心を忘れるな。」
中身の一万円は入ったままだった。父のあの当時とても嬉しかった事と、気持ちは充分に受け取ったからこれはお前が持っておけという想いを語ってくれた。
何十年と一つの職業をやり通した父。三年そこらで職を辞めてしまった私にとってそれはとても偉大なことであった。父がどうしてそれほどまでにまっすぐ仕事をしてこれたのか、茶封筒を返された夜初めて理解した気がした。
結婚はそう簡単には辞められない人生の大きなスタート。そこに常に初心を持つことの大切さを父は私の心にしっかりと刻んだのだった。
父は三年前に定年を迎え、今では時間に縛られることなく田畑で一日の大半を過ごしている。緑一色の田んぼに立つ、少し小さくなった父の背中を眺めながら私は平凡で幸せな子の結婚生活に今日も感謝を忘れない。
古川 峰生(76) 神奈川県
「あのね、ジャングルでね・・・」この言葉は私が父の蒲団に潜り込み、懐に抱かれながら聞いた寝物語の出だしで、父との唯一のものである。
父は海軍々人で私が五歳の冬に戦死した。その数年前から海洋勤務のが多く家にいることは殆んどなかったという。だから私は父を知らない。母の話によると、父は大変なお洒落で身嗜みに気を遣う、几帳面な勤勉家であったこと。そして、私が父の生き様を身近に育ったかのように、特性及び所作が酷似しているとの事である。私はそれが大層嬉しく、父からの伝承資格を誇りに思っている。
その父が誂えた二重廻し、合コート、三ツ揃いの衣服は、戦死訃報の数日後に届けられた。戦後母は女手一つで家族を養うため、懸命に働く傍ら、大方の衣料類を食べ物に換えた。父の遺したこだわりの衣服類は特に有効な品として、私たち家族の飢えを大いに充たしてくれた。然し、死後納品されたこれらの三品については手元に残した。毎年お盆が来ると軒下に吊るしては風を通し、念入りに手入れをして大切に保存して来た。
その母が死没後は、長男の私が父の貴重な形見として譲り受けた。お盆の虫干し等諸事母が実行したと同様、丁寧に取扱い保管し、今日に至る。これらの衣服は無事帰還し、袖を通すという強い意志が込められたもので、その父の気持ちに寄り添うと思うからである。
本年十月喜寿を迎える私は、病身で何をするにも大義億劫になりつつある。そのような中、未だ身体が動く内にとこの春定年退職後初めて、現役時に身に着け携帯した軍服、衣料カバン等多くの品々を、思い切って処分(発展途上国への支援品として提供)した。
手入れが行き届いていた品物はいずれも新品同様であったが、今後着用見込みがない物であり、家族の為にも手仕舞い、整理すべきと思ったからである。その作業をしながら重要なことに気付かされた。それは各々の品には手に入れた折々の思い出があり、その品を手放すことは、そうした思い出を断ち切ることなのだと。それ故私は自分の衣服は処分出来たが、父の形見の三品は躊躇することなく残した。父への貴重な思いでの<縁(よすが)>をなくしたくなかったからである。
私もやがて父の処へ往く。そのときは幼くしての離別故、再会ではなく初めての出会いに等しいものとなろう。その際誂えの三品を持参していれば、我が息子とためらわず認知してくれるであろう。
私は是非、父に為してもらいたいことが二つある。一つは、格別の思いを込めて注文、仮縫いをなどしたであろう三品の衣服に誂えに主として、七十年以上経過したが存分に心行く迄袖を通してもらうこと。二つは、海軍の父が何故ジャングルなのか、そしてその話の続き、結末をしっかり聞きたい。そうすることにより、私は父の懐で聴き耳をそば立てたあの頃の幼児に戻り、親子の温もり、絆を実感出来ると思うからである。このように父への思いは、加齢と共に薄れるどころか、より一層深まっており、それが何よりの供養と思っているのである。
竹内 祐二(52) 愛知県
「地震・雷・火事・おやじ」という言葉がある。世の中の怖いものを集めたものだ。今も、地震、雷、火事は怖いが、おやじに至っては、かなり怖さ度は低下していると思う。かくいう私も、二人の娘の父だが、二人からは、歩く財布とか、休日のトドとか呼ばれてなめられきっている。
そんな私の父は筋金入の昭和の頑固親父だ。どうしてそんなことしたんだ!と言われ、答える前に鉄拳が頭に落ちている。なんでこんなことした!と言われ、理由を答えると、いいわけするな!とまた平手。
学生の時、年上の女性とつきあっていて、その女性が卒業し他県に帰ってしまったのだが、私は夏休み、おいかけて彼女の家に一週間泊まった。帰ってきて、父がなんと言うか、とても怖かった。
「どういうつもりだ!」
その問いに、私は迷いなく
「結婚するつもりだ」
と答えた。すると父は、今まで見たことのない笑顔で
「それならいい」
と、行ってしまった。もし、私が、うーんとかまだわからないなどと言ったら鉄拳だったのだろう。しかし私の覚悟を父も分かってくれたようだった。おかげさまでその時の彼女は今も大切な奥さんである。
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
狩野 智子(34) 群馬県
「アイスでも食べるか?」
父はニヤリと笑って、駄菓子屋に車を停めた。そうして私に好きなアイスを選ばせ、自分は決まってモナカのアイスを買う。私の小学生当時、これが父と私の密かな楽しみだった。
小学校の入学前健診で「先天性乱視」と診断された私は、六才で眼鏡をかけ始めた。今でこそ眼鏡の小学生は珍しくもないけれど、当時は少数派。学校ではからかわれ、あだ名を付けられ、牛乳瓶底のような分厚いレンズは私の顔にも心にも重くのしかかった。
私の両親はこの子の目を何とかしようと必死だったと思う。車で片道二時間の、『〇〇研究所名』と名の付くような眼科のパイオニアに、月に二回程父に連れられ私は通っていた。診察は平日なので私は学校を早退し、父は職場に半体を取り通った。この眼科の帰りに、父と私はこっそり駄菓子屋へ寄ってアイスを買うのが習慣だった。当時家では、倹約家の母が大容量のバニラアイスしか買ってくれなかった為、父に買ってもらうアイスがとても贅沢で格別なものに感じられた。そして、父とふたりだけの秘密を共有しているようでワクワクしたことを、よく覚えている。
肝心の私の目の方は、様々な検査をし、視力回復のトレーニングのようなこともしたけれど特に効果は出なかった。「また視力が下がった」などと医師に言われれば、父とふたり責められているような気持ちになった。たぶん父は、そういうどんよりした気持ちを少しでも軽くする為に、アイスを買ってくれたのだ。当時の父は働き盛り、会社を休むことも往復の運転も負担だっただろうけれど、いつも父には穏やかな優しさがあった。
視力回復は見込めないと両親が判断したのか、いつしか眼科通いはなくなり、私は思春期と同時に反抗期を迎えた。父に対しても八つ当たりし、ひどい言葉をぶつけた。中三の受験期、一度だけ父に激しく叩かれたことがある。もうそれは、父に暴言を吐いた私が百パーセント悪く、父には何の非もなかった。叩かれている体の痛みよりも、父の悲しみがダイレクトに伝わってきて、心が痛かった。
あの時父に叩かれて、私は自分を省みるこができ、気づいたこともたくさんあった。だから父には感謝しているのだけれど、私に手を上げたことを二十年経った今でも後悔していて、思い出すのも辛いのだと、最近になって母から聞いた。驚いたと同時に、私は本当に父に対して申し訳ない気持ちになった。父は友人や親戚に「よっちゃん(父)は本当に穏やかで優しいなあ。」と言われる度、私を叩いたことを思い出して涙ぐんでしまうのだという。「そんなの私が悪かったから気にしないでって、父さんに言っておいてよ。」とわざと軽い口調で言った私に、母は苦笑いしながら、でも真面目な顔で答えた。
「親っていうのは、そういうもんじゃないのよ。」
親子の関係は近いようで遠く、年々切なさが増してゆく。子が親の気持ちを理解できるようになるには、何て長い時間がかかるのだろう。実家の冷凍庫には、もう大容量タイプのアイスはなく、父が変わらず好きなモナカのアイスが並んでいる。それをかじりながら私が昔の話を切り出したら、やっぱり父は泣いてしまうのだろうか。
昔共有した、ささやかで楽しい秘密と、各々が胸にしまっている秘密。娘に手を上げたことを悔やみ続けている父と、父にそんな思いをさせていることを悔やむ私。それでも、甘く軽やかに溶けていったアイスのようにいつか父の心を溶かしたいと思っている。
中山 沙香(小3) 東京都
「あー。いたー!」
まいごになった時やかくれんぼをする時にはすぐわかる。わたしのお父さんは、柱に頭がぶつかるほど背が高い。しかもつるっぱげである。
「ジージージー。」
「アハハハ。」
二かいから聞こえてくる。あわてて時計を見た。
「五時三十分」いつもより早い時間だ。カーテンのすきまが少しだけ明るい。かい段をドタドタおりていった。おふろばのドアを開ける。
「おはよう。」
「おはよう。」
バリカンを手に持ったお母さんといすにすわっているお父さん。お父さんの頭はけいこうとうの光があたってまぶしい。てっぺんがピカンとひかっている。つるっぱげのかんせいだ。ドアをバッシンと閉める。ソファにあわてていった。ふらふらとたおれこむようによこになる。毎朝この調子である。
「トゥルルル。トゥルルル。トゥルルル。おふろでよんでいます。」
ベルがなる。あわててかけてようふくをほりなげておふろへつっこむ。
「後ろむいて。」
「ゴシゴシゴシ。」
「ジャジャジャ。」
体についているホワホワのせっけんをながす。おとうさんのひざと手の上にねっころがる。かみの毛があわいっぱいになる。シャワーでながす。おふろにぽちゃんととびこむ。
「一、二、三、四、、、十。」
とはやく数える。ドタンとおふろのドアを閉める。
「プカプカ。」
ういている。
「ザッブン。」
と大きななみがあわを立ててやってくる。お父さんのところだけ大きな波がきた。流された。ウキワがひっくりかえり、頭をどーんとぶつけた。
「頭がふらふらする。」
と言って、お父さんは、りくにあがってごろんとした。
仕事がおわってまっすぐに帰ってくるお父さん。いつもわたしをおふろいれてくれる。学校であったことや友だちのこといろいろとおしゃべりする。でもこんなふうにしょっちゅうドジをやっている。
父の日のプレゼントにおり紙でメダルを作りいつもありがとうとメッセージを書いた。次の日、父の日になにをあげるか友だちに聞いた。
「チーズケーキ」
何とお父さんの好きなものだ。家に帰ってお母さんに相だんした。
「いいねぇ。いいねぇ。」
作ることにした。パソコンでしらべ、上がバリバリ下がホワホワなチーズケーキを作った。
父の日の夕方
「父の日おめでとう。」
とプレゼントをわたした。りょうてをあげてよろこぶお父さんのむねに、黄色のメダルがひかっていた。
山本 由美 大阪府
携帯がなった。「オセロ知ってるか」と父。知るも知らないも、夫と連日勝負する日が2年も続いた。先日そのオセロゲームを断捨離したばかり。「どこで売ってるかな?。買いたいんやけど」と父が問う。
会社経営から退き、足腰が弱ってゴルフもできなくなり、専らテレビでひがなー日過ごす父に、母と一緒にデイサービスに行くことを勧めたのは私。通うようになって半年になっていた。そこでオセロを知り、スタッフや仲間と遊ぶ内、父はすっかりはまったらしい。
数日後、私はオセロゲームを買って持参した。早速父と初勝負。勿論父のあっけない負け。全然わかってない。でもあえて沢山のアドバイスはしなかった。回数を重ねる内に自分で学習し、腕を上げていくに違いない。それより私は胸が熱くなった。パーキンソン病で手に震えがある父がオセロを必死で返す。ゆっくりで時間がかかる。でもいい。できることがうれしい。
それからというもの、実家に行く度父との勝負が待っていた。父とオセロする日が来るなんて人生未来図にはなかったことだが、何とも穏やかで優しい光景を享受できる日々が始まった。やがて父はオセロの指南書を購入。最近本もあんまり読まなくなっていたのに、ここまで夢中になるとは。いつ行っても熱心に読んでいると思っていたら、父が私を負かす日も増えてきた。デイサービスでも勝つ回数が増えてきたと言う。
父は旅行バッグにもオセロを入れて、旅先でもオセロ。父とオセロする場面が日常風景となって私は小さな感動を覚えている。仕事ばかりの父とは幼い頃からコミュニケーションも決して多くはなかった。それが今、父とこんなに素敵な時間が持てる。八路を行く父が手を考えている間、私はそっと父を眺めて、大切な時間を吸収している。
父はだんだんうまくなった。父が引き金となって今や通っているデイサービスはオセロブーム。スタッフが親切にもオセロゲームを父の携帯にダウンロードしてくれた。携帯でこんなこともできるのか、と父はただただ感心するやら感激するやら。
若い頃から時代の先端を生き、まだ珍しかった8ミリカメラを趣味にしていた時期もあったが、IT革命には乗り遅れ、ダウンロードと言われても何のことやらわからない。
とにかくその日から、父はインターネットの世界に足を踏み入れ、コンピューターと対戦する初体験を嬉々として受け入れた。暇さえあれば小さな画面を見つめてコンピュ―ターと勝負。ピッ、ピッ、ピピラピピラといつもの電子音がして、父が携帯片手にオセロゲームに興じている。「どう、勝ってる?」と問いかけると、画面から目を離すことなく「楽勝、楽勝」と笑っている。「もっと上級をやりたいな?」と。
先日母が教えてくれた。携帯ゲームが急にできなくなって、父はあわてて一人不自由な足で携帯ショップに出向いたというのだ。原因は充電切れだったという笑い話なのだが、父にとっては大切な携帯ゲーム。1日とてなしには過ごせない。そして私はもう父に勝てなくなっている。悔しいが、うれしくもある。
父がオセロを始めてもうすぐ5年。ついに父はデイサービスで負け知らずのチャンピオンになった。
うれしい発見がある。オセロを返す父の手が早くなったのだ。震えも少なくなった。リハビリにもなっていたのだ。今やオセロは父の一番の趣味となった。手垢で真っ黒になるまでオセロ指南書を読み、若者みたいにケータイでオセロゲームしている。何ともうれしい。
86 歳の父の手は、今日もピッピと携帯キーを押している。勿論アナログオセロにも余念がない。
大田 真穂(10) 三重県
わたしのお父さんは、毎晩仕事がおそくて時々しか話す機会がなく、もっといっぱいお父さんと一緒に、学校であったことを話したいのに話すことができない毎日でした。そんなことがずっと続いていて、お父さんが「交かん日記やらんか?」と聞いてきました。私は、めんどくさがりやし、長文書かないといけないと思っていたので気が乗らなくて、「えぇー。」とやる気のない声を出しました。そりゃ、お父さんとしゃべりたいけど交かん日記だと直接いうのと文章では、あんまり伝わらんのじゃないのかなぁと思い、でもお父さんとしゃべりたいしなぁっていう中途はんぱな気持ちがあったからです。でも、けっきょくお父さんは前向きな人なので「いやっやる!」と言って交換日記をすることになりました。替わりばんこで私が最初に書くことになりました。内容は、「今日、学校でみんなとあそんだよ。」で終わりみたいな短い文でてきとうに書いていたのに、お父さんは一生けん命返事を書いてくれました。仕事でおもしろかったこととか、私たちの学校であったことの質問とか、絵もいっぱい書いてくれてありました。すべて、私のために。私がすこしでも日記を書くのが楽しくなるように。そういうことが初めてわかって、だからあの時お父さんは日記を書くのをあきらめないで私に言ってくれたんだなと思いました。そういうおとうさんのさりげない優しさが大好きです。そして、私だけやる気がなくて日記を書いていたらいかんなぁと思って心から書くことにしました。1年生から今までずっと日記を書き続けています。前に書いていた日記を見返してみると字がへたくそやなぁと思ったりこんなことあったんやと思って見ていました。きっと大人になった時この日記が小学校の時の思い出になるんかなぁと思いました。
交換日記を始めた時に、お父さんと私で三つの約束をしました。それは、うそをつかない、弱いものをいじめてはいけない、そして自分に負けないということです。お父さんに、「この約束は大人になっても必要なことだからずっとお父さんとの約束としておぼえておくようにな。」と言われました。かんたんそうでむずかしくて今だに、守れなかったり、約束の意味が分からなかったりすることもあります。でも、この三つの約束をきちんと守れて約束の本当の意味を理解してこれからもお父さんと交換日記を続けていきたいです。
大西 賢(41) 東京都
父は酒とパチンコを好む剛胆な遊び人だが、弱点が一つある。私である。息子の私のこととなると、とたんに心配性になる。
私が高校三年のとき、自転車で東京から鹿児島まで行く計画を立てたことがある。
「俺も男だから分かるぞ。旅は男のロマンだ」
父は最初はそんなことを言って応援してくれていたが、いざ自転車も荷物も揃え、旅支度が着々と進んでいくと急に不安そうな顔になり、
「今の日本はどこへ行っても車だらけで危ない。一人で自転車旅行なんて、父さんは許さんぞ!」
などと言い出し、家族のなかで一番の強硬な反対派になった。母も兄弟も、
「今しかできない冒険だから」
などと言って認めてくれたのだが、出発前日まで父は反対し続けた。
「自転車旅行をあきらめるなら、銀座で高級な靴を買ってやる」などと最後には妥協案まで持ち出す始末だった。麻雀で十万円負けても平気な顔をしている父だが、私のこととなるとてんで弱い。
結局、私は父の反対を押し切って自転車旅行に出てしまうのだが、それから帰宅するまでの一ヶ月半、父は心配で夜も眠れなかったらしい。深夜に救急車のサイレンが聞こえると、私が交通事故に遭ったのではないかと思い、飛び起きたという。東京に帰ってそんな話を聞いたとき、正直、私は感動も感謝もしなかった。父を心配させているということが、私の「半人前」を証明しているような気がしたからである。
「お前のことが心配で、父さんは眠れなかったよ」
などと言われると、まるで自分が小さい男の子になってしまったようで、情けなさすら感じた。十八歳にもなって父親を心配させているということは、私の自尊心を傷付けた。父親から心配されないような成熟した男になりたいと、いつも思っていた。
ところが、である。私が二十歳になっても三十歳になっても、父は私のことを心配し続けた。年をとれば父はいずれ息子の心配などしなくなると思っていたのだが、その予想ははずれ、私が四十一歳になった今も、昔と変わらない心配を続けている。
先日、実家に行く用事があったのだが、途中で寄り道をしてしまい、予定の時間より十五分ほど遅くなってしまった。十五分ぐらい何でもなかろうと思って連絡もしなかったのだが、夕暮れの歩道を実家に向かって歩いていると、前方から父に似た老人がやってくる。
父だった。私を見つけると、なくした財布を見つけたような大げさなため息をついて、こう言った。
「予定の時間が過ぎてもお前が来ないから、心配で探しに来たんだ。前からお前に似た男の子が来たから、ホッとしたよ」
遅いといってもたかが十五分である。何を大げさなと思ったが、それより驚いたのは「男の子」という言葉だ。四十を過ぎても、父にとっては私は「男の子」なのだ。
たぶん、父はこれからもずっと私のことを心配し続けるだろう。そしてこれからもずっと、私のことを「男の子」だと思い続けていくのだろう。それは子供扱いされているようでやや屈辱的でもあるが、それ以上に嬉しいことだと思う。中年の息子が予定より十五分遅くなっただけで家にいられず、探しに来る父親。そんな父親を持ったことを、私は今、とても幸福に感じている。
およそ現実味のないことだけれど、父がもっと高齢になって寝たきりになっても、救急車のサイレンが聞こえたら飛び起きてくれるのではないかという期待がある。ベッドからまったく動けなくなっても、来るのが遅かったら、
「息子が事故にでも遭ったのではないか」
などと言って探しに来てくれるのではないか。私にはそんな期待がある。どんなときも父は私のことを心配してくれた。その前例が、私の期待をここまで大きくしている。
四十歳を過ぎても「男の子」と呼ばれるのは、男子として不名誉なことである。だが、それ以上に、私のことをそこまで心配してくれる父に感謝している。
身を案じてくれる人がいるということは、誰にとっても幸福なことだ。
父さん、今まで心配し続けてくれてありがとう。
これからも、ずっと俺のことを心配してくれよな。
増田 陽太(5年生) 広島県
「おっ。めずらしっ。」
ふだんは、全く雑誌を買わず、本ばかり読んでいる父が、ビジネス雑誌を買ってきた。
「へぇ~」
手に取ってながめてみると、その雑誌には、読者アンケートがあって、抽選で当たると、プレゼント商品がもらえるらしい。中身をしっかり読んだ後に、父もこの読者アンケートをすることにした。
すぐに父はペンを取って、十一問あるアンケート用紙になにやら書きはじめた。ペンを持つ手に力がこもっている。とても熱心にほかのページを見ながら丁寧に書き込んでいる。
「よっぽどほしくてたまらん商品があるなぁ」
「当たってくれ」
僕は、父の狙っている商品がきっと当たることを願いながらアンケート用紙ながめていた。そして、数十分後。
「よし!!」
父が、ようやく十一問アンケートに答え終わったようだ。父がなんのプレゼント商品を選ぶのか見るために、家族全員父のもとに集まった。
「何選ぶん?」
「これから決める。」
「え・・・これから!?」
プレゼント商品を選ぶのは、どうやらこれからのようだ。
「いい商品あるんかなぁ。」
僕も母も、自分の商品を選ぶかのようにキラキラと目を輝かせて、商品のたくさんのっているページを探した。
「おっ。あったあった」
いろいろなプレゼント商品が写真などで紹介してある。
「どれどれ。ほしい物はあるかなぁ。」
かたっぱしから順に一つずつ目を通していく。商品の特徴や説明も全て読んでいった。
「ん?何やこれ。」
三人とも、プレゼント商品に目をうたがった。見てみれば、消臭スプレーや、頭を洗うブラシなどばかり。掃除機などの電化製品は、一つもなかった。
「この消臭スプレー、そこら辺のスーパーで売ってるの見たことがある。どこでもかんたんに手に入れられるやん。」
コンフォートホテルの宿泊券はペアだから、家族だれかひとり泊まることができないのでダメ。アクションスリラーのDVDは父が見ないのでダメ。ビールなら好きだけど、日本酒は父は飲まないのでダメ。
「お父さんの好きなスーパードライの詰め合わせみたいなんあったらよかったのになぁ。」「じゃぁお父さんのほしいものないやんか。」
家族全員苦笑い。しばらくちんもくが流れた。
そして父が沈黙を破った。
「こんなしょうもないもんで、個人情報売るんやったらやめるわ」
「先にプレゼント商品の内容を見てたらアンケートしなくてよかったのに。おっちょこちょいやなぁお父さん。ふぅ~」
みんなため息をついた。そして、結局読者アンケートは辞めた。父は無言でアンケート用紙をくしゃくしゃにまるめて、ボールを投げるようにしてゴミ箱に入れた。
「せっかくやったのになぁ。」
僕は、笑いをこらえて言った。空気の読めない母は、大爆笑している。
「お父さんかわいそぅ」
僕は、父に自分でプレゼントしたいと思った。
「そうだ!!」
父は阪神タイガースの大ファンで、野球を見るのがとても好き。だから選手が最も近くで見られる年間予約席を自分でコツコツ貯めたお金で買ってあげたい。それも僕と父の二席。
「お父さん。楽しみに待っててね」
そのチケットはとても高い。だからコツコツ貯めていつか父の日にプレゼントしたい。僕はもらったおこずかいをすぐ、父の喜んでいる顔を想像しながら、貯金箱にそっと入れた。
石原 節子(69) 岐阜県
昭和30年頃、日本は一番大変な時代でした。父は8人を養っていく為に町工場の荷作り班で、早出、残業、盆と正月だけ休みという厳しい生き方をしていました。残業の弁当を届けに行くのは女の子の私の仕事でした。小柄な父が大きな木箱を背にトラックの荷台一生懸命運ぶ背を私はずっとみてきて、父ちゃんかっこいい!と思ってきました。
私が中学二年生の梅雨時の出来事でした。朝学校に行く時、母が台所から「節子、中学は遠いで傘、届けてやれんで持っていけ」と。私は母の言葉などまったく無視して、さっさと家を出てきた。昼休み、私の机のまわりに仲良しの二人が楽しそうに話しています。窓の外を見ると激しく雨が降り始めました。とっても気になりました。どうして母ちゃんの言う事を聞かなかったのか・・・・
教室のドアの近くに、男子が数人ふざけて遊んでいた。その中に最近好意を持ちかけていたA男君がいました。その時です。ドアが開き、そこに汚れた作業着を着た父が男物の黒い傘を手に私を探している姿を見たのでした。私は夢中でした。走っていって父の手から傘を“ざっと”取り怖い顔をして廊下を走っていったのでした。教室に戻って窓の外を見ると雨の中を古い自転車にカッパを着て急いで工場の方に走る悲しい父の背を見たのです。涙があふれてきました。どうしてありがとう!と感謝の言葉を伝えてやれなかったのか・・・
父は30分の貴重な弁当の時間に、私のために傘を届けてくれたのでした。この光景は、私の脳裏の中にずっとありました。都会で苦学している時も、いつも勇気づけられました。
22歳の時、私は故郷でよきパートナーを見つけて、4人の子のために厳しい苦労をしてきてくれた父にかわいい孫といっぱい触れ合わせてやりたいと主人との結婚を決意しました。父は一人娘の花嫁姿をとても楽しみにして指折り数えて待っていましたが、神様はそんな父にひどい仕打ちをされました。式の2か月前“急死”という別れを・・・
わたしは天国の父に幸せな私の姿をいっぱい見せてやりたいと、大好きな仕事、幸せな2世帯暮らし46年間、送ってきました。
ありがとう 父ちゃん
節子はこの町で一番幸せな69才だと思っています!
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
鈴木 美紀(中3) 宮城県
「今日は一日ゆっくり寝てなさい」
そう言って父さんが出て行った。
ガーン、そうなの嫌だよ。
父さんの看病受けるなんて。
何だって母さんいないのさ。
「少し静かに、
熱があって寝てるっつーのに」
怒られているのは誰?
妹かな?
ひょっとして兄ちゃん?
意外なところで姉ちゃんかな?
あー、そんなこと
どうでもいいや。
天井を見ているだけの私には、
関係のないことだから。
家の中がシーンとなった。
どうやら誰もいないらしい。
私は父さん呼んだけど、
庭仕事している父さんの耳には
このかすれ声は届かない。
父さんの影はこの窓から、
ちらりふわりと映るのに。
体の中でバイキンが、
燃えろよ燃えろ
キャンプファイヤーしているよう。
頭の中ではウィルスが、
パカーンガツーン
お構いなしに薪を割る。
父さん早く火を消して。
今すぐナタを取り上げて。
喉には煙がこもってる。
この騒ぎ鎮めて楽させて。
どこもかしこも
ジンジンガンガン。
こんなに熱くて苦しいのに、
「みのり?こんなにいい天気なのに風邪で寝てるんですよ」
脳天気な声が聞こえてくる。
(ジュワー)
私の心に雨が降る。
涙となって川となる。
予想外のどしゃぶりで、
川は氾濫、大洪水。
私は流れに身を任せ、
溺れて意識が遠のいた。
どのくらいの時間が経ったのか。
「みのり、みのり」
聞き覚えのある温かい声。
ああ、声の主は父さんか。
私は体にスイッチ入り、
ゆっくりゆっくり目を開ける。
真っ先に飛び込む父さんの顔。
輪郭ふやけて見えたけど
柔和な顔が飛び込んだ。
「おかゆ、作ったから食べなさい」
「食べれるか?」
「起きれるか?」
ありがとう、父さん。
嬉しいよ。
「ん?何で泣いてるんだ?具合悪いのか?」
「おかゆ、そんなにまずいか?やっぱ母さんみたいにおいしく作れないな」
ううん、父さん
おいしいよ、最高だよ。
土屋 春美(55) 東京都
若い頃の父の写真があります。
白いヘルメットをかぶって、手にはスコップを持っています。顔はさわやかな満面の笑顔です。
今ではとても好きな写真ですが、子供時代は複雑な気持ちでその写真を見ていました。父は北海道の開拓農家の生まれで、十人兄弟の八番目でした。
その当時、そういう家庭の子供の多くは学校を卒業すると、家の手伝いか、または生活費を稼ぐためにすぐに働きました。父も小学校を出ると、すぐに家の仕事を手伝いました。
母と結婚してからは、独立して同じ町の親とは別の集落で農地を手に入れ、畑作をはじめました。
しかし、子供がつぎつぎと生まれ、小さな耕作地からの収入では子供達に満足に教育を受けさせることもできないからと夫婦で話し合って、離農して町に出ることになりました。父も母も、まだ三十歳前後でした。
町中で、家族が暮らしていける賃金をもらうためには、力仕事をするしかありませんでした。父は、山で木を切り出す仕事や、道路工事の仕事などをし、母は、農家の手伝いなどで毎日朝早くから日が暮れるまで働きました。
父は雪が降る季節になると、雪のない関東圏に出稼ぎにも出ました。
私が町中の小学校に上がると、同級生の多くは商店の子供や、サラリーマンの子供が多く、私の父のような労働者はそんなにいないようでした。話を聞くと、どのお父さんも、みんな私の父より品がよく知的に思えました。
今にして思えば、どんな仕事をしているお父さんだって、そんなに違いはないと思えるのですが、その頃の私は、いつも泥だらけになっいている父が恥ずかしくて仕方ありませんでした。
父は何も悪くないのに、町中で友達といるときに仕事帰りの父に声をかけられたりすると、ふてくされたような顔をしてしまったこともありました。
父は、そんな私の態度に気づいていたのかどうかはわかりません。
ヘルメットの父の写真は、その頃の一枚です。
父は子供達が皆、学校を終え就職し、年金をもらうようになるまで、ずっと力仕事で働き続けていました。
そして年金生活の今でも、時々町から依頼で蜂退治の仕事などをしています。暇なときは、自転車にまたがり何キロも走って知り合いに会いに行ったりする元気な人です。
無邪気な顔で近所の人や家族に笑いかける父の顔は、写真の頃とほとんど変わりません。とうさん、私は思うのです。
あなたの人生が、他の誰より誇らしくさえある、汚れない輝きに満ちたものであることに、あの写真を見たときから本当は私にもわかっていたんですよ。ちゃんとわかっていたんです。
佐々木 幹雄(56) 東京都
うちの親父ですか?本当にしょうがないとしか言いようがない人間でしたね。医者が大嫌いで、若い頃は健脚を誇ってたのが、歩くこともままならないほどあちこち調子悪くなっても、絶対に病院には行きませんでしたね。結局、肝硬変でポックリ。朝気がついたら、畳の上で大往生。
えっ?健脚というのは、陸上の選手だったんですよ、若い頃。大したことはないですよ。ちょっと箱根の駅伝に出たくらいで・・・五区ですよ、ほら柏原が記録作った登りの。区間新を作った訳じゃないですし。まぁ、二年続けて出たらしいですけど。そんなに驚くほどじゃないですよ。年とってからは酒ばかり飲んでいる酔っぱらいでしたよ。そういえば、シニアでも走ってましたね。還暦過ぎてフルマラソンに出たりして。「走ったあとのビールはうまい」って言ってましたから、うまい酒を呑むために走ってたようなもんじゃないの。
いや、酒ばかり飲んでたけど、身を持ち崩すって程では・・・オイラも兄貴もちゃんと大学行かせてもらったから。あまり会話はなかったけど、年に一回手紙をくれたね。それが達筆過ぎて全く読めないんだよ、書道やってたからね。うーん、確か四段だったかな。そんなに凄い?たいしたことないって。
あはは、確かに劣性遺伝。悪かったね、こちとら、スポーツも字も不自由と言われ続けて五十余年、なんてね。
やっぱり親父は大したもんだったね。「さっき、しょうがない」って言っただろって?そりゃ、謙遜ってもんだろ。何だよ、うちの親父のこと悪く言うの?俺のことはいいけど、親父に文句言う奴は許さないぞ。
何?酒?酒ならお前も飲むだろ。必死に走ったり、一生懸命仕事した後、キーンと冷えたビールほどうまいもんはないだろ。
あんたオイラの話をきいてなかったのかい?箱根の駅伝、登りの五区だぞ。あんただったら歩いても登れないだろ。オイラもそうだけど。それを、真冬にランニングに短パン、靴だって柏原みたいに科学の粋を尽くしたものなんかじゃないぞ。粗末な靴で走って二人も抜いたんだぞ。
だいたいあんたの字はなんだよ。ミミズがはいつくばったような字を書いて。ああ、オイラも下手だよ、左手で書いたんですかって、よく嫌みを言われたよ。でもさ、親父は書道家なんだから。さながら、走る書道家だ。
親父は、日本一、いや世界一の親父なんだよ。女房と兄貴とオイラのために、黙って必死に働いて・・・うう・・・泣いてんじゃねえ、目から昨日飲んだビールが出て来ただけだ。
為房 梅子(65) 岡山県
父の中の「不肖の娘」が、「不肖の娘だ」に代わったのはいつの頃からだろうか。思い出せもしない。それなのにふっと「父と同じ嗜好を持っている」と気づくこともある。歳を重ねるとは色々含んでのことかと「はっ」としたりもする。
三歳違いの姉と弟に挟まれた「次女」として産まれたのが私で、父は平たく言えば御養子さん。父の使命は何が何でも「男子」を「跡取りを」作ること。
弟は私と四歳違いて産まれた。父はその四年もの間どんな思いでいたのだろうか。
あの日のことは覚えている。
あの日とは弟が産まれた日のことである。
四歳の少し前で、還暦を過ぎた今でも私の記憶にははっきりと止まっている。
お産には男は邪魔だとでも言われたのか、父は朝早くから自転車の前に子供用の椅子を設え、私を乗せてつばめのように風を切っていた。
望んでいた男子がやっと生まれたのだ。
「子どもが産まれてなあ」
見上げた父の鼻が思いっきり膨らんでいた。
「要さん、そりゃあ、そりゃぁ」
おじさんは手を取らんばかりに破顔した。
「おとごでなぁ」
また、父の鼻が膨らむ。
「そりゃあ二重のおめでたじゃぁが」
おじさんの笑顔の顔がいっそう崩れる。
「へへへ」
父の親友とも言える電機屋さんの店先での会話であった。
三つ子の魂とでもいうのか、鼓動を震わすような高揚した父の声が頭上を飛んだ。私の知る限り、父が感情の高ぶりを見せたのは後にも先にもこの日だけのような気がする。いつもは静かで無口な父であるからだ。だが、それ以後我が子をその手に抱いたことがあったのだろうか。父にはなかったのかも知れない。種馬のような扱いの父からは文句も愚痴も私は聞いた事がなかった。
いつも弟の後には影のように祖父がいた。目の中に入れても痛くない諺通りに、祖父は片時も跡継ぎの男孫からは目を離すことはなかった。いつの間にか祖父は百姓仕事もそっちのけで、ひたすら子守り役に専念した。そんな祖父を私は冷ややかに見ていた。そんなだから、長女の予備軍のような私は尚更母からは嫌われた。
そんな立場の私の寂しさと御養子さんの父の気持ちが呼び合ったとでも言うのか、どこに行くにも父は私を連れ歩いた。それはまるで祖父を真似ているようだった。
父は映画が好きで観るのは洋画と決まっていた。字幕も読めない幼さでも父と一緒は楽しかった。お菓子の一つも買ってもらえないのに嫌だと思った記憶もない。絵本もない職後、父の借りて来る本の中の平仮名だけを拾い読みをしても悦楽だった。長じて洋画が好きで読書に幸せを見いだす娘に育ち、父の口笛のジャズのリズムに身を委ねる至福の時をも知った。つまり私の中にだけ父が存在しているような気がしていた。それなのに思春期のなせる技なのか、将又母の言うような捻くれ者なのか、いつの間にかあれほど慕っていた父の心とはすれ違ってしまった。
父の望みとは正反対のような男と結婚し、気づけば父に不肖の娘だと言わせるように振る舞っていた。父の心情など少しも思いやる気持ちをあの時分は持ち合わせていなかった。若さとは残酷でもある。
二人の息子は父の膝の暖かさも知らなければ連れ歩いてもらうこともなかった。ただ、実家では疎んじられている存在の母親を幼かったとは言え二人の息子たちは感じていたのかも知れない。
父や祖母の気持ちとは裏腹に母からは邪険にされ、疎んじられていたからだ。
最近になって父の中にあった「不肖の娘だ」が重くのしかかる。
漸く父の懐の深さ、その度量の大きさに気づいていてももう遅いのだ。いくら弁解したくても父には現世ではもうできないからだ。「不肖の娘だ」とのレッテルを貼られてこれからの残りを生きていくしかないのだ。
親族やましてや他人に何と思われようが私には痛くも辛くもない。だが、できるものならば父にだけは弁解したかった。
「父さん、ごめんね。不肖の娘の詫び状だけは受け取って欲しいのです」と。
髙信 紫花(小2) 福島県
わたしのおとうさんは、たんしんふにんをしています。
おかあさんは、おとうさんのぶんまでがんばっておうちのことをしてくれています。
この前おとうとが
「パパがいないとさみしい。」
と言って、おかあさんをこまらせました。
それからまい朝おとうさんはおうちにでん話をかけてくれます。
いつもは、私が学校に行った後にかけてくるので、わたしは、お話ができません。でも今日はやっと話ができました。
たくさんお話することがあったのに、とてもうれしくて何を話していいのかわからなくなってしまいました。
「あのね、パパ、え~と。え~と。」
「なぁに。」
「えーと、わすれちゃった。」
「じゃあ今どいっぱい話そうよ。」
今どは、わすれないでぜんぶ話せたらいいなあと思います。
白岩 麻里子(51) 東京都
田舎に帰省するたびに、いつも目にする光景は、八十三歳の父が毎日、分厚い日記帳をめくりながら、「去年は何日に帰ってきているな。」とか、「去年の今日は、こんなことがあった」とか、一人でつぶやいていることである。いつもの光景だったが、なぜか今年、父に尋ねてみた。「お父さん、いつから日記をつけているの?」「もうかれこれ五十年以上かなぁ。」と、父はぽつりとつぶやくように答えた。そういえば、私が物心付く頃には父はいつも日記をつけていた。そして買い替える時はいつも三年分書くことのできる分厚い日記帳である。
なぜか今年は妙に感慨深いものがこみあげてきた。「同じことを五十年以上続けることはすごいことだね。」私は心底そう思い、思わず口に出た。父は苦笑いをしながら、「お父さんは、これ以上に何も能力がないからね。」と照れくさそうにポツリと言った。
思えば、私が二十代の頃、世の中はバブル景気だった。会社には周囲にバリバリと働く元気な男性がたくさんいた。父はおとなしい性格で、とても仕事ができるタイプではなかった。仕事のできる上司と父を比較し、私は無口な父と、ろくに口もきかなかった。それどころか、父の問いかけに返事もしないことも多かった。
父は定年後、のんびり家にいるが、日記だけは欠かさずつけるのを、私は横目で見てきた。
私が東京で一人暮らしをするようになってからは、父からハガキがよく届いた。ハガキの裏面に、いつも小さい字でびっしりと書いてきた。内容はその日にあったこと、気候のことなど、他愛もないことだけだった。そしていつも最後に、私が元気で働いているから、お父さんはいつも安心している、と言うものだった。最初の頃、あまりにびっしりと文字が書かれているので、読むのも面倒で斜め読みでざっと流し、返事も出さなかった。もう、たびたび送ってこないで、なんて思っていた。それでも、バレンタインデーの前には、チョコレートくらい送ってやろうと、適当に選んで送ったこともある。すると、一か月後のホワイトデーにマシュマロが二袋も届いた。さすがにうれしいというよりも、同じものを二袋もいらない、ありがた迷惑に思ったこともある。
そんなふうに、今まで特に父の存在を意識することもなく、おとなしい父を半ばさげすみに近い気持ちで接していた。それなのに、今、目の前の白髪の姿を見て、すごいと思えるのはどうしてなのだろう。
時の流れが私をも変えた。半世紀を生きてきた私。そして、今だから父の歴史、そしてこれまでの父の苦労を理解できる。
私の誕生日に、また父からハガキが届いた。そこには、「誕生日おめでとう。誕生の日はお母さんが一番苦しんだ日。だから生まれてきたことを、お母さんに感謝してね。」と書かれてあった。私はその瞬間、はっと目が覚めたように、その言葉に納得した。同時に母親に対しても新たな思いが込み上げてきた。そして、平凡な家庭、平凡な両親だけれど、改めてこの父と母の子どもに生まれてよかった、と神様に感謝した。
これまで、自分のやりたいように生きてきて、親の忠告にも耳を貸さなかった。そして未だに結婚もせず、親元を離れ自由気ままに暮らし、親に心配ばかりかけている。でも、心の中ではいつも親不孝な娘で申し訳ないと思っている。
父は相変わらず、時々日記帳のページをめくりながら、毎日のように日記をつけている。周りで何が起きても、何を言われようとも、ただ黙々と書き続けている。
父は、あの頃の私の傲慢さを許してくれるだろうか?
でも、もしかして鈍感な父は私があの頃、父を無視していた事さえ気づいていないのかもしれない。
そうであってほしい。
でも、そんなことより、ただ、何より今、父の偉大さを確信出来てよかった。今、目の前にいる父の姿を見て、そう気付いてよかった。
父に今の私の思いは伝わっているだろうか?
これからも今のままの父でいい。ただただ元気で日記を書き続けていってほしい。
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
鬼塚 君枝(57) 福岡県
押し入れにしまっていた父のブーツを取り出して、
「だれか、はかんね?」
と母が言った。父が亡くなった後、箱に入れて、しまい込んでいた黒い革のブーツ。まだ新品のようにきれいにしていた。
「えェ?だれも履かんやろう。」
私は、そう言いながら家に持ってかえった。
主人には大きく、息子には小さい父のブーツを、私は仕事場の片隅にオブジェのように飾っている。35年前のものとは思えない程きれいにしている。それを見ると、遠いあの頃の父を思い出す。
母は毎朝、父が出勤する前に車を洗って、靴を磨いて、それを玄関に並べて送り出していた。それは母の日課だった。私は小学生の頃、母は体が弱くて寝込んでいる時間があった。漢方薬を煎じて飲んでいたので、小さな家の中ににおいがこもっていた。ある日、学校帰りに家に入らず玄関の外に立っていたら、父が帰ってきた。父に、
「なんで、はいらんとね?」
と、言われ、
「だって、くさいもん!」
と、私が言うと、父は静かに、
「きみえちゃんは、匂いだけで、臭い、臭いって言っとうけど、おかあさんはその臭い薬を口から入れようとよ。」
と、言った。私はハッとして、心の中で、(お母さんごめんなさい)と、思った。
優しい父だった。優しすぎて病魔に負けたのか。私が大学4年生の時、父は、胃がんが見つかって、私が通っていた大学の病院に入院した。大きかった父は、すっかり痩せてしまった。私の手首を握って、
「なんキロ?同じ位になったろ?」
と、苦笑いした。私は泣きそうになったのを我慢した。学校帰りに毎日病院に寄った。外資系の航空会社を受験して落ちた時、
「ごめんね、お父さんにコネがなくて。そんな所はコネがないと合格せんくさ。」
と、慰めてくれた父。
でも、お父さん、私は次の年、その会社に入社したのよ。おとうさんに伝えたかった。私が大学を卒業して三カ月で父は亡くなった。病院のロビーで写った式後の写真。振り袖の私と、?せてしまったガウン姿の父が最後の写真となってしまった。
入院前は、なぜかよく父母と私は三人で小旅行に行った。まもなく来るであろう別離を父は感じていたのか。最後に言った萩では、泊まるところがなくて、小さな民宿に泊まった。山と田んぼがみえる小さな部屋に三人並んで寝た。今度は、私の運転で天草に行こう、と約束したのに、果たせないまま、終わってしまった。
建築業をしていた父が手がけた建物が街のあちこちに残って、その歴史を物語っている。しかし、新しい道路建設のために解体されたい、老朽化で壊されたビルもある。父が建てた我が家も無くなり、今ではバイパスの下に思い出を封じ込めている。父の魂のかけらがひとつずつ消えていって、記憶の粒もちいさくなって行く。それなのに、わたしの傍らにあるブーツは、あの頃と同じように父を待っているかに見える。そこだけ時が止まっているかのように。ピカピカに磨かれた父のブーツを見ると、私は父を恋しいあの頃の自分になってしまう。
齋藤 俊介 東京都
ぼくの箸と親父の箸が一枚の刺身をつまんだ。親父はムスっとしたままそれをぼくに譲ってくれた。母親はそれを見てクスッと笑う。
親父はとても寡黙な人だ。晩酌の時でさえニコリともしない。そんな親父が昔から不気味で怖くて苦手だったけれど、嫌いじゃなかった。
親父は航空整備士だった。ぼくの物心のついたときには働き盛りだったから夜勤と日勤を繰り返していて殆ど食事を共にすることもなかったし、親父がどんな人でどんな仕事をしているのかも子どものぼくにはさっぱりだった。時々ランドセルを置きに帰った午後夜勤前の親父と遭遇した。親父はいつも英語だらけの小難しそうな書類にマーカーを引いていたけれど、ぼくの顔を見やるやパタンとファイルを閉じて「おかえり」の代わりに軽く頷く。毎度のことながらぼくは驚いて「ただいま」も言わず急いで遊び場へ逃げ出したのを思い出す。そんな親父との関係だったから、親父の仕事ぶりを直接に見たのはずいぶん後になってからだ。二十歳に少しばかり毛の生えた頃、当然将来に思い悩んだぼくは勝手に退学を決めてしまった。何気なく母親に切り出すと案の定烈火の如く怒り狂い泣き叫んだ。そうしてぽつり「お父さんに直接言いなさい」と。親父にだけは完全に事後報告にしたかったけれど、母親の乱れっぷりに負けて親父に会いに行った。親父は当時四国の空港に単身赴任していたから、ぼくの突然の訪問の打診に慌てたようだったが、到着日時を確認するとあとは何事もなかったように電話を切った。到着してすぐにぼくは指定された場所に行った。そこは瀬戸内の海が一望できる高台の店で、親父はすでに座して茶をすすっていた。ぼくの顔を見るなりいつもの「おかえり」替わりの一頷き。ぼくは緊張して問面に座す。「海が良いだろう?」窓の遠くを見ながら珍しく親父から口を開いた。「今から行くからな、あそこ」それだけ言うとぼくのコーヒーが飲み終わらないうちにそそくさと車に乗り込んでしまった。瀬戸内の沖で親父とぼくは釣り糸を垂らしていた。「ここはな、アジの穴場だ」そう言う親父は子どもみたいに笑っていた。漁船に乗ってからずっと親父は楽しそうで、釣りを知らないぼくに何から何まで教えてくれた。そして夕暮の頃には大漁のアジとともにゆったりと浜を目指していた。親父は沖合の方を見ながら妙に穏やかな口調で言った。「話、あんだろ?」突然のことにくちごもっているぼくに「いいよ、分かったから。好きにすればいいさ。でもな、夢ってのはきっと、船を進めるためのガソリンみたいなもんじゃないか?ガソリンばっかあっても船がねえんじゃ仕方ねえ気もするんだよ。よく分からねえけど、な」それきり親父は口を噤んでしまった。話はもう終わったんだ、ぼくは生まれてはじめてちゃんと親父の言葉を聞いた気がした。
かえりの便を待つ間、ぼんやりとジェット機の準備を眺めていた。ツナギ姿の幾人かが何やらせかせかと作業をしていた。その一人が親父だった。機内に乗り込み窓から親父の作業を見ていた。瀬戸内の沖で見せた顔とは打って変わった引き締まった表情に何故かぼくも緊張した。あらかたの作業も終わりやがて飛行機は離陸体制に入った。その時親父は飛行機に敬礼をしていた。今もう一度それを見たら多分吹き出してしまうと思うけれど、その瞬間のぼくには直立した親父の姿が誇らしいものに見えた。高度三千m上空でどうしてか涙が止まらなかった。
もうすぐぼくは親父になろうとしている。けれども父親というもののイメージが上手く持てない。きっと寡黙で子供から怖がられて、それでも子供に甘くて、一晩僅かな酒で気持ち良くなってソファで鼾をかくんだろう。たった今目の前でぐうすか鼾をかいて眠るソファの初老のその人に、そっと毛布をかけながら、急に「ありがとう」と言いたくなった。
印南 房吉(83) 神奈川県
お父さん、暫らく振りに言問橋に来ました。一見一驚、期待通りでしたよ。あのスカイツリーが言問橋の巾でニョキョッと聳えていました。いや一言、言問橋が立ち上がってスカイツリーになったんですね。鉄骨がビッシリ組んで空を刺したと云った具合ですね。東京の新しいシンボルに間違い有りません。
ゆっくり渡りました。あの日と同じ様に橋の下を風が吹き抜け広々とした隅田川、実は今日三月二日はお父さんと並んで橋を渡った紀念日なんですよ、憶えていますか、私の中学合格発表の朝なんですよ。起き抜け突然「一緒に行こう」と他の約束を全部断って黙々と橋を渡りました。ポンポン船が艀を五杯、音ばっかり景気良く曳いて川を遡っていました。橋を降りて墨堤の未だ固い桜並木を言問団子の方に先刻のポンポン船と並んで歩きましたっけ、正直、合格しているかどうかが胸につっかえていました。
日段減多に笑わないお父さんが私の番号を素早くチェックして
「アッタゾー、おい、アッター」
と大声をあげニヤリとしました、私も嬉しさドッと胸一杯、帰り道、角の大きな蓄麦屋に入り「好きなモノ食べなよ、腹あ減ったな」とメニューも見ずに「俺は抜きで一本」と奥に云いました。私は此の時とばかり上天井、それにしても抜きで一本とは何だろかとメニューを見ても判りませんでした。来た、上天井!金色の大丼、大きな蓋を取るとフワーツと素晴らしい香り、ヤッター、以来外で食べる時は何処でも天丼、今でもそうです。お父さんの「抜きで一本」は何とメシ抜きの天丼の事で大エビ三本の天婦羅に熱燗一本でした。お父さんは自分でトコトコ注ぐとクイッと一口。「ウン、良かったな、オイ良かったなあ」と何度も頷きトコトコ注いではクイッと旨そうでした。私は大きくなったら蕎麦屋で「抜きで一本」と注文しようと思いましたがこの齢になっても遂々云えません、お父さんはヤッパリ浅草でしたね。
お父さん、今度桜の時分に来ます。お母さんが好きだった隅川の花吹雪、そして流れる花筏、無性に懐かしくなりました。
田口 吉一(6) 大阪府
テレビで、ロンドンオリンピックをみていたら、たいそうせんしゅが、しろいだいのうえを、かっこよくとんでいた。「これなに?」ときくと、おかあさんが「ちょうばよ。はこのうえをとぶ、とびばこににてるね。」といった。しごとからかえってきたおとうさんに、「ぼくもとびばこしたい。」というと、「ばんごはんのあとならいいよ。」といってくれた。ごはんがおわると、おとうさんは、たたみのうえにすわって、てであたまをかくして、まるくなった。おとうさんは、からだがおおきいので、おおきいダンゴムシみたいだった。おちたらいたいかなとおもって、こわかったけど、おとうさんが「だいじょうぶだよ。てをとおくにおいて、あしをいっぱいひろげてとぶといいよ。」とおしえてくれたので、ゆうきをだしてとんだ。ぼくのあしが、おとうさんのあたまにあたって、おとうさんが「イタ!」といった。ぼくのおしりがおとうさんのこしにおちたときも、おとうさんは「イタ!」といった。なんだかおもしろくて、わらってしまった。なんかいもとんで、じょうずになってきたので、つぎはぼくがとびばこになりたくなった。ぼくもたたみのうえで、ちいさいダンゴムシみたいに、まるくなった。ぼくのうえを、おとうさんがとんだら、おもくて、ぼくは「ウッ!」といった。また、おもしろくて、またわらった。いっぱいあせをかいたけど、たのしかった。
堀江 千春(28) 東京都
父の存在がコンプレックスだった。友達のお父さんみたいにスーツを着て会社に行くわけではなく、私が高校生の時には務めていた工務店も辞めてしまった。父の職業を聞かれるたび、なんとなくごまかしていた。「お父さん、いないんです。」そう答えられたらどんなに楽か、なんて考えたりしたこともあった。
学校を卒業した私は、上京して一人暮らしを始める。それは、父の存在から離れたいという気持ちもあったのかもしれない。父以上に稼いで、貧しい自分を打ち消した。それでもときどき父の話題になることもあり、そのたびに私は苦しいような、気まずいような気持になって、相変わらずごまかしていた。
そんな私も結婚することになった。実家へのあいさつで、恋人に貧しい実家を、頼りない父を見せることになる。本当に嫌で、恋人に事前に何度も「汚いから、貧しいから」と言って出かけたのだった。父親は、やっぱり頼りなくて、恥ずかしかったけれど、優しい恋人は受け入れてくれた。
恋人は先に帰って、私は実家で結婚式で使おうと、子供の頃のアルバムを引っ張り出してみた。赤ちゃんの頃の写真を見るのは、ほとんど初めてだった。若い両親が私を抱いて笑っている。「その帽子はお父さんが編んだのよ」と横から母が一枚の写真を指差す。赤い毛糸の帽子をかぶった、小さな私。何だか、涙が出て止まらなかった。
結婚式当日、『両親への手紙』は恥ずかしくてやらなかったけど、父からまさかの『娘への手紙』。生まれてきてくれてうれしかったこと、人生にたくさんの春が訪れるようにこの名前を付けたこと、そしてこれまでも、これからも離れていても応援しているということ。恥ずかしく思う必要なんてなかったんだ。おとうさんごめんね。おとうさん、ありがとう。
西澤 傑(25) 東京都
私には父親が二人いる。二人いると言っても、一人にはほとんど会った事がい。それは生まれてすぐに離婚してしまったからである。今はもう一人の親のおかげで、大きくなった。今の父親、という言い方は、嫌いだ。父親は父親、オトンである。オトンは、髪の毛がバカボンドの宮本武蔵のような髪型をしている。このような髪型をしているのも、美容師という職業柄であろう。オトンからは黒人音楽を教わり、そして生き方を教わった。数年前は「オトンのアホばけカス!」や「いつかチクワにしたんぞ!」等と、反抗もしていたが、子供がいてもおかしくないような年齢に自分がなると、改めてオトンの大きさを感じた。「好きな女とはいえ、違う男の子供に、オレは愛情を持って育てられるだろうか」と。この言葉は直接、オトンには言えない。言うと調子にのり、「そんな言葉よりプレミアムモルツでも買ってこんかーい!」となったあげく、「オレがお前の年齢の時は、すでに働いていた!」と、酔った勢いで苦労自慢されるだろう。今では私も大人なので、オトンなりの照れ隠しかな、とその話を五分は聞いていられるようになったが。
本当の父親、このような言い方も嫌いなのだ。だから、お父さんとしよう。オトンは髪の毛がフサフサなのだが、私は若くして M字ハゲである。それをごまかすのも嫌なので坊主頭にすると「鉄腕アトム!」とあだ名がつくほど、剃り込みが入っている。それはお父さんのせいである。お父さんは写真でしか見た事がない。正確には見ているのだが、小さすぎてほとんど覚えてはいない。このお父さんは、でこっぱちである。母親の話によると、お父さんのお父さんは、ハゲていたそうだ。私は間違いなくその遺伝子を受け継いでいる事になる。くそう!と思う事もあったが、今ではこの頭が、お父さんとの共通点である。なんだか、おでこが愛おしいではないか。すりすり、である。
私には父親が二人いる。昔は「なんでやねん。なんで普通じゃないねん」と嘆いていた夜もあった。だが、今はこう言える。私にはお父さんとオトンがいる。二人のおかげで私はこうしている。二人もいるのだ。どうだ、うらやましいだろう? そしてありがとう、と言葉通り言える毎日である。
中村 真理子(27) 大阪府
青天霹靂だった。
その日は「聖バレンタインデー」だった。昨日まで、幸福な家族であったのに、私が高三受験時、父は「駆け落ち」して家を出た。
無責任な父が許せなかった。
それが原因ではないだろうか、それ以来、私はずっと「鬱」が続いている。未だ治癒ならず。
その父は「営業マン」であった。営業マンであっただけに「靴は顔である」と言い、毎日自分で靴をせっせと磨いていた。 すり減った靴底。泥だらけになった靴は、父の勲章であるかのように思った。そんな真面目で一生懸命な父を、私たち家族は心から尊敬し、誇ってもいた。帰宅すれば玄関には靴をちゃーんと並びそろえて自分の心もそろえていたのだ。古き良き日本の教えを靴をそろえることで、私たち子どもに伝えていたように思う。 父の靴に、たくした思い。父の背を見て私と弟は育ってきたのだ。真面目で誠実で子煩悩で・・・。
私は父が大好きだった。お父さんっ子であった。信頼もしていた。でも、現実は違っていた!?母、障害がある弟、そして、私の家族を捨てた。そして父の本能のおもむくままに、好きな女性の元へと去っていった・・・。
(父に何があった!?何故?)
ショックだった。でも、その時点で私は父をあざ笑った。
(な~んや、しょうもない奴。たんなるおっさんやったんや!)
自分自身に言い聞かせることで少しは楽になったように感じた。異性問題は、人間本来の理性が失われると言われている。どうやら、父もそうであったようだ。父も単なる男にすぎなかったのだ。この父の行動は、我が国の「法」では触れないことだ。しかし、人間として、父親として許されるべき行為であったのか・・・。道徳モラルに反する行為であったはずと私は、ずっと父を責め続けてきた。
あれから、もう10年。いろいろあった。わたしは相変わらず体調すぐれず、せっかく入学した大学も途中退学してしまった。祖母も、随分年いったが、家事頑張ってくれている。母は毎日、職場でいじめにあいながらも、稼ぎのため勤めにでている。弟も社会人となり「介護福祉士」として社会のお役に立つほど成長した。成人となり年月が経つごとに、あの時の怒り、悔しさは徐々に緩和されている。ときに父に会ってみたいと思う。父はどんな声で私を呼んでくれてたっけ。もう1度、父の声聞きたい。顔見たいと思う。
お父さんへ?
お元気ですか?お父さんは今、幸福なのでしょうか?お父さんが家を出てから、今年でもう10年になるね。私はもう27歳になったよ。あの日は、ちょうど「バレンタインデー」だったね。寒い日だった・・・。私は、いつものように、お父さんのためにチョコレートを用意しておいたんだよ・・・。とびっきりの笑顔見たかったな。あの時渡せなかったチョコ、又、プレゼントしたいなあ。
毎年、今もこの時期になると普通の女の子が恋人にときめく心で選ぶように、私も真剣にチョコ探しに夢中になっているんだよ・・・。
お母さん、ゆう、私にとっても、この日だけはとても複雑な気持ちの「バレンタインデー」を迎えています。
あるひ、私は見たよ。お母さんが、お父さんの靴を時々は取り出して磨いては「風」を入れている。お父さんが「シンデレラ」になっている。そんな気持ちで、お母さんは、お父さんのことを今でも愛しているよ。心の奥底に、思い出をしまっているよ。そして、ゆうは、お父さんの「靴は顔である」、その思いをしっかり受け継いでいるよ。靴はきちんとそろえて、心もそろえている。あの幼子の彼とは違う・・・。表情、優しく、気配りもでき、心豊かな青年に成長したように思う。彼も、もう24歳。お父さんの生きざまをみんなが世襲しているよ。
「お父さん、お父さん、お父さん・・・」
心の中でいつもこだましています。一度は声に出して叫びたい。「お父~さ~ん!」
私はここにいます。会いたい!!
あなたの娘より