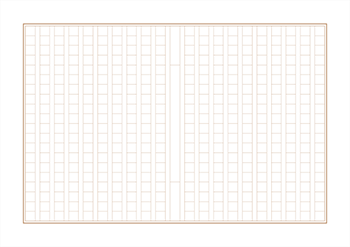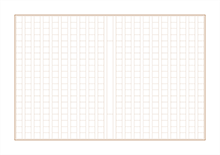お父さんへの作文コンクール入選結果2023~2020
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
藤本 千尋(6) 愛知県
ととは、たまにかかになります。スカートははきません。じょりじょりのひげもきえません。でも、ごはんをつくってくれたり、おせんたくをしたり、ちょっとへたくそだけど、ゼッケンとかをつけてくれようとします。
かかはたいいんしてからも、すぐつかれちゃいます。だから、かかがたいへんなときは、ととがかかにへんしんします。小がっこうのはじめてのさんかん日も、ととがきました。みんなはおかあさんだったけど、ととはいつもこうえんでみんなとあそんでいるので、
「あ、ちいちゃんのおとうさんだ!」
とだいにんきでした。みんなによばれて、ととはたのしそうでした。わたしは、いつもいっぱいあそんでくれるととがだいすきなので、うれしいきもちになりました。
おおきくなったら、ととといっしょにおふろにはいれません。じゅぎょうがいっぱいになったら、いっしょにあそぶじかんがへるかもしれません。おおきくなるのはうれしいけれど、それはちょっと、さみしいです。わたしがおとなになったら、ととはおじさんか、おじいちゃんです。でも、わたしがこどもをうんだら、わたしとあそんでくれたみたいに、いっぱいあそんでくれるとおもいます。いつまでも、じまんのととでいてほしいから、ずっとげんきでいてくれるように、まいにちニコニコたのしいはなしをしてあげます。そうしたら、まいにちたのしみで、げんきがでるでしょ。とと、ずっとだいすきだよ。
小松﨑 有美(38) 埼玉県
バカという言葉が一番嫌いな父。そんな私もまたその言葉に悩まされた。三年生なのにひらがなが読めず、九九が言えない。そんな状況からついたあだ名はバカボン。バカ殿なんて言われたこともあったような。いま思うと発達障害だったのかもしれない。読み、書き、計算。どれをとっても人より遅く、クラスから置いてけぼりを食らった。
だけど父は私に人一倍やさしかった。漢字が書けなくても『ににんがに』になっても、絶対に責めなかった。それどころか優しく教えてくれた。だから父の前では唯一『バカ』を忘れられた。私はこのままでいい。いいんだ。そう信じることができた。
しかし、事件は起きた。あれは父親参観日。その日は図工で描いた父の似顔絵が展示された。どの作品も心の込もったものばかり。しかし私のを見るなり目を疑った。なぜか似顔絵に『バカ』と書いてある。こんなことを一体誰が。私は怒りで震え、悔しさでさらに震えた。すぐに先生がやって来て「こんなことをする人は誰ですか」という犯人探しが始まった。私は『バカ』と書かれた悔しさより、それを父が見てしまう焦りの方が強かった。
来ないで、父さん。
止まって、時間。
泣くな、わたし。
消えろ、落書き。
先生は私だけを呼び出し、この絵を取り外してもいいかと尋ねた。描き直す時間はもうない。私は絵を見つめながら、しばらく考えた。
父は似顔絵が展示されるのを知っている。だから……。
父は私が居残りをして描いていたことも知っている。だから……。
何より父はこの日を楽しみにしていた。だから……。
「そのまま飾って下さい」
先生は目を丸くして「本当に」という表情を見せた。それも無理はない。『バカ』の字は画用紙の中央に書かれ、修正はおろか、消すことすらできない。それでも私の絵だけなかったら父はきっと悲しむと思った。
「どんな絵を描いたかじゃないよ。どんな気持ちで描いたかだよ」と言う父に、やっぱり絵を見せたかった。
父は教室に入るなり、事情を聞いた。似顔絵も見た。落書きにも気づいた。だけど何も言わず、すぐにペンを取り出して、『親』とつけ足した。たちまち『バカ』は『親バカ』に。私への中傷は、私への愛情に、書き換わった。
うちの娘にバカなんて言うなよ。かわいい娘だぞ。バカなんて許さないぞ。
『親バカ』の字に込められた父の叫びが聞こえた気がした。
あれから何十年も経つが帰省のたびに父は「孫も娘もかわいいなあ」と目尻を下げる。そんな父を見て、親の愛に勝るものはないと感じる。長年いじめに遭ってきたなら、尚更。
今なら言える気がする。
私を守り、愛してくれた父に。
「お父さん。私も『バカ』は嫌いだよ。こんなひどい言葉は大嫌い。でもね、親バカなお父さんは大好きだよ!」
野入 桃子(9) 福岡県
お父さんの額には傷がある。お父さんが子どもの時に、けんじゅうでうたれた傷なのだそうだ。もう五十年以上も前の話らしい。
「うそ。絶対うそだよ。」
そのことを友達に話したら、私はうそつきになってしまった。
「うそじゃないよ!お父さんに聞いたもん。」
言い合いになっても一歩も引かなかった。だって私はうそつきじゃないし、これはお父さんから聞いた話だったからうその訳がない。
仕事から帰ってきたお父さんに、友達との出来事を話した。
「えっ?話したの?これは水ぼうそうのあとだよ。」
私はショックだった。本当だと思っていた話がうそだったなんて。うそだってことが本当はうそみたい。うそと本当で、なんだか頭がクラクラしてきた。私は思わず泣き出してしまった。私がうそをつくつもりはなくても、結果的に友達にうそをついてしまったことになったのがくやしかったからだ。
「ごめん!じょうだんだったんだよ!」
お父さんは私に何度もあやまった。
うそって何だろう。私は考えた。うそとじょうだんは何がちがうのだろう。国語辞典で調べてみた。うそは、真実ではないことを本当のように言うこと。じょうだんは、遊びで言う言葉、ふざけた内容の話。なるほど、たしかにお父さんの話はふざけている。
自分が本当だと思って話したことが、本当はうそだった場合、私はうそをついたことになるのだろうか。難しくてわからなくなってきたので、お母さんと話し合ってみた。世の中には、いろんな話や様々な情報がある。それらを見たり聞いたりして、それが本当に信じていいことなのか、そうでないのかを考えて決めるのは自分自身だ。その決断を間違えてしまわないように、様々なことを勉強してたくさんの経験をすることが大切なのだとわかった。
次の日の朝、お父さんが仕事に行く時「おみやげに桃ちゃんの好きなおかしを買って帰るね」と言って出かけて行った。腹が立っていたので私は返事をしなかった。お父さんは、きっと本当におかしを買って帰ってくるだろう。けれどもしばらくは、お父さんの言うことは信じないと私は心に決めている。
お父さんはくだらないうそばかりついて、いつも私をからかう。ふざけてばかりのお父さんが、真面目なお母さんと結婚できたのは、きせきだと思う。少しいじわるを言いたくなって、そうお父さんに伝えたのに、お父さんはうれしそうに笑って言った。
「桃ちゃんが産まれて来てくれたことが、パパの人生で一番のきせきだよ。」
お父さんはじょうだんばかり言うけれど、この言葉は信じてあげよう。
國吉 桃美(5) 青森県
「パパいってらっしゃーい」
パパがたたかいにむかった。きょうもわたしのパパはてきとたたかう。てきは、とても強い。いま、ちきゅうのみんなもたたかっているてきだ。
わたしのパパは、しょうにかのおいしゃさん。まいにちびょうきやけがの子どもたちのちりょうをしている。いま、一ばんのきょうてきは、コロナウイルス。
パパは、どんなにたいへんでも、くじけない。うちゅうひこうしみたいなぼうごふくにへんしんしてかんぜんぼうびで立ちむかう。なつのあつい日は、あせがいっぱいでてたいへんっていってた。
パパは、じぶんがコロナウイルスにかんせんしても、こういしょうでくるしくても、がんばりつづける。まるで、わたしの大すきなプリキュアみたい。
プリキュアは、へいわをまもるみんなのヒーロー。どんなにてきが強くても、あきらめない。
パパは、いつもおしごとでいそがしいけどおうちに帰ってくると、わたしとあそんでくれる。プリキュアのとくいわざをいっしょにしてくれる。うたはちょっぴりおんちだけど、おどりをノリノリでおどるしおもしろい。
パパとあそんでいるときに、びょういんからでんわがきてきゅうにおしごとにいくときもある。ほんとうはもっといっしょにあそびたかったのに。
でも、プリキュアもわるいてきがきたら、どんなときでもとんでいく。パパはプリキュアとおんなじなんだね。みんなのためにがんばっているんだね。わたしはパパにいっぱいあまえたかったけど、がまんしたよ。
わたしは、プリキュアみたいなパパが大すき。たくさんの人をすくうために、いっしょうけんめいなプリキュアが大すき。
パパ、わたしね、七夕のねがいごと、たんざくにかいたよ。
「プリキュアになりたい。」って。
大平 真由美(42) 東京都
私の父は見た目が怖い。目つきも鋭く、声も低くて大きい。サングラスなんてかけてしまうと、近寄らない方が良さそうな、かなり怖いおじさんになる。
そんな見た目の父だが、私にとって、小さい頃からとても優しくて、尊い存在だった。
父は無口で謙虚な性格なので、自分から自分のことを話すことはほぼなかった。しかし、
「お父さんは頭の回転も早くてスポーツも何でも出来るから、会社の人や友達とかみんなに信頼されてるんよ。」
と母が口グセのように言っていたこともあり、父は何でも出来るスーパーマンのように思えていた。
確かに、スーパーマンではないが、父にはすごく不思議なパワーがある。
私は小学生の時、算数が苦手で、授業中に先生が説明してくれる内容だけでは、全く理解出来ていなかった。しかし、家に帰って父に説明してもらうと、魔法の言葉なのかと思うくらいに、頭にすんなり算数の公式が入ってきて、なぜかスラスラ問題が解けるようになるのだ。スポーツでも器械体操でつまづいた時、コーチ経験があるのではないかと思えるほどの的確なアドバイスをくれ、全ての体力テストを合格へと導いてくれた。跳び箱の練習の時には、家で布団が幾重にも重ねられ、布団が高くて柔らかい遊具のような跳び箱に変身したので、楽しく遊んだという記憶しかない。そして今でも父のパワーは続いており、私の子供達もその恩恵を授かっている。全く出来なかったことが、父に一度教わっただけで克服出来てしまうのだ。何度も私と練習したのに乗れなかった自転車も、父とのたった一日の練習で、補助輪なしでスイスイ乗れるようになったり、怖くて大嫌いだった鉄棒も、あっという間に逆上がりまで出来るようになって「鉄棒大好き」と言わせてしまうほどになっていた。オムツ外れが進まなかった末っ子は、父とトイレに行ってどんな約束をしたのだろう、数日でパンツマンになっていた。
父の不思議パワーは、もう一つある。
本能で行動する動物や、直感で動くような小さな子供達に、父はやたらと好かれるのだ。
犬も、飼い主の私よりなぜか父にばかり懐いていたし、他の動物も不思議なことに父の方へ近付いて父から離れないのだ。
私が可愛がって大事に育てていたインコも、父が指を差し出した時だけ、毛をフワフワに逆立たせて喜びを表現し、歌っているかのように父の指に向かっておしゃべりし始めるのだ。父は、動物達にとってまるでムツゴロウさんのような存在なのだろうか。
初めて会った子供達もなぜだろう、あたかも父と今までお友達だったかのように、父に近づいて話しかけてくる。
見た目は怖そうだけど、父の人柄が動物や子供達を引きつけるのだろう。
私の子供達はもちろん、父が大好きで、父の隣に誰が座るかという理由の喧嘩が頻繁に起こる。いつも私の事が大好きで、私から離れようとしない末っ子でさえ、私の事が視界に入っているのかも分からないくらいだ。
そんな不思議パワーを持つ父を、今も私は心から尊敬している。きっとこのパワーは、父の優しさの表れなんだと思う。コロナが流行してから持病がある父と会えない日が続く中、母から箱いっぱいの果物が毎月届く。私は、まだあるから大丈夫だよと伝えようと母に電話をした。すると母は、
「お父さんがあなた達に食べさせたいんだって。コロナで手伝いにも行ってあげられないから、美味しい物を早く送ってやれってうるさいんよ。お父さん、子供達だけじゃなく、あなたにもちゃんと食べさせられるようにっていっぱい買ってたよ。」
と教えてくれた。
こんなにあって食べきれるかな。
箱いっぱいの果物を見て、あふれんばかりの愛情を感じ涙がこぼれた。
『お父さん、ありがとう。
遠く離れていてなかなか会うことが出来ないけれど、お父さんパワーのおかげで、子供たちも元気にすくすく育っているよ。
子供達と一緒に、私も沢山果物食べるね。』
果物から父の不思議パワーをもらった気分だ。
今尾 僚子(46) 千葉県
父が事故で亡くなった時、みんな心から悲しんだが、誰も「○○をさせてあげたかったね」とは言わなかった。父はマイペースで、やりたいことは何でも実現する人だったからだ。
商社に勤めていたため、海外へ単身赴任している時期が長かった。
私が高校生だったある年、12月上旬に帰国した。大きなトランクと中くらいのトランクと、小さなボストンを一つ持って。
家に入るなり、中くらいのトランクを開けると、玉手箱のようにぎっしりとお土産が入っていた。今年はきっと、クリスマスとお正月を家族と過ごすために早めに帰国したのだろうと、心が温かくなった。
久しぶりに父が毎日いて、夕食のおかずがいつもより二品多い日々が続いた。
12月24日の朝に、父が「じゃあ行ってくるね!」と言った。どこへ?
父は、一人でマレーシアのセブ島にダイビングに行き、クリスマスとお正月を含む2週間を島で迎えるのだという。そう、開かれなかった一番大きなトランクには、ウェットスーツやボンベが入っていたのだ。
白けた気持ちで手を振る私に、父はとびっきりの笑顔で振り返した。そういう人だった。
数年おきに、日本と海外が交互に勤務場所になった。赴任先は計7か国に及んだが、父はどの国に行ってもその国の言葉が話せるようになって帰ってきた。
赴任中、印象的に覚えているのは、現地の家庭教師を雇い、熱心に勉強する姿だ。仕事のあと、平日は毎日のように机に向かい、英語と現地語のちゃんぽんで家庭教師と真剣に話し込む。
その後ろ姿は、勉強は子供だけのものでも、やらされるものでもないこと、努力の先には実りがあることを教えてくれた。
同調圧力にも負けない人だった。
30年前の、長時間残業が美徳のような時代に、週2回は家族との夕食に間に合う時間に帰ってきた。同僚は毎日深夜まで仕事をしていて、早く帰っているのは父だけだと聞き、心配した私たちに父は言った。
「仕事を終える時間から逆算すると、自然と優先順位とかけていい時間が決まってくる。通勤中に段取りを考えて無駄なくやってるから、週2日位早く帰っても仕事は終わるんだよ。時間は作るものだよ。」
そんな父だから、仕事自体の評価は高かったようだが、さほど出世しなかった。
定年退職してからは、週3日は朝7時から原付でテニスに行き、英会話サークルの先生などもしていたが、その毎日にも飽きたのか、青年海外協力隊のシニア版である「海外シニアボランティア」に応募し、アフリカのチュニジアに赴任した。
日本企業誘致のための支援業務を担当するとのことで、チュニジアの外務省に毎日通勤し、時にはチュニジア側の代理人として、海外工場の設置を検討している全国の日本企業の担当者と話したり、充実した毎日を楽しく過ごした。
率直で粘り強い父は、チュニジア政府から厚い信頼を受けたようで、シニアボランティアは1期で交代するのが規則なのに、外務大臣からの強い続投要請を受けて特例でもう1期務めるのだと、父は嬉しそうに語った。
チュニジアからの“出国”で帰国して、久しぶりに家族揃って夕食を食べた。
日本にいる間は、仕事に差し支えない金曜と土曜だけ晩酌をするのが父の習慣で、その横でおつまみを横取りしながら他愛のない話をするのが私の習慣だった。
テレビでは藤原道長の特集をしていて、かの有名な「この世をば我が世とぞ思う望月の 欠けたることもなしと思えば」という和歌の紹介をしていた。
画面いっぱいの、煌々と輝く満月。
父が言った。「パパも今まさに満月みたいな気持ちなんだよね。やりがいのある仕事があり、信頼できる仲間がいて、愛する家族がいる。いい人生だったと思う。」
私は胸を突かれて、わざと横目で言った。「天下人になぞらえるとは、ちょっとおこがましすぎない?」父は大笑いして、私の頭を撫でた。
その1週間後、父は事故にあった。駅の階段を駆け下りて、足を滑らせたのだという。初孫の出産予定日だったから、生まれたという連絡を楽しみに、家路を急ぎ過ぎたのかもしれない。
電話を受けて、現実味のない中で向かった病院で、父の意識は戻らなかった。父の手は、乾いていてごつごつと硬くて、何も変わらないのに、もう私の頭を撫でてはくれない。
私は、あれは本人すら気づいていない遺言だったのかもしれない、と思った。
私たち家族は、父が不在の状態に慣れていたから、日々のルーティンが変わったりはしなかった。ただ思った、いつか帰ってくる不在と、もう帰ってこない不在とでは、こんなにも感じ方が違うのかと。
それでも父の満月は、亡くなるには早すぎたと嘆く私たちを慰めてくれた。
それから10年余が経った。弟や私の子供たちは誰も「おじいちゃん」と会ったことはないが、「きっとおじいちゃんなら○○って言うよね」と話す。
弟の仕事への取組み方、物事への捉え方に、確かに父を感じる。
そして今夜も光る満月が、子供を寝かしつけた後に勉強する私を見守っている。
栗原 佑奈(5) 神奈川県
わたしのおとうさんはかっこよくて、おもしろいです。おとうさんのすきなところは、ふさふさのあたまのてっぺんです。いつも、だっこやおんぶやかたぐるまをしてくれるときにみています。わたしはおとうさんのつむじをさわるのがすきです。つむじはざらざらしていてきもちがいいです。
おとうさんは、まいにちうでたてふせをしています。しごとでつかれているひでも、まいにちつづけてがんばっています。おとうさんに、どうしてうでたてふせをしているのかきいてみたら、わたしがしょうがくせいになってもだっこできるようにうでをきたえているのだそうです。
うれしいな。ありがとう。わたしが90さいになってもだっこしてください。いつもだっこしてくれてありがとう。おとうさんのだっことつむじがだいすきです。
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
西浦 星成(5) 徳島県
ぼくのパパはとってもやさしいよ。ヤモリがすきなぼく。よるになるとパパとのヤモリさがしがはじまる。パパはどんなにつかれていても、あめのひいがいはぜったいいってくれるんだ。かいちゅうでんとうをにぎりしめて、しろいかべをつぎからつぎにてらしていく。
あるひ、かべのたかいところにかわいいヤモリがいたよ。パパはいえからながいながいはしごをもってきた。
「パパがんばって。」
ぼくはおうえんする。パパはくらいよるのなかはしごをのぼる。
「やったあ。もうとれる。」
ぼくがそういったとき、パパのうごきがとまった。
「パパ、ヤモリさわれんのわすれとった。」
パパがさけんだ。パパはヤモリをさわれない。さわれないけど、ぼくがヤモリをすきだからいっしょうけんめいさがしてくれていたんだよ。ヤモリはどこかにいっちゃった。でもぼくはかなしくなかったよ。だってね、パパとのヤモリさがしはとってもたのしいから。あしたもあさってもそのつぎもパパとのヤモリさがしはおわらない。パパいつもありがとう。
岸本 一花(17) 愛知県
私は父が好きである。
どれくらい好きかと言うと、父が好きなところについて本が数冊書けてしまうくらいである。
父の好い所を挙げたらキリがない。
布団を被らずに寝てしまったときに布団をかけてくれるところ。麦茶が無くなりそうになったら沸かしておいてくれるところ。それから、おひるごはんが素麺のときに庭から大葉を摘んできて切ってくれるところも。
それから・・・。
父は天然である。
病院に連れて行ってもらったときには、診察用紙に「痛」の文字が書けなくて結局私が書いたし、彩り(いろどり)寿司を「あやりずし」と読んでいた。
従姉妹の結婚式で素晴らしいスピーチをしていた禿げているおじさんがいた。スピーチの後に父は
「いやあー!さっきのスピーチ良かったですー!」
と話しかけに行った。違う禿げている人に。そんな父の額は光っている。
この前は「この世界の片隅に」を「この片隅の隅に」と言っていた。どれだけ隅に行くんだよ。すみっコぐらしかよ。
父は寡黙である。
寡黙なおかげか「こだわりが強い人風」に見えるが実際はそんなことはない。
コーヒーは豆から挽きます、みたいな顔をしているが、毎朝インスタントの安いやつで済ませている。
そんな父はお酒を飲んではじめて普通の人と同じくらい喋るようになる。といってもそれはとても珍しいことで月に一回あるか無いか程度だ。
出来上がっている父は非常に珍しい。よく笑うし、面白いことも言う。たまにしつこく絡んでくるが、私はそんな父も新鮮で嫌いではない。
酒はたまに飲むがタバコは吸っていない。厳密に言うと前までは吸っていた。健康に良くないのとお金がかかるから辞めて欲しいと思う反面、たばこを吸っている父をかっこいいと思う気持ちもあった。
ちびまる子ちゃんの話にまるちゃんがタバコを吸う父ヒロシのために灰皿を作るという話がある。まるちゃんがヒロシのことをかっこいいと思うように、私もまた父のことをかっこいいと思っていたのだ。
そしてこれは喫煙者がみんな、だとかタバコの銘柄が関係しているという訳ではない。
父だから当時百九十円の「わかば」でもかっこよく見えたのだ。
当時小学生だった私は体に悪いとわかっていたけれどタバコを吸っている父のそばによく行って、学校であった話などを一方的にしたものだ。父は寡黙な代わりに聞き上手なのだ。そんな訳で禁煙することになったときは嬉しい気持ちと寂しい気持ちが入り交じった。
そして何より、父といると安心する。
父は平日休みで、学校が終わって帰ると父がいる日がある。
特に何かする訳では無い。でも、無性に嬉しくなる。
私が不登校になったとき、何もかもが信じられなくなってみんなが敵だと思っていたとき、父はなにも言わなかった。その代わりに私を優しく抱きしめてくれた。愛情を伝えるのに言葉なんて要らなかった。
私は父に愛されているのだと分かった。
十七の娘がこんなにも父を愛しているのは、父も私を愛してくれているからである。
素敵な父からの愛情を存分に受けて育った私は本当に幸せだと思う。
この作文も所謂父へのラブレターだと思う。恥ずかしいからとても見せられないが。
そんな父も定年まであと二年である。あんなにかっこいい五十八歳は多分、父とジョニー・デップしかいない。
この前母に
「結婚相手を見つけるならパパよりも素敵な人じゃないと認めないからね。」
と言われたが、恐らく一生見つからないだろう。今のところジョニーデップと結婚するしか策はない。
もちろん父とは結婚できないので本屋やスーパーに二人で出かけるときに助手席に座って束の間のデート気分を味わうことにしている。
思い出した。車を発車するときにいつも
「出発するよ?いい?」
と確認してくれるところも好きである。
こんな風に友達などに言うと大半が苦笑いして
「素敵なお父さんで良かったね。」
と苦し紛れに言葉を紡ぐ。無理はない。
今こうやって文章を書いていて自分で自分に引いている節があるからだ。
しかし、こんなに父の良いところを知っているのは私と母だけだ。
どれか一つについて書くなんてとてもできない。全部大好きなのだ。
これからも父というかけがえのない存在を大切にしていきたいし、父の大好きなところをもっと見つけていきたいと思う。
青野 敏子(33) 東京都
小学生の頃、私は顔が大きくてお父さんにそっくりなことが嫌で、お母さんに「なんでもっとハンサムな人と結婚しなかったの!?」と怒ったことがありました。お母さんは、
「そうだよね、きっと大きくなったらわかるわよ。」と微笑みました。
「分かるわけない。」そう思って過ごしてきました。
中学の頃は、お父さんと同じ空間にいることも嫌で舌打ちしたり「キモイ」と暴言を吐いていた私に「ははははは!」と大笑いされ逆にイライラしました。
高校一年生の夏、一晩で髪を金色に染め、ピアスをあけた私に父は、いつもと全く変わらない反応で「そうかそうか」と笑っていましたが、感想くらい言ってよと、怒りを逆なでされました。
大学入学に際して一人暮らしをしたいと懇願したときは、お母さんには反対されたけれど、お父さんは少し考えてから「自分で決めたことなら頑張ってね!」と送り出してくれました。
私が仕事に忙殺され、うっかりどこかに自転車を置いてきて無くしてしまったことがありました。その時、激怒するお母さんの横でお父さんは「地球上のどこかにあるはずだから大丈夫だよ。」とにっこり言いました。
私は結婚して母になりました。そこで気がついたことがあります。太陽のようなお母さんのお陰で家族が成り立っていると思っていたけれど、それは少し違っていたようです。お父さんという「大空」があって初めて、太陽のように明るいお母さんも私達こどもも平和に過ごせるのだと思います。そして今、私はお父さんにとても良く似た旦那さんの
「大空」のもとで明るく過ごすことができています。私のお父さんでいてくれてありがとうございます。お父さんそっくりの自分の顔も大好きです。
井口 泰子(70) 神奈川県
父が九十四歳で亡くなって、二年になる。
父は八十七歳の時、癌になり、少しずつ体が弱っていった。しかし、杖をつき、敢えて外に出た。足腰を鍛えたかったのだ。外に出て、自分に刺激を与えたかったのだ。体は九十度に曲がっていたが、小さい歩幅で脇目も振らずに歩いた。やせ細った小さい体で、睨むように前を向き、人を寄せ付けない厳しさが、体中を貫いていた。
ある日、父と歩いていると、車が止まり、
「お送りしましょうか。」
と言ってくれた人がいた。父と私は、
「歩く練習をしているので」と丁寧に断った。
厚意に対しては礼を尽くす父であったが、この時は複雑だった。前向きに取り組んでいるのに、弱々しい老人に見られたことが、悔しかったのだ。
癌と闘いながらも、父は、新聞を丹念に読み、時には俳句・川柳を投稿した。掲載されると、本当に嬉しそうだった。好きということもあったが、句作を続けることが、自分を律することに繋がると考えていた。
九十歳を過ぎると、父は以前にも増して自分を鼓舞するようになった。
「がんばるしかない。諦めたら、そこで終わりだ。」
「一センチでも一ミリでもいい。前に進め。」
何度も声に出して、自分に言い聞かせていた。会社員時代のように、自分を奮い立たせていたのだ。私は、父の真剣さに度肝を抜かれた。
癌・老いに負けたくない。僅かでも前に進もうと必死だった。敵は、弱音を吐く父自身であった。自分を鼓舞しなければ、受け身の生活になってしまう。たった一歩の譲歩が、それまで積み上げたものを、駄目にしてしまうことを、父は、分かっていた。
亡くなる半年程前から、着替えに時間が掛かるようになった。しかし家族の手を借りず、一時間近く早く起き、自分で着替えた。私は、父の意思の強さに圧倒された。
ベッドにいる時間が増えても、家族の一人ひとりの動きをよく見ていた。そして言うべきことは、厳然たる態度で家族に伝えた。感謝を言うことはあっても、卑屈になることはなかった。
父は最期まで自分の生き方を貫いた。身を以て、私に生き方を示してくれた。凛とした人生だった。
私が、八十歳・九十歳になった時、父のように生きるのは、容易ではない。でも、それは、私の義務だと思う。なぜなら、父の深い思いを全く理解せず、冷たく接した時が少なくなかったからだ。父の悲しい眼差しが忘れられない。しかし、父は、長い目で私を見守ってくれた。信じてくれた。父に心底、謝りたい。
私の残りの人生を、父のように生きると心に決めた。人に頼らず、自分を叱咤激励して生きる。自分を絶対に諦めない。私にとって、これ以上も、これ以外の人生もあり得ない。私にできる、父への最後の詫びであり、感謝である。
父は、私の命の中にいる。
三宮 和子(21) 神奈川県
今まで出会った人の中でいちばんやさしい人。料理がとっても上手な人。意外と背が高くて私とちょっと顔が似てるかっこいい人。雑学をたくさん知っている人。カメラを向けると変顔しかしない人。典型的な親父ギャグで私を笑わしてくれる人。野球が好きな人。洗濯物をたたむのが上手な人。これが、私の知っている、私のお父さんです。
お父さんは仕事人間で、私が小さいときからたまにしか家に帰ってこなくて、一年に一・二回くらい一緒に遊びに行ける、私が心待ちにする日がありました。私が成長するにつれてその機会もどんどん減っていき、いつのまにか家ではお父さんの姿を見かけなくなりました。それでも私は、たとえ離れていても、お父さんはお母さんのこと、お母さんはお父さんのこと、ずっとずっと大好きなことは永遠に変わらないと信じていました。
でも、私は末っ子だったのもあったのか、何にも知りませんでした。気付いたら、お父さんとお母さんの離婚が決まっていました。私の中で永遠だと信じていたものが、永遠ではなくなってしまったように感じて、心にぽっかりと大きな穴があいてしまったようでした。これが事実だとすぐには受け入れられなかったし、本当は受け入れたくありませんでした。
離婚から何日か後、お父さんの誕生日がありました。おめでとうのメッセージを送るか少しだけ迷ってしまいました。でも、自分のお父さんに“誕生日おめでとう”を言わない理由なんてある訳ないと思って、例年通りメッセージを送りました。次の日の朝、目が覚めるとお父さんから返信が来ていました。そこには「だめな父でごめんね、生まれてくれてありがとう」と書いてありました。これを見たとき、これが現実なんだ、と初めて実感が沸いたような気がしました。
そして今、離婚から約一年たちました。お父さんとは一年以上会っていません。それでも、お父さんが私の中から消える瞬間はなくて、今でも至るところでお父さんの影を探してしまいます。少しでもお父さんの姿がよぎるものを感じたりすると、目頭がじんわりと熱くなります。
ずっとお父さんのことを考えていて、分かったことが一つだけあります。それは、私はお父さんのことが本当に大好きだということです。頭で考えているよりも、心はずっとずっとお父さんのことが大好きなようです。幻のように感じるときもある昔のお父さんも、今のお父さんも、そしてこれから先のお父さんも、永遠に大好きです。
そんな今の目標は、大好きなお父さんに誇りに思ってもらえるような娘になることです。一生懸命努力して、お父さんに幸せな姿を見せてあげたいし、お父さんも幸せにしてあげたいです。だから、私が自信をもって一人前になれたら、お父さんに会いに行こうと思います。すごく緊張してしまう気がするし、きちんと自分の言葉で伝えられるか自信はないけれど、絶対に会いに行って“私をうんで、育ててくれてありがとう”と感謝を伝えたいです。
今回は、今の私の気持ちをどうしても消したくなくて、形に残しておきたくて、この作文を書きました。お父さん、いつか会える日まで、どうかお元気でいてください。そして、お父さんは永遠に私のお父さんです。
心からのありがとうと大好きを込めて。
石本 恵里香(29) 福岡県
小さい頃、私は父と一緒によく走っていた。車のほとんど通らない、新鮮な空気をいっぱい吸って、田舎の一本道を父の背中を追って走っていた。マラソン大会にも一緒に出た。ゴールは遠いのに、いつも父は決まって「あと少しだ。」そう言ってあきらめそうになる私を引っ張ってくれた。
短距離は苦手、球技も苦手、でも長距離は今でも大好き。その始まりはきっと小さい頃の父とのランニングなのだと思う。大人になっても走っていると言うと、そんなきついこと、何で今もやっているの、と聞かれることが多い。実家を離れ、一人暮らしをして、仕事をし、父と連絡を取ることは何かあったとき以外はほとんどない。だけど、そんな日常の中で、私は一人ランニングをしながら、ふとした瞬間に小さい頃、一緒に走った父との時間を思い出す。
社会人になって、父と同じマラソン大会に出た。タイムとか結果とかそういうのより、父と一緒に走る喜びとゴールした達成感を味わえたのが、何より嬉しかった。疲れ切った身体とはよそに、心は日常では感じられないくらいの栄養を与えられたように元気になった。一緒に撮った写真には満面の笑みを浮かべて写る父の姿があった。今、マラソン大会は軒並み中止になっていて、以前のような世の中はすっかりどこかへ行ってしまった。けれど、走ろうという気持ちとランニングシューズさえあれば、私はいつだって走ることができる。一歩踏み出せば、今日その瞬間しか味わえない外の空気と自分の移り行く気持ちを味わえる。
どんなにつらいことがあっても、私にはランニングというぶれない軸がある。それを教えてくれた父には、面と向かっては恥ずかしくて言えない心からのありがとうを今日も実家から離れた土地で私はつぶやきながら、ランニングシューズに足を入れる。
朝見 煌仁(8) 神奈川県
ぼくは、生まれた時からパパがいなくて、ママとくらしてきた。生まれた時からずっとパパがいなくてさびしかった。たまにおばあちゃんが来て一緒にいた。それでも、僕はさびしい気もちは変わらなかった。そして4才になったある日毎週金曜日に行っていたやき鳥屋で奇跡が起こった。僕が隣にすわっていた男の人を指でつんつんしてみた。そしたら、ふり向いてくれた。それを何回もやってみると、なんとママとその男の人がけっこんする事になった。僕はパパがいなかったので、その男の人とママがけっこんするのをすごくよろこんだ。それから7才になって僕はパパから手紙をもらった。手紙をよんだら、僕がお勉強をしている姿を見てパパも頑張ろうと書いてあった。僕はそれを読んでびっくりした。次は僕がパパが頑張っている姿を見習おうと思う。
僕のパパになってくれて有難う。いつまでも僕のパパでいてね。
いつかパパみたいな大きなせ中になりたいな。
吉田 朝美(21) 大阪府
働かない父に苦労ばかりかけられてきた。躁うつ病のせいもあったのか、頭に血が上ると制御が効かなくなるのでどこへ行っても仕事が続かない。調子の悪い時は被害妄想が激しくなり、母や私たち兄弟に当たり散らした。普段は優しい父が突然目の色を変えて暴走する姿は、何度見ても悲しかった。不安定な父は昔から精神病院への入院や家出を繰り返していたが、私が十五歳の頃にようやく離婚が成立し、完全に家からいなくなった。
父がいなくなると、母は私に父の愚痴をよくこぼした。離婚は父に原因があることは明らかだったが、事実を知れば知るほど父のことが嫌いになってしまう自分が怖かった。家族にひどい苦労を負わせた父を恨みつつも、一人ぼっちになってしまった父を心配する気持ちがあったからだろう。穏やかな状態の父を忘れることはできなかった。
連絡をとることは、母から禁止されていたが、父からは時折メッセージが届いた。聞いてもいないのに近況を報告してきたり、話したくもないのに学校のことをきいてきたり。毎回一度は無視しようとしたが、しばらくすりと決まって父の寂しそうな背中が頭に浮かんできた。嫌いになったはずの父を気にかけてしまうことが悔しかったので、結局なるべくそっけなく返信した。五年ほどそんな状態が続いた。
しかし、私が二十一歳になった大学三回生の夏、突然霧が晴れるように父を嫌う気持ちがなくなった。私が少しだけ大人になったのだろうか。父を恨むことにもはや何の意味もない、と思えるようになったのである。母は、あれから別の人と新たな愛を育み、幾分穏やかになった。姉は結婚して二人の子どもを授かり、兄や弟も好きなことを何だかんだ楽しそうにやっている。私自身は念願の大学で好きな勉強ができて、好きなものと沢山出会い、おまけに心の底から信頼できる男性に出会えた。貧しい一人暮らしを強いられているが、それでも胸を張って幸せだと言える。
父を恨む気持ちがなくなると、突然父と話がしてみたくなった。もう何年もまともに話せていない。これまでに起こったことを一番正直な気持ちで話して、今の私を見て欲しい。もしかすると当てつけだと思われるかもしれない。しかし、私は失われた時間を少し埋めたいだけだ。未だに「またかけっこしような」とメッセージをよこす父である。私のイメージは、小学校の頃で止まっているに違いない。父がいてくれて、私を生んでくれたおかげで今はこんなに幸せに暮らせていることが伝わればいい。そして父も同じように、新たな人生を幸せに歩んでいてほしい。もしもまた会える日が来たら、きっと今までで一番素直に話せるだろう。
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
久家 祥子(33) 福岡県
子どもの頃、私は父の「手」が大好きだった。体格のわりに小さいその手は、指は短く、だけど厚みはたっぷりで、全くもってスマートさの欠片もないダサい手だった。そんなダサさ満点の手だが、ひと目見ると「クリームパン食べたいなぁ」と思わせる力量を持つ愛嬌ある手なのだった。いつもその手は温かくて柔らかくて、私はその手で頭を撫でられると包み込まれている気がして幸せだった。
およそ細かな作業には向かないであろう形体の手を持つ父だが、それが意外にも器用だった。その手にかかればプラモデルはえらくリアルに仕上がっていくし、たこ焼きも食品サンプルか?と思うほど美しい球体になる。家の何かが壊れれば何をしているのか私たちには謎な作業を経てあっという間に直し、美容師でもないのにやたらヘアカットもうまかった。そう、父の手には何もかも不思議と従順なのだった。
子どもの私はそんな何でもこなす父が好きで自慢だった。だって父の手から生み出されるものはいつだって周りを笑顔にしてくれるのだ。まるで魔法の手のように思えた。
大人になるにつれ、父と手を繋いだり、頭を撫でられることは当然減っていった。一人暮らしを始めると顔を合わせる機会すら減った。私は忙しくて心の余裕がなくなり、自分のことで精一杯になっていた。そんなある日。「あ、もう疲れた。ダメだ。実家帰ろう。お父さんとお母さんに会いに行こう」
世知辛い世の中に打ちのめされた私は、ふわふわと実家に帰ることにした。両親は久しぶりに帰って来たふわふわ娘の訪問を喜んでくれた。私ももちろん両親に会えて嬉しかったが、同時にとあることにショックを受けた。「あれ?何だかお父さん、小さくなった?」あんなに大きく思えていた父が小さく見えてくるのは、成長した子どもの『あるある』だろうが、いざ我が身に起きると胸がキューッとなるものだ。いつの間にこんなに時間が経っていたのだろうか?急に時間が貴重なものに思えた。私は何だか久しぶりに父の手をじっくり見たくなった。魔法にかかりたかったのかもしれない。
「ちょっとお父さん、手、見せてよ」
気恥かしさもあったが、勇気を出してそう言った。差し出された父の右手を私は手相を見るかのごとくマジマジと見た。大人になって改めて見つめたその手は何だか見覚えのある手だと思った。いや、見覚えどころか、見飽きる程見ている手にそっくりだ。これは毎日見ている手と一緒じゃないか。私は自分の右手を父に見せた。
「そっくりやんか」
ダサいダサいと思っていた手にいつの間にか私の手はそっくりに成長していたのだった。私は指が短い自分の手が好きではなかったのに、父にそっくりに育ったその手に急に愛着が沸いてきた。こんなに似ているのだから、もしかしたら私の手も、そこから生み出されるもので周りを笑顔にできるんじゃないだろうか?そんな根拠のない自身が沸いてきたのだ。
父の魔法の手には到底及ばないが、きっと私はその魔法をちょっとは引き継いでいるはずだ。何て言ったって、その魔法の手に育てられた私なのだ。『この手から紡がれるものを自信を持って大切にして、周りの人を幸せな気持ちにできるよう頑張りたい』そう思えた。
その第一歩として、まずはこれを一生懸命に書こう。これを読んでくれた人がほっこりした気持ちになってくれたら万々歳だ。
稲森 彩子(22) 大阪府
「しゃあない。」
これは関西弁で「仕方がない」という意味なのだが、この言葉が父の口癖だ。
私はこの言葉が苦手だった。なぜなら、「しゃあない」の一言で片づけられてしまうと、結果は元から決まっていて、どれだけ努力をしても運命は変えられないといわれているような気がするからだ。
『失敗すれば反省をして同じ失敗は繰り返さないように努力するべき』と考えている私にとって「しゃあない」という言葉は、まるで反省の色が無く無責任に聞こえる。
父がこの言葉を口にする度に「反省はしないのか」と憤りさえ感じていた。
18歳の時、私は病気になった。
『神経性無食欲症』いわゆる『拒食症』だ。久しぶりに会った親戚に、「結構体重あるよね。」と言われたのがきっかけだった。身長165cmで体重49kgと決して太っていたわけではなかったとは思うが、その一言が私の胸の深い所まで突き刺さった。
その日以降、お菓子はもちろんのこと肉や卵や乳製品なども、カロリーが高いからという理由で一切口にすることを辞めた。健康的なダイエット方法をきちんと調べてから実践すれば病気になんてならなかったのに、と何度も後悔したが、それはもう後の祭りだ。
結果、3ヵ月で10kgも減量できたのだがその代償として拒食症を患った。痩せても痩せてもまだ痩せたくて、自分は太っていると思い込んでいた。100gでも体重を減らそうと水分すら口にするのも嫌がった。
ついに体重が37kgを切った時、いよいよ母に連れられて病院へ行った。生命の維持も危ういほどの低体重だと告げられ入院する羽目になった。
私は「こんなことになってしまって情けない」と自分を責め続け、「毎日母も一緒に居たのに止めてあげられず母として情けない」と自分を責めていた。
やり場の無い怒りと不安をお互いにぶつけ合い病院内で喧嘩をすることもしょっちゅうあった。
そんな状況でも父は「しゃあない」と言っていた。
私が無謀なダイエットをしたことを責めることもなく、もちろん母を責めることもなく、父自身を責めることもなかった。「しゃあない」以外の言葉は何も言わなかった。
一度、見舞いに来てくれた時も「綺麗な病室やな。ホテルみたいや。」とワハハと笑い、体調を気遣う言葉をかけることもなく「ほな!」と颯爽と帰って行った。わが子が入院しているというのにあまりにも冷たくないか、と不快になり、私はそれ以降父と距離を置くようになってしまった。
退院後も、病状は悪化と良化を繰り返し、なかなか完治には至らなかった。そのもどかしさを私はよく母にぶつけた。
「病気になるくらいなら、ダイエットなんてするんじゃなかった」と。
すると母はニコッと笑い「もうそんな風に言うのは辞めようよ」と言った。
その時初めて、母が教えてくれたことがある。私の入院中にたった一度だけ、母は父の前で「自分は母親失格だ」と泣いたことがあったそうだ。すると父は「もう過ぎたことを後悔してもしゃあない。これからどうしていくか、どう病気と向き合っていくのか考えよう。あの子も病気になりたくてなったわけじゃないし、母親に失格も合格も無いよ。」と言ったそうだ。
泣きじゃくる母を見て「過ぎたことはしゃあない!」と相変わらずワハハと笑っていたらしい。母はその言葉に救われ、やっと前を向くことが出来たと言っていた。
私はその時に初めて、父の「しゃあない」に込められている意味が分かった。反省していないというわけではなく、ただ『後ろは振り向くな』という意味に過ぎなかったのだ。思えば、私が病気になったことに対して、一度も「どうして」と責めなかったのは父だけだった。
また私が家の中でどれだけ当たり散らしても決して怒らなかった。
幼少期のころからそうだ。躾や礼儀には厳しかったが、それ以外の失敗はほとんど「しゃあない」で済まされ、怒られた記憶はあまりない。
そのことに今明で気付かずにいた自分が恥ずかしく、布団の中で一晩中泣いた。
それ以来、私は「もう病気になったのはしゃあない」と自分のことを受け入れて前を向くことにした。病状は、三歩進んで三歩下がるというようなスローペースではあったが徐々に善くなっていった。
今でも、私が小さな事で悩んでいると、父は「しゃあない」と言う。それ以外の言葉は何も言わないし、後になって悩み事は解決したのか、とも聞いてもこない。
でも、もう憤りを感じることは無い。それどころか「しゃあない」と言われると「そっか、しゃあないよね。」と心が軽くなる。
あれほど苦手だった「しゃあない」が今では悩みの種を小さくする魔法の言葉になった。
お父さん。
こんなに素敵な魔法の言葉をずっと言ってくれていたのに、気付かなくてごめんなさい。そして、ありがとう。
森 惇(37) 千葉県
幼い頃の私の記憶には、父が全く登場しない。私が小さい頃は特に忙しく、休み返上で年中飛び回っていたらしい。育児も母に任せっきりだったようで、私は母一人に育てられたといっても過言ではなかった。私はそれが当然だと思っていたし、そのことに不満はなかった。ただ、もちろん父との会話はほとんど無く、ごく稀に家に帰ってくる父の存在は、父親というよりたまに会う親戚のおじさんに近かった。私と父の関係は、そのまま変わることなく時が流れていった。
そうして私が思春期に入った頃のある日、母と私は口論になった。食事の味付けが薄いとかそういう些細な話だった。そこに、たまたま居合わせた父が仲裁に入り、なぜか結局、「よし、じゃあ父さんが作ろう」ということになった。
その頃の父は、長い単身赴任中だった。この日も、たまたま帰ってきただけだった。父が突然私と母の間に割って入ってきたことにも驚いたが、そもそも父の料理を食べたことがない私は、どんな料理になるのか半信半疑だった。だが、そんな私の思いをよそに、父は冷蔵庫からパッパと食材を取り出して手際よく料理をしていった。
「できたぞー!」
十分ほどでフライパンを持った父が現れ、私の皿に盛り始めた。ニンニクの効いた良い香りがするチャーハンだった。しかし、父のチャーハンには尋常ではないほどの野菜が入っていた。その量や見た目に圧倒されてちょっと気が引けたが、父に勧められて一口食べると驚いた。
「うまい!」
思わず声を上げた。野菜は多いが、バターがたっぷり入って私好みの濃厚な味。食べ盛りの私にはうってつけだった。なんだ、めちゃくちゃ美味しいじゃないか!私は一心不乱に食べ続け、あっという間に平らげてしまった。私が食べ続けている間、父は、「うまいか?どんどん食え。お父さんは料理が上手なんだぞ」と、誇らしげに笑っていた。
そういえば、健康に気遣う父はいつも外食をせず、休日に作り置きしたものを毎晩食べていると母が言っていた。今思えば、単身赴任先で一人で食べている自分の料理を思春期の息子が喜んで食べていることは、父にとってはよほど嬉しいことだったのだろう。
以来、あのチャーハンは私の好物となり、父が帰ってくるたびに頼むようになった。父も本当は家でゆっくりしたかったかもしれないが、毎回快く作ってくれた。そして何より、私と父の会話もたくさん生まれ始めた。思春期で母との会話が少なくなっていた私は、以外にも料理という形で、父との関係が新たに築かれていった。
あれから二十年以上の月日が経つ。
生涯現役で働いていた父が突然他界し、バタバタしているうちに三周忌となった。まだ父の死が実感できず、「チャーハン作るか?」と父が書斎からひょいと顔を出してきそうな錯覚に陥る。キッチンを見れば、父が元気にチャーハンを作ってくれた後ろ姿を思い出し、切なくて歯痒くて涙が溢れてくる。だが、涙を拭いて前を向こう。親子を結び付けてくれたあのチャーハンや破顔する父の姿は、これからも私の中に永遠に生き続けるのだから。
岩本 香菜(37) 大分県
私の父はこの世にはいない。父が亡くなったのは平成26年、今から6年前。それは私が妊娠7ヶ月のことだった。
父と母の待望の一人目として生まれてきた私は溺愛されて育った。父は遊びに夢中になる私を怒りもせず、それどころか茶碗を持ち追いかけながら食べさせてくれていた。鼻が詰まっている時は、自らの口で鼻水を吸い込む程。目の中に入れても痛くない、とはこのことを言うのではないだろうか。
ただ、そんな父は時間厳守の自衛官。物心ついた頃から門限五時のルールができていた。私は、友だちと遊びの誘惑に負け、度々門限を破った。五時に仕事が終わると直帰する父。父の自転車を恐る恐る確認し、なければセーフ。定位置にあるとアウト。ソワソワしながら帰っていたなぁ、鍵をかけられしばらく家に入れてもらえず、玄関の前で泣いていたなと、あの頃が懐かしく思い出される。
優しくもあり、厳しくもある父。そんな父に対し、それなりに反抗期もあったが、仕事の関係で単身赴任となったこともあり、適度な距離の父娘の関係は良好だった。
そんな父は私たち家族に大きな秘密があったのだ。それは、私が結婚してすぐの夏の日、あっけなくバレた。胃の再検査を二年間も放置していたのだ。
「今年は三年目(三回引っかかった)から、仕方なく病院に行ってやるんじゃ」と、なぜか上から目線で言っていた父。
そこで発覚したのが胃癌。ステージ4。
しかも、胃癌の中でも最も稀なAFP産生胃癌という予後の悪いものだったのだ。余命一年の宣告だった。奇しくも、診断が下りたのは、私の初めての結婚記念日だった。主人とご飯でも食べに行こうかと言っていた矢先、青天の霹靂であった。
父は病院で言い放った。
「自然に任せる。悪あがきはしない」と。その時はまだ、痛みなど自覚症状もないので、しばらくは家で過ごすことに決めたのだった。
その矢先、私の妊娠が分かった。父の生きる希望が出来たと私はとても嬉しかった。
「孫が出来るんやな」と、噛み締めるように言った父。
それから間もなく私は悪阻が始まった。私は実家に帰ることに決めた。それは、もしかしたら、父と過ごす最後になるかもしれないという思いからでもあった。
季節が少しずつ変わり、もうすっかり寒くなった冬の日、父は胃や腰の痛みが出て寝込むようになっていた。体も徐々に小さくなり、体重も減ってきているのは見た目でも明らかだった。そんなある日、私が悪阻で寝込んでいるのを見て父が言った。
「お前の苦しみや痛みを全部お父さんが取り除いてやりたい。お父さんが死んだ時に、悪いもの全部持っていってやるからな」と。
泣き言を決して言わない父なのに、そんな父でさえ痛みに苦しみ過酷な状態なのに、悪阻でキツイと漏らす娘に寄り添ってくれるのかと、父にバレないように炬燵にもぐり声を押し殺して静かに泣いた。父の愛と優しさを感じ、父の子で良かったと心から思えた。
私の悪阻も落ち着いた頃、父は入院することになった。限られた命をつなぐための胃のバイパス手術だった。手術は成功し、退院という直前、父は脳梗塞を起こしたのだ。
幸い処置が早く命に別状はなかったものの、左半身に麻痺が残った。
私は仕事をしている母の代わりに、毎日お見舞いに行った。一人で食事をすることも難しく、ある日ご飯を食べさせていたら、父の目から大粒の涙が溢れた。父の涙は私の結婚式でさえ見たことがなく、初めて見たのであまりにも衝撃で、私も気がついたら涙がこぼれた。桜のきれいな時期だった。
その頃、子どもの性別が男の子だと分かった。父は男の子が欲しく、もし産まれたら名前は孝治にするとまで言っていた程。だが、三姉妹。父の夢は叶わなかった。だからこそ孫が男の子なら絶対に喜んでくれると思っていた。父は、
「ヤロウか」と一言、その後窓の外をじっと眺めていた。
父に報告して何日か経ったある日、病院から意識不明だと連絡があった。その時はなんとか持ち堪えたが、大部屋から個室へと部屋が変わった。それは、そろそろ覚悟して下さいという意味だと受け入れた。
会話をするのも苦しそうで、筆談へ。達筆だった父が、筆圧も弱く、ミミズのような字になるのが、なんだかすごく切なかった。
父の涙を見た一ヶ月後、父は旅立った。この日は父と母の33回目の結婚記念日。手作りのアルバムを病室で製作し、夜11時頃出来上がったのだ。アルバムを枕元に置き、耳元でおめでとうと言い残し、病院を出てすぐのことだった。母は
「あと15分経ったら日付けが変わってたのに」と。父はどうしてもこの日が良かったのかとさえ思ってしまった。
四十九日を終え、父の死から77日後、緊急帝王切開で息子が生まれた。普通分娩で産みたかったが、母子共に危険と判断され、帝王切開となったのだ。ただ、私の子宮にあったチョコレート嚢胞も出産と一緒に手術で吸い取ってくれたと後に聞いた。その際、私と息子の命もだが、私の身体の悪いものを全部持っていってくれたのではないか、と父をふと思い出したのだ。
小さく産まれた息子も耳だけは誰にも負けない程大きかった。実は父も福耳。生前、得意げに言っていた福耳自慢。父が息子に残したプレゼントだと、私は密かに思っている。孝治ではないが、私はどうしても父の字をつけたいと夫に話し、夫も快く承諾してくれたので、治という字をもらい、恵(けい)治(じ)と名付けた。
そんな息子も6歳になり、弟も出来た。当たり前のような幸せな家族ができた。
ただ、日常の幸せは忙しい日々に追われる中で忘れがちだ。でも、決して人の死はどんなに忙しくても忘れることはできない。
毎日、私は寝る前に息子の耳を見ると思い出す。父は今頃何をしているのかな、もし生きていたら、、、などと。神様や仏様よりも、私は空で見守ってくれているのは父ではないか、と思ってしまう。
そして、父は、日常の幸せを忘れないことを、息子の福耳を通して教えてくれている気がするのだ。
中野 民子(45) 大阪府
「あぁ、また時計の時間がずれてきたなぁ。」
先日、時計の電池を交換したついでに時間を合わせたばかりなのに、また時間が狂っている。洗面所に置かれた時計は早くなり、部屋の掛け時計は遅くなる。この時計は時間が何分狂っていると頭で計算しながら、今日も朝の支度に追われる。
そんな時に思い出す父の言葉。
「この時計は1秒たりとも狂わない。」
父は嬉しそうにその懐中時計を幼い私に自慢した。鉄道会社に勤めていた父は時間を忠実に守る人だったようだ。人付き合いも良く、職場の仲間も沢山いたようだ。
子供だった私との約束が守られることは、ほとんどなかったのだけど。
私はその時計がどうしても欲しくて、父に何度かお願いしてみたが、会社からの大切な記念品だと、いつも断られた。
子供だった私も社会人になり、子供にだけ与えられたゆっくりとした時の流れを感じることもなくなった。目まぐるしく日々が過ぎていく中、突然私の手元にその時計がやってきた。父が急死し、部屋を片付けている時にその時計を見つけたのだ。あまりに突然のことで、寝ても覚めても父の死が夢のように感じられた数日だったが、この時計を見て父はこの世にいないことを現実として感じた。狂わないはずの時計は止まっていたのだ。時間が狂わなかったのは、毎日父が時間を合わせ、手入れをしていたからだった。
父が働く鉄道会社では、少しの時間の狂いも許されず、毎日時計が狂わないよう確認を怠らなかったのだと、この時知った。
子供だった私には、決して友達に自慢できる父ではなかったが、大人になった私なら少しは父の気持ちが理解できるだろうか。父の譲れないこだわりは何だったのだろう。そんなことをふと考えながら、また今日も時間に追われる朝がくる。
田仲 浩子(58) 神奈川県
父と話をしているとき、何かの拍子で写真の話題となった。私は自分の子どもの頃の写真の枚数が、姉のものに比べて半数以下であることを思いだした。それで、当時のカメラマン役だった父に、
「お姉ちゃんの写真はたくさんあるのに、私のは少ないね」
と言ってみた。私としては父が、
「それは悪かったなぁ。でも、おまえもお姉ちゃんと同じようにかわいかったし、同じように大切な子どもだったんだよ」
と言ってくれるものと思っていた。
ところが、父は次のように言ったのだった。
「うん。お姉ちゃんは一人目の子どもだったから、写真もたくさん撮ったけれど、おまえはもう二人目の子どもだったから、写真を撮るのも飽きたんだ」。
あまりの予想外の返答に、私は思わずのけぞってしまった。しかし、のけぞった体を元の位置に戻す頃には、笑いがこみあげてきた。
と同時に、
1.「飽きたのなら仕方がないか…」という思いと、
2.「それにしても、『飽きた』なんて、よく言えるなぁ」という思いと、
3.「父がそんなことを言えるくらいには、私も大人になったんだなぁ」
という思いが、心の中で錯綜した。そしてこのとき、父は全く意識していなかったと思うが、私は次のことを学んだ。それは、
「思ったことは、言葉にしてもよい」
ということだった。
もちろん、これは相手との人間関係にもよるし、状況によっても違ってくる。しかし当時、「こんなことを言ったら、相手の人を傷つけたり、いやな想いをさせるかな」ということが気になって、なかなか思ったことを言えない自分がいた。だからなのかもしれないが、本心を言いあえる人間関係はおもしろいし、基本的には相手を信頼しているから言えることだし、その場では言われた方はちょっと驚くかもしれないが、かえってそこに、新しい発見や笑いが生まれて、結果として二人の人間関係がより深まる、ということもある、と思えた。
もっとも父は、自分が発した「飽きたんだ」の一言で、娘がそこから人生の教訓じみたことを学びとってしまうことなどは、知るよしもない。そのことがおかしくなって、再び私は一人で笑った。
父との会話は、次第に写真からカメラの話になっていった。父は姉が生まれたとき、カメラがどうしても欲しくなり、職場の先輩から中古のカメラを買ったこと。そして、そのカメラは当時としてはとてもいいもので、はじめてそのカメラが自分のものになったときは、本当にうれしかった、ということを、ニコニコしながら語った。
私も、そのカメラのことは、よく覚えている。とてもがっちりとしたこげ茶色の革のカバーがついていて、5,6歳頃の私の目には、きりんの顔ほどある大きなカメラに思われた。ふだんはよく、床の間の上に置かれてあった。しかし、いつの頃からか見かけなくなり、気がついたときには、もうそこにはなかった。
私はなつかしくなって、父に聞いてみた。
「お父さん、あのカメラ、まだあるの?」
すると父は、どこか遠くを見るような目になって、
「あるよ。おまえたちを写したカメラだと思うと、捨てられなくてな」
と言った。
さっきまでは、好き勝手なことを言っている父に思えていた。しかし、この言葉を聞いたとき、「父は、私の写真を撮ることには飽きてしまったかもしれないが、私たちを愛することには、飽きないでいてくれたのだ」と思った。
こんな話を父としてから、早五年がたった。今はもう、実家には誰も住んでいない。しかし、父のカメラは私がもらい、今、そのカメラは、私の家の本棚に置かれている。そのカメラを見ていると、ひな壇の前で、「もっと笑いなさい」としかられながら写真を撮られたこと、幼稚園の入園式の朝早く、まだ眠たいのに起こされて、ふきげんな顔のまま、記念写真を撮られたこと、フイルムがうまく巻きとられず、寒い中、ずっと立ったまま待たされたことなどなど、今となっては懐かしい思い出が、父の姿と共によみがえる。
久しぶりにカメラを手にとると、思っていたよりずっと重く感じられた。この重さが、私にとっての父なのかもしれない。そして、カメラのむこうにいた父につぶやいてみた。
「お父さん、これからもたまにでいいから、私の写真、取ってね。お父さんのいるところからもよく見えるように、これからはとびっきり素敵な笑顔、お父さんに見せるから」と。
吉田 愛央(17) 愛媛県
看護師だった母は夜勤も多く、思い出の中の私はいつも父に肩車されていた。肩車されて見える景色は、父が見ている景色と同じように感じた。小学生になると、父の帰りは遅くなり、夕飯を一緒に食べる回数が少しずつ減った。それでも、休日になるといろんなところに連れて行ってくれた。運転する父の隣が私にとっては特等席で、目的地まで父が私の話をずっと聞いてくれるから、私は眠たくてもしゃべり続けた。
中学生になり、部活動で忙しくなると、父とは生活がすれ違った。たまに顔を合わせても、何を話していいのかわからず、何となく父との時間が気まずくなっていった。
高校一年生の三者面談で、予定日が休日だということもあり、母は父に行かないかと聞いたらしい。しかし、父は断った。それが妙に突き放されたように感じ、その時初めて父との間に大きな壁ができてしまったことを実感した。
私は、テスト期間に入り、夜遅くまで勉強する日々が数日続いた。のどが渇いて、リビングに行くと、父が帰ってきていた。
「おかえり。」
「ただいま。」
それだけの会話をして、私は冷蔵庫を開けた。
「何か作るか。」
お腹がすいていたわけではなかったが、私は何となく、「うん。」と返事をした。久しぶりに食べた父の手料理はインスタントラーメンだった。
「どうして三者面談、断ったん?」
「作ってくれてありがとう。」や「おいしい。」の言葉は出さなかった。
「お父さんが行ったら、嫌だろう。」
「なんで?」
「傷のこと、友達に言われるかもしれない。」父の顔には大きな傷があった。父が子供のころにできたものらしく、見慣れている私からすれば何でもなかった。それでも、小さい時から、友達には父の顔の傷について問われたことは何度かあった。しかし、それが嫌だと感じたことは今まで一度もなかった。それより、父がそのことを気にしていたとは思いもしなかった。
「そんなこと、気にしないよ。」
私の言葉に特に父が反応することはなかったが、それからというもの、自分の出勤時間を少し早めて、毎朝のように私を学校まで送ってくれるようになった。私の席は変わらず父の隣だった。学校までの数十分の道のりで私たちがこれといった話をすることはなかった。しかし、父は毎朝私を学校に送るために少し遠回りをしてくれる。それが不器用な父なりの優しさなのだろうとうれしかったりもする。今の私には、直接こんなこと言えないけれど、卒業するころには、自分の言葉でちゃんと伝えたい。
「いつもありがとう。」
笹村 弥生(20) 山口県
私は、優しい父が大好きです。私が幼い頃沢山抱っ子やおんぶや肩車をしてくれたからです。人見知りなので外ではおとなしいですが、家に帰ると思い切り笑い合っていました。仕事で疲れていても遊んでくれてありがとう。
私は、頑張る父が大好きです。私が小学生の頃、牛飼いを仕事に足しました。農家としての幅が拡がり、家に帰ってくる時間が遅くなっていました。家族の為に必死に働いてくれてありがとう。
私は、怒ってくれる父が大好きです。私が中学生の頃、不登校にはなるなと教えてくれたお陰で、特別支援学級のみんなと出会うことができました。あきらめなくて良かったと感じさせてくれてありがとう。
私は、陰で見守ってくれる父が大好きです。私が高校生の頃、本や大学で心理学を学び始め、心の病について理解を深めようとしてくれました。高校生活が辛くなったら通信制を考えてもいいと声をかけてくれてありがとう。
私は、我慢できる父も大好きです。私が保育短大生の頃、もう少し続けてみろと背中を押してくれました。授業を受け続けていくうち、親の立場が徐々に理解できるようになっていきました。自分の子どもが苦しむ姿を見る親の辛さに気付かせてくれてありがとう。
私は、父を尊敬しています。今まで私をここまで育ててくれたからです。仕事は挫折してばかりですが、父のように弱音を吐かず、好きなこと・やりたいことに向かって強く生きていきたいと思います。
父さん、人から信頼を得るって難しいけど、私も農業を通して沢山のあたたかい人と繋がりたいです。これからもまだまだ色々なことを私に伝えてください。そのかっこいい背中で、父さんらしく。
「お父さんへの作文コンクール」
入賞作品発表!
※画像をクリックすると作品が開きます
石田 桂子(40) 福岡県
幼い頃の私が、楽しみにしていたこと。
お昼ごろ、家の中でママに遊んでもらっていると、家の外からクラクションが、
「ブブブ。ブブブ。」
と、鳴ることが、しばしばありました。
「わあい。パパだぁ。」
パパが、仕事の途中で、トラックを家に横づけして、
(むかえにきたよ)
と、合図をしているのです。
私のパパは、若い頃、トラックの運転手でした。私はパパのトラックを『お二階バス』と、呼んでいました。ママに抱かれて、助手席に座って観る景色は、パパに肩車してもらうのよりも、もっと見晴らしが、よかったからです。バスの二階にいるように・・・・・・。
「よかったね。パパが一緒に、お仕事に、いこうねって」
ママがにっこり笑います。
トラックの助手席の階段は、子供の私には高すぎるので、ママが私をだっこして、運転席から、手をのばしているパパに渡してくれていました。
「おお。いい子にしてたか?うれしいか?」
「うん。パパ。ありがとう」
助手席から見るパパは、とても格好よく見えました。
「ほら、いくぞ。」パパが、言います。
「はあい。しゅっぱあつ!!」私もいいます。
トラックはゆっくり動き出しました。
「すごぉい。」
「そうか。すごいか」
パパとママが、顔を見合わせて笑います。
「うん。パパが、一番、格好いい。」
「そうか。そうか。」
その後に、トラックを運転するのに集中するために、「キリリ」と、真顔になるパパも大好きでした。
**
パパは、五人兄弟の五男として、誕生しました。
「また、男か。」と祖父は言ったそうです。
だから、私が、ママのお腹の中にいて、男の子か、女の子か、まだ、わからないころから、パパは、「絶対に、女の子がいい。」と言っていたそうです。
「女の子が生まれた。」
電話で伝えられたパパは、なにもかも放り出して、ママと私のもとへ、かけつけ、
「ありがとう、ありがとう・・・・・・。」
と、泣きながら何度も繰り返したそうです。
そして私は、パパとママに尋常でなく、かわいがられて、恵まれた幼少期を、過ごしました。
**
私が、散々、はしゃいで、はしゃぎつかれてうとうとしていると、パパとママのヒソヒソ声がなんとなく、聞こえてきます。
「桂子、ねたか?」
「うん。ねむりかけているみたい。」
ママが答えると、パパはトラックのスピードを、おとします。
私は、いつも、それを確認して、深い眠りに、おちるのでした。
**
それなのに、いつの頃からか、パパの職業について、私は引け目を感じるようになってしまいました。
「桂子ちゃんのお父さんは、何をして働いているの?」
「トラックの運転手!!」
私が、はりきって答えると、訊いてきたおばさんは、
「ああ。トラックの運ちゃんね。」
と、軽蔑のまなざしで、私をみました。
これとは、多少違っても、”トラックの運転手“というと、見下したような言い方をする大人が、少なからずいました。
逆に、“医者”とか、“弁護士”とかの子供であると、親の七光りのようなものがあるということも、成長するとともに、わかってきました。
そんな私に、ママがいました。
「パパは、汗を流して働いてくれているのよ。ママと桂子が生活できるのも、全部、パパのおかげなのよ。」
ママは続けます。
「恥ずかしがることなんて、ないのよ。桂子は、お二階バスに乗ることが恥ずかしいの?」
「ううん。お二階バスも、パパもママも、大好き。」
「じゃあ。いいじゃない。」
「うん」
**
あの頃から、歳月が過ぎ、パパも定年を迎えました。私も、四十歳になり、あの頃のパパの年齢を、追い越しました。
今だから、わかります。
“一家の大黒柱”として働くことが、どんなに大変か。責任感を持たなければ、ならないか。
(パパは、“お二階バス”に私を乗せていくことによって、働いている姿を、見てほしかったんじゃないかなあ。)と、思います。
“職業に貴賤は、ない”と、簡単にまとめることもできます。
ただ、「パパは、本当は、野球選手になりたかった。」ということを、私は、知っています。
家族のため、夢に、おりあいをつけて、生きるために仕事をしていたパパを、今でも、いい父親だと思います。
これからは、余生を楽しんでほしいです。今まで、ありがとう。
これからも、宜しくね。パパ。
豊崎 朋子(49) オーストラリア
朝起きれば、丼ぶりに、ドカンと入った野沢菜の漬物が食卓に上がっている。一服入れる時も、昼の時間も、夕飯の時も、必ず野沢菜の漬物がある。ここは、長野県の旧四賀村(現松本市)、父の生まれ育ったふる里だ。
毎年夏になると、神奈川県に住む私は、家族と一緒にここを訪ねた。
「よぅ、来たね。さぁ、上がりましょ」
花柄の割烹着をかけた伯母さんが、私たちをにこやかに笑顔で迎えてくれた。足の悪い婆ちゃんが、障子をガラッと開けて、居間からぬっと顔をだす。
「とわかったずら(遠かっただろう)。ほれ、茶でも飲んで、漬物食え」
家の中に上がると、今年もやっぱり野沢菜の漬物が、丼ぶりにこんもりと盛られていた。いやぁ疲れた疲れた、と言って父は、ズズズーっと茶をすすった後、つま楊枝二本を使って、3センチほどの長さに切られた漬物を、ザクザクザクっと4、5本串刺しにして、一口でバリボリバリ。私は茎の部分を一本だけ楊枝に刺す。小指をちょっと立てて、前歯でカミカミしていると・・・
「そんな食い方してぇ」
と、婆ちゃんが呆れている。この食べ方はどうも邪道らしい。とにもかくにも、子供だった私には、どうしてこんなに大人たちが、ボリボリボリと口を休めることなく野沢菜を食べるのか、不思議で不思議でたまらなかった。
そんなこんなで、帰りの土産は、やっぱり伯母さん特性の野沢菜の漬物。
「大した土産もなくてねぇ・・・」
と伯母さんが恐縮すると、
「いやぁ、これが一番の土産だよ」
と父は満面の笑顔で受取り、車のトランクに大事そーに詰め込むと、信州の山々を惜しみながら、くねくね曲がった山道を下って行った。
父は警察官だった。何事にもきちっとした性格で、警察が天職のように思えた。
ある日の晩、うぐいす色の包装紙に○○堂と印刷された菓子折りらしきものを持って帰宅した。父の手土産と言えば、大抵飲んだ時に駅前で買った天津甘栗だ。
それにしても珍しい。今日の手土産は、甘栗でもなく、時計の針は六時半。台所では、母は、あらかた晩御飯の支度が終わったとみえ、前掛けで手をふきふき、父の方をチラッと見た。そして、台所のテーブルに置いてある包みに目を向けた。
「あら、それなに?」
「・・・」
「誰からなの?」
「・・・」
父は大抵無言だ。聞いているのか、聞いていないのか・・・わからない。が、ちゃんと聞いている。
「お礼しなくちゃいけないわねぇ」
母が独り言のように言うと、
「礼なんていらないよ」
突然、父は口を開いた。
「そういうわけにはいかないわろねぇ?」
母は、隣にいた私に同意を求めるかのように言った。が、父は、何も答えずに、台所からすぅーっと出て行った。そして普段着に着替えて戻ってくると、テーブルの自分の席に腰を下ろし、その包をじっと見つめて、ぼそぼそっと話を始めたのだ。
うちの留置場に、コソ泥で捕まったのが入ってきてさぁ、そいつと当直の晩に、ちょこっと話したんだよ。そしたら、うちの田舎と同じような話し方するから、長野の生まれかって訊いたら、そうだって言うんだよ。だからさぁ、うちの野沢菜でも食わせてやろうかなぁと思って、弁当箱、ほら、あのカニの形をした弁当箱だよ、あれにちょこっと入れて持ってってやったんだよ。これでも食って、田舎のことを思い出せって言ったらさぁ、オイオイオイオイ泣きだすんだよ。声を上げてさぁ。お袋さんも泣いてるぞって驚かしたら、とにかくないてよぉ。俺もそれから気になって、もう一度野沢菜もって顔出して、お袋さんを泣かせるようなことだけはするなよって言ってやったよ。まぁ、それから俺もそっちに行かなくなって、気にはしてなんだけどな・・・。そしたら、今日、受付から電話があって、人が来てるっていうから、誰かと思って下に降りて行ったら、そいつがいてさぁ、おかげさんで目が覚めましたって、そう言うんだよ。仕事見つけて、初めて給料もらって、その金でこれ買って・・・。
父は、どこか遠い目をしていた。
「わぁ、わざわざあいさつに来てくれたんだね。なんか言ってあげたの?」
母は、ふいに父に尋ねた。
「いやぁ、言わないよ。そうかそうかって話聞いて、よかったよかったって、肩叩いてやっただけだよ。そしたら、世話になりましたって言ってさぁ、頭深く下げて、かえったよ」
お父さんって、こんなところがあるんだ。私はしばらく動けなかった。
ふと、外を見ると、車がいつもよりゆっくり通り過ぎていくような気がした。
「ふぅん。じゃぁ、これからは、まじめに働くんだろうねぇ・・・」
母は、つぶやくように言った。
「あぁ、そうだろうよ。未だに、あの時の漬物の味が忘れられないだとよ」
父は、来年九十歳になる。長年の習慣のせいだろうか。家の中でじっとしているのは、どうしても苦手らしい。今は、農家の畑を借りて、寒かろうが暑かろうが、毎日、ひとりもくもくと、野菜作りに精を出している。警察のカチッとした制服より、プ~ンと土のにおいのする作業服が良く似合う。
父は、シャキッと背筋が伸びたキューリを見ながら独り言のように言った。
生き物相手の趣味はいいぞ。生き物ってのは可愛がれば、まっすぐ育つもんだからなぁ・・・。」
父の何気ないその言葉から、ふとあの野沢菜の話を思い出した。父の見返りを期待しない無償の愛は、人に安心感と幸福感を与えている。遠く離れて暮らす父の顔を思い浮かべながら、私も父のような人になりたいなぁと、この年になってつくづく思う。
小松崎 潤(36) 東京都
教育係の父は何かにつけて「競争」という言葉を使った。
あれは中学三年の夏だった。僕は勉強が大嫌いで、通信簿は見事に「2」が揃っていた。3段階ならまだしも、当時は十段階である。さすがに両親は開いた口がふさがらず、父はすぐさま僕を集団塾にいれた。僕は全く乗り気ではなかった。勉強ができない僕はダメなやつって言われているみたいだから。
だけど父は言った。
「まあ、行ってみろ」
こうして始まった塾通い。そもそも僕は、ちゃんと勉強したことがないから持ちものすらわからない。だから恥ずかしいことに手ぶらで行ってしまった。
こうして初めて入った、つくし塾。そこは茶の間で勉強しているようなアットホームさだった。
僕は正直に話した。勉強が嫌いなこと。勉強の仕方がわからないこと。
すると米山先生が笑いながら言った。
「大丈夫よ」
だけど僕はかけ算さえ怪しかった。分数だってすっかり忘れていた。それでも先生は決して僕を馬鹿にせずに一から教えてくれた。
幸い、この塾はテストさえなければ誰かと争うこともなかった。競争、競争という割には父の選んだ塾は以外にも気楽な場所だった。
それから月日が流れ、友達が大学受験をする中で僕は専門学校へ行くことにした。なぜかって。それは勉強が嫌いだからだ。もう英語も数学もやりたくない。そんな安易な考えからだった。僕は勉強が嫌いだけど、お年寄りと子どもは好きだった。介護士か、保育士か。悩んだ末に介護の道を選んだ。まわりの友達からは「3Kだろ」と揶揄された。
「くさい、きつい、あとなんだっけ」
「きたない、だよ」
そんな会話は日常茶飯事だった。だけど全然気にならなかった。机で勉強するくらいならお年寄りの相手をしている方が幸せだから。
だけど就職してから3年目のこと。初めて移動の洗礼を受けた。新天地では当然右も左もわからず戸惑った。それに加え、もともと要領の悪い僕は周りの足を引っ張らないか気が気じゃなかった。気づけばいつだって時間と競争していた。
「あと三十分で食事介助をおわらせて」
「二時までにおむつ交換を済ませて」
頭の中は常にタイムスケジュールでいっぱいだった。そんな時、ナースコールで爪を切ってほしいとか散歩に行きたいとか言われると、ものすごく困った。
「ちょっと時間がないんで」
そう言って僕は断ってしまって。だけど本当はずっと後ろめたかった。だって僕らはやろうと思えば自分のことは何でもできるから。長くなった爪を切ることも、天気のいい公園を歩くことも。だけど老人ホームにいるお年寄りにはそんな自由がない。ああ、ぼくは何をしているんだ。
こうしてやってあげたいことと、やらなきゃならないことの狭間で僕はもがいていた。
すると異動してから二週間後、僕はついに四十度の熱をだした。突然のことだった。この日、僕ははじめて欠勤をし、その足で実家へ戻った。三年ぶりだった。居間に入るなり懐かしい畳の香りがした。しかし、すぐさま僕はどうしようもない気持ちに襲われた。もう行きたくない。もう死にたい。もう、もう。いっそ熱が下がらなければいいとさえ思った。しかし、神様は無惨にもたった一日で熱を下げてしまった。
翌朝僕は廊下をうろうろしていた。行こうか、休もうか。すすむ、とまる、もどる。気持ちも体もそんな感じだった。すると父がひょっこり顔を出して僕を呼んだ。
「おい、潤。なんかあったか」
僕は話した。父はそれを、うんうんと聞いていた。だけど最後に言ったんだ。
「まあ行ってみろ。介護ってさ、時間でやるもんじゃなくて、時間をかけてやるもんだろ」
ああ、そうか。僕は妙に納得して家をでた。
二日ぶりの職場は新鮮だった。だけど相変わらず僕は容量が悪かった。
おむつ交換ひとつとっても他の人より倍かかる。爪を切ろうとすれば他の方から呼び止められてしまい、なかなか仕上げることができない。だけど精一杯やってみた。そしたら気がついた。時間をかけてやるからこそ見えるものがあるんだって。お年寄りの嬉しそうな表情。さみしい、かなしい、傍にいてほしいという心の声。時間をかけるとそんな小さな表情まで見えてくる。確かに、たったひとりの力で、大きなことはできない。だけど、おおらかな気持ちで接すると「楽しい」とか「嬉しい」という気持ちが生まれて、自然と笑顔が増える。それは相手も同じだった。手をぎゅっと握れば喜んで、背中をさすれば「ありがとう」と笑った。そうか。僕にできることは、人の気持ちに寄り添うことなんだ。
そこで気づいた。父の考える「キョウイク」と「キョウソウ」の本当の意味。それは「今日、行く」と「今日、添う」ではなかろうか。
「とりあえず行ってみろ」
「時間をかけてやってみろ」
その言葉は僕に、一歩踏み出すことの大切さと、誰かに寄り添う事の意味を教えてくれた。
ああ、そうか。あの塾を選んだ父はその時既にそのことを教えてくれていたんだ。そんな気がしてならない。なんだか気づかなかった愛情が身に沁みて急に父に会いたくなった。
今年の夏は父のところにその答え合わせをしに行こうと思う。今さらちょっと、はずかしいけどな。
大西 賢(47) 東京都
高校一年生の一学期が終わって、通知表をもらった。しまった、と思った。通知表には5段階評価で「1」と「2」しか並んでおらず、「普通」を示す「3」は一つもなかった。
(こんな通知表を見たら、 父さん、悲しむだろうな)
そう思った。 我が家は兄も妹も優秀で、「4」や「5」ばかりが並んでいる通知表をもらっている。 そんななか、私だけ「1」と「2」のオンパレードなのだ。一体、どんな顔をしてこの通知表を見せればいいのだろう。
夕食の時間になり、 兄も妹も通知表を父に見せた。父は満足そうに笑った。
「さて、じゃあお前の通知表も見せてもらおうか」
そう言われて、仕方なく、私は通知表を見せた。
父は黙って通知表を見ていたが、ふいに、こんなことを言った。
「お前、将来に夢はあるか?」
「世界中を旅行したい」
正直にそう告げると、
「よし!それで充分だ!」
と父は言い、通知表を閉じた。
「どんなに成績が悪くても、お前が青年らしい夢を持っているのなら、それで父さんは満足だ。それ以上、何も望むものはない」
父は笑って言った。
父さんは子供に「優秀な学力」なんて求めていなかったんだね。青年らしい大志を抱いていること、そして我が子がそれを成し遂げるだけの健康な身体を持っていること、それだけで本当に充分だったんだね。
父さん、あの時は本当にありがとう。「1と「2」しかない通知表を見てもまったく動じず、ありのままの息子を認めてくれたその姿勢に、 本当に救われたよ。
松井 裕子(47) 茨城県
子どもの頃、父のタバコを買いに行くことが、ちょっとした小遣い稼ぎだった。目当ての銘柄はハイライト、当時百五十円。私に二百円を渡した父は、釣銭はとっておけ、と言った。しばらくしてから、父は銘柄をマイルドセブンに変えた。ハイライトの時は、ミスすることなく自動販売機のボタンを押すことができた私は、名前の似ていたセブンスター を二回ぐらい買って帰ったことがあった。父は、こっちじゃないんだけどなあ、と口をへの字にして受けとったが、そんな時は子ども心に私はいつもの小遣いを遠慮したものだった。
父はとにかくヘビースモーカーだった。私の弟曰く、一本火を点けたかと思うと、あっという間に灰皿に押し付けてしまう贅沢な吸い方で、もったいないのだそうだ。そんな弟は自分の娘が生まれたら、ピタッと禁煙したが。私達兄弟三人が独立し一緒に暮らすことがなくなった後も、父は変わらずタバコをくわえ続けていた。
ある日父を訪ねた時、よく行くいつものタバコの自動販売機の前での出来事について父から聞いた。
高齢の女性が財布から小銭を探しているようだった。しばらく待っていたが、なかなか 小銭が揃わないらしい。父は後から声をかけた。
「タバコを吸われるんですね」
すると女性は、
「すみませんね、遅くてね」
と言いながら、やっと彼女は目当てのタバコを購入することができた。近くのベンチで二人並んで座って一服。聞けば、女性は五年ほど前から愛煙家になったとのこと。病床の旦那さんから、
「お前、俺が死んだら気晴らしにタバコ覚えてみたらどうだ」
の言葉がきっかけだということ。思えばあれは、遺言かしらと思い出し笑いをし、寂しさを伴いながらもそれ以来、たまにタバコを買いに来るということ。普段無口な父が、そんな風に人とコミュニケーョンをとるなんて意外に感じた。
健康増進法の成立、受動喫煙対策が二〇二〇年より全面施行、相次ぐタバコ価格の値上 げ、愛煙家の人々は、ますます肩身がせまくなってしまいそうだ。生命として限界を迎えているという父の主治医の言葉を聞き、もうタバコをくわえることがなくなった父の寝顔を見ながら、私はタバコが取り持った幼い頃の思い出や、父がタバコを介した人との関わりの一端について、ぼんやりと考えていた。
星野 ゆかり(32) 静岡県
「写真撮ってよ、パパ!」
満開の桜トンネル。紺碧の海。赤く燃える紅葉。白銀の雪景色。どんなに美しい風景を背にして私がねだっても、一眼レフをぶら下さげた父はいつも首を横に振ってばかり。
「俺は風景カメラマンだ。人物は撮らないよ」
それが決まり文句。
「一人娘よりも景色の方が大事なの?」
幼い頃から私は不満だった。だから家族旅行に行っても、思春期を迎える頃には父に「写真を撮って」と頼まなくなっていた。
そして、 大人になった私は次第に家族と出掛ける事もなくなっていった。
一年前。三十年間暮らした故郷を遠く離れた地へ私は嫁いだ。
嫁入り前夜、居間で母としんみり語っていると、父が沢山の冊子を抱えて現れた。
「嫁入り道具だ。持っていけ」
照れ隠しなのか、無愛想に手渡す父。
一目で手作りと分かる製本。丁寧に綴られた装丁には、全て同じ文字が印字されていた。
『ゆかりの十二ヶ月』
唯一違うのは元号だけ。平成元年から始まり、平成三十年まで一年も欠かさず揃っていた。驚きながら中を開くと…
それは、父手製のオリジナルカレンダーだった。春夏秋冬、三十年分の十二ヶ月の『私』がいた。母と手を繋いで桜並木を歩く入園式の私。祖父と海で西瓜割りをしている小学生の私、中学の体育祭でリレーのアンカーを走る私。旧友とはしゃぐ成人式の振袖姿の私。
そこには、カメラ目線の私は一人もいない。全て父の隠し撮り写真。だからこそ、自然な笑顔。父だから娘の一番『いい顔』を知っていたのだ。
大きくプリントされた私の写真の下の、カレンダーの日付欄に印字された文字は…
「入学式」「運動会」「テニスの試合」「卒業式」「結納」…
全て私に纏わる行事で埋め尽くされていた。
父の愛情に彩られた十二ヶ月×三十年。
「なーんだ、風景よりも私の方が大事だったんじゃん」
世界でただ一つだけの手作りカレンダーを抱き締めながら、三十年越しに父の愛情を泣き笑いで痛感した。
「ありがとう、パパ」